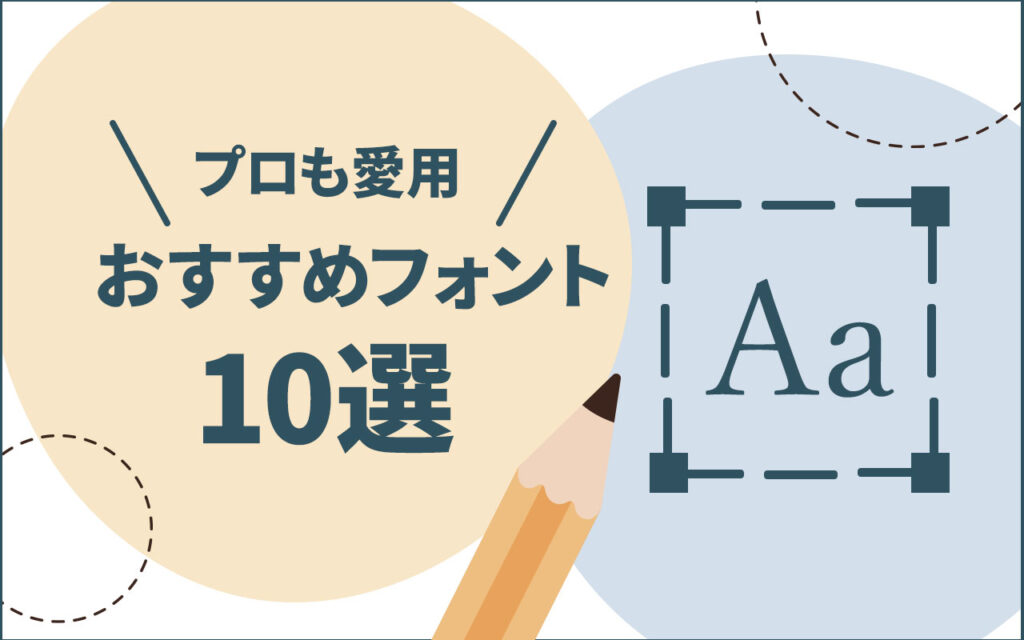【無料あり】記事作成におすすめの生成AIツール10選!活用メリット・デメリットも解説
近年注目されている「生成AI」を記事作成に活用したいと考えている方は多いのではないでしょうか。手作業で執筆するよりも、生成AIが出力したほうがスピーディーな場合が多く、工数削減のためにも取り入れてみたいと検討している方は多いでしょう。
そこで、今回は記事作成に生成AIを活用するメリットやデメリット、注意点のほか、おすすめの生成AIツールについてご紹介します。
記事作成に生成AIを活用するメリット
記事作成に生成AIを活用するメリットとしては何が挙げられるのでしょうか。まずは、記事生成に生成AIを使うことの利点を見ていきましょう。
記事作成時間を短縮できる
生成AIの最大の強みのひとつが、記事作成にかかる時間を大幅に短縮できる点です。例えば、1,500文字程度の記事をゼロから執筆する場合、人間のライターでは2〜3時間かかることもあります。
しかし、生成AIを使えば、構成の設計から本文の草案までをわずか数分で自動生成することが可能です。そのまま公開できる品質ではなくとも、修正や追記を加えるだけで記事が完成するため、執筆作業の「骨組み」部分の時間を大幅に削減できます。
限られた時間の中でも複数記事の同時進行が可能となり、全体の制作スピードが向上するでしょう。
少ないリソースでも安定した数を作成できる
記事作成に生成AIを使うことで、小規模なチームや個人事業主でも、継続的に記事を量産することが可能です。仮に、社内にライターが1名しかいない場合でも、AIが構成案やベースの文章を出力してくれるため、人手不足に悩まされることなく、定期的にコンテンツを更新できます。
特に、SEO対策として定期的な記事投稿が求められるWebメディア運営では、安定して継続的に作成できることは重要でしょう。
また、繁忙期に一時的に記事本数を増やしたいといった場面でも、AIは即戦力として活躍してくれるため、リソースの不足を補う心強い味方になります。
部分的な活用ができる
生成AIは、すべての工程を自動化する必要はなく、用途に応じて「部分的に活用する」という使い方が効果的です。
具体的には「構成案だけAIに任せて、本文は自分で書く」といった使い方や、「導入文だけAIに生成させ、結論はライター自身が考える」といった利用スタイルです。
構成や見出しの作成は時間がかかりやすく、アウトラインの精度で記事全体の質も左右されるものです。アウトラインの作成にAIを取り入れるだけでも、大幅な時短と品質安定が見込めます。
無理に全工程をAI任せにせず、自分の得意・不得意に合わせた利用ができるのが、AI活用のメリットでしょう。
文章作成に自信がなくても品質が高い記事が書ける
文章力に自信がない場合でも、生成AIを使えば高品質な記事を作成できます。AIは、入力されたキーワードやテーマに対して、適切な語彙・文法・構成で自然な文章を生成してくれます。
そのため、アイデアはあるけど文章化が苦手という人でも、AIのアウトプットを土台に執筆作業を進めることが可能なのです。また、AIの出力結果を添削・ブラッシュアップすることで、自分の文章力も自然と向上していくというメリットも期待できます。
ライティングの初心者からプロライターまで、誰でも一定以上のクオリティを担保した記事作成が実現できる点は、生成AIの大きな魅力と言えるでしょう。
記事作成に生成AIを活用するデメリット
記事作成に生成AIを活用するメリットは豊富ですが、一方で気を付けるべきデメリットも存在します。実際に生成AIを活用する前に、以下のデメリットを把握しておきましょう。
出力された情報が誤っているリスクがある
生成AIは過去に学習した膨大なテキスト情報をもとに文章を生成しますが、出力される内容が常に正確とは限りません。特に法務、医療、金融といった専門性の高い分野では、情報の正確性が極めて重要ですが、AIはその分野における最新情報や法改正などに対応できないことがあります。
また、「それっぽく見えるけれど根拠がない」といった文章が出力されることもあるため、そのまま公開すると誤情報を発信するリスクもあります。そのため、AIで生成した記事を使用する際は、必ず人間によるファクトチェックと編集が必要です。
文章のテイストや雰囲気が他の記事と類似しやすい
記事生成でAIを使うにあたって、デメリットになりやすいのが表現が他の記事と類似しやすいことです。生成AIは、広く使われている言い回しや構文を好んで使用する傾向があります。
AIで記事を生成してみると、他の企業やライターが書いた記事とテイストが似てしまうことがよくあります。特にSEO目的で量産されているコンテンツでは、「どこかで見たような文章」「目新しさがない」と感じられることが少なくありません。
結果的に差別化が難しくなり、ブランドの個性が埋もれてしまうリスクもあるでしょう。オリジナリティを出すには、AIから出力された文章に手を加え、自社のトーンや読者の感情に訴えかけるような調整が必要です。
文章の品質が低い場合がある
生成AIの出力は、そのまま記事として通用するケースもあれば、読みづらかったり、論理の流れが不自然だったりする場合もあります。
特に、複雑な構成が求められる長文記事や、論理展開が重要なコラム記事では、AIの出力だけではクオリティに不安が生じることも多いものです。また、AIが文脈を完全に理解しているわけではないため、主語と述語が食い違っていたり、微妙なニュアンスが伝わらなかったりするリスクもあります。
品質を重視するのであれば、必ず人の手で最終確認をおこない、文章を整える必要があるでしょう。
現場の経験や専門家の知見を交えた文章作成は難しい
生成AIは膨大な情報をもとに文章を作成しているため、「実際の現場での体験」や「専門家ならではのリアルな知見」などの一次情報の反映は難しいのが現状です。
例えば、製造業の工場現場で起きたヒヤリハットの事例や、医師や税理士が実務で感じる課題意識などは、実際にその立場にいないAIでは、正確に表現することは難しいといえます。
AIはあくまで公開情報や過去データをもとに推測的に記述するため、臨場感や説得力に欠けることがある点を覚えておきましょう。
記事作成に生成AIを活用する際の注意点
記事作成に生成AIを使用するメリット・デメリットを踏まえたうえで、どのように活用していくべきかを考える必要があります。仮に記事作成に生成AIを使用するとしたら、どのような点に注意したら良いのか、以下から見ていきましょう。
必ず事実確認(ファクトチェック)をする
記事作成に生成AIを活用する際には、公開前に必ず事実確認をしましょう。生成AIによる記事作成は非常に便利ですが、出力された内容をそのまま使用するのはリスクが高い行為です。AIは信頼性の高い情報だけでなく、不正確なデータや古い情報を基に文章を生成することもあるからです。
特に、医療・法律・金融などの専門分野では、事実誤認があると重大なトラブルに発展する恐れがあるのです。AIが出力した文章は、必ず人の手で一次情報と照らし合わせ、ファクトチェックを徹底しましょう。
たとえば、統計データは出典元を明記し、法律や制度に関する記述は最新の情報かどうかを確認する必要があります。AIはあくまで「補助的なツール」であることを理解し、最終的には人の判断を優先させることが重要です。
コピペの一致率を確認する
生成AIで記事を作成したら、コピペの一致率を確認してください。生成AIは既存の文献やネット上の情報を学習して文章を生成します。そのため、まれに他記事と構成や文体が酷似したり、一部が別の記事や文献と一致したりしてしまうことがあるのです。
納品前には「CopyContentDetector」や「こぴらん」などのツールを活用し、コピペ一致率を確認するのが望ましいでしょう。
指示する段階でトンマナや読者層を指定する
生成AIを使って記事作成をする際には、指示する段階でプロンプトに配慮する必要があります。生成AIは与えられた指示に忠実である一方、あいまいなプロンプトでは出力の精度が落ちてしまい、意図しない文章になるリスクがあります。
生成AIを使って記事を作成するのであれば、記事のトンマナや読者の属性を事前に具体的に伝えることが、品質の高いコンテンツ生成につながります。
具体的には、「経営層向けに、丁寧かつ論理的に説明して」「20代女性向けにやさしい言葉で親しみやすくまとめて」など、ペルソナと語り口のイメージをセットで伝えるのが効果的です。
また、フォーマットや見出し構成も事前に決めておくことで、記事全体の統一感が出やすくなります。AIは「指示の質=出力の質」になるため、上流のプロンプト設計を丁寧におこなうことが必須なのです。
AIで記事作成する際に使えるプロンプト例5選
生成AIが出力する文章の品質を高めるためには、「どのような指示をするか」が重要です。ここからは、生成AIで記事作成をする際に便利なプロンプトについてご紹介します。
記事構成を考えるときのプロンプト
生成AIは、与えられたテーマやキーワードをもとに、見出し構成(H2・H3)を論理的に整理することを得意としています。
SEO対策や読みやすさを考慮したアウトラインをAIに提案してもらえば、執筆全体の時間短縮にもつながるでしょう。構成が明確であれば、次のステップとなる「執筆」もスムーズに進みます。
【プロンプト例】
- BtoBコンテンツマーケティングというテーマで、H2・H3構成のアウトラインをSEO対策を意識して作ってください
- フリーランスの確定申告に関する記事の構成を、初心者向けに提案してください
- 在宅ワークで使える便利ツールというテーマで、読者がすぐに使いたくなるような構成を作ってください
本文執筆を依頼するときのプロンプト
アウトラインを作成したら、実際に執筆の指示を生成AIに出していきます。とはいえ、「見出しに合わせて記事を書いて」と指示するだけでは、文章ボリュームや文体などが、想定していたものと異なる場合があります。
そのため、どのような文章を求めているのかを正確に生成AIに指示しなければなりません。
【プロンプト例】
- BtoBコンテンツマーケティングのメリットについて、初心者向けに500文字で本文を書いてください
- クラウド会計ソフトの比較というH2の本文を、堅めのビジネス口調で作成してください
- SNS運用のよくある失敗例というH3の本文を500文字で、20代マーケター向けに説明してください
タイトルを作成してもらうときのプロンプト
生成AIにタイトル制作を指示する際は、「SEOキーワードを含める」「具体性を持たせる」「共感を誘う言い回しにする」といったポイントを盛り込むように指示しましょう。
また、複数のタイトル案を生成させ、それぞれを比較したうえで人が選ぶこともおすすめです。タイトル案を10個ほど出してもらえば、その中から記事に適したものを選びやすくなるでしょう。
【プロンプト例】
- 「生成AI 記事作成 メリット」というキーワードを使って、クリックされやすい記事タイトルを10個提案してください
- 「在宅ワーク デメリットに関するSEO記事のタイトル案を10個ください。共感を誘う形にしてください」
- 「副業ライターの始め方」というテーマで、初心者が興味を持ちそうなタイトルを3案作ってください」
導入文を作るときのプロンプト
生成AIに導入文を作成させるときは、「誰向けの記事か」「どんな悩みを持っているか」「記事で何を伝えるのか」を明確にするのがコツです。
また、あらかじめ文字数も指定しておくと、文章のボリュームが極端に増えたり、不足したりする心配がありません。
【プロンプト例】
- 「クラウド会計ソフト 初心者向け」という記事の導入文を200文字で作ってください。
- 「BtoBマーケティングとは?」という記事のリード文を、ターゲットがマーケ初心者だと想定して作成してください
- 「副業で稼ぐにはどうすれば良い?」という悩みを持つ20代会社員向けに、導入文を250文字で書いてください
事例・具体例を出してもらうときのプロンプト
生成AIは豊富な知識から、実在企業の取り組み例や仮想のストーリー形式の例を出すことが可能です。特定の業種や状況を指定すると、より読者に合った例が生成されやすくなります。
また、複数の例を出力するよう指示することで、記事全体のバリエーションや情報密度も向上しやすくなるでしょう。
【プロンプト例】
- 生成AIで記事作成を効率化した企業の事例を1つ紹介してください
- 副業を始めた会社員の成功事例を2つ、実在するかのようなリアルな内容で作成してください
- BtoB企業がホワイトペーパーを活用した成果例を1つ挙げて、成果と背景を含めて解説してください
| ▼参考 【バクヤスAI 記事代行 紹介情報 】 ・会社名:TechSuite株式会社 ・会社所在地:〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目19-1 芝浦アークビル 2階 ・創立年:2021年9月 ・提供サービス:バクヤスAI 記事代行は、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップで支援し、高品質な記事を、圧倒的なコストパフォーマンスで提供するサービスです。 ・参考URL:https://bakuyasu.techsuite.co.jp/ |
【無料】記事作成におすすめの生成AIツール5選
ここからは、無料で記事作成に使用できる生成AIツールをご紹介します。使いやすく、直感的に活用できる生成AIツールを厳選していくため、参考にしてみてください。
Chat GPT
出典:Chat GPT
ChatGPTは、OpenAIが開発した対話型の生成AIツールで、自然な文章生成に優れた生成AIツールです。日本語の処理能力が高く、記事作成にも広く活用されています。
テーマを与えるだけで、構成案から本文作成、要約、リライトまで柔軟に対応できるのが特徴で、工数削減を目指したい方にもおすすめです。
また、SEO対策を意識したキーワード設計や、読者層に応じたトンマナ調整も得意で、初心者でも使いやすいのが魅力です。
Gemini
出典:Gemini
Geminiは、Googleが開発した対話型AIツールで、Web検索との連携性が高いのが最大の特徴です。ChatGPTと異なり、Google検索での結果をベースに情報を出力しているため、最新の情報や信頼性のある情報を活用した記事作成に適しています。
また、GoogleドキュメントやGmailなどのGoogle Workspaceとの親和性が高く、普段の業務でGoogleサービスを使っている人にとっては非常に扱いやすいツールといえるでしょう。
PlayAI
出典:PlayAI
PlayAIは、ブラウザのみで使用が可能なAIライティングツールです。Web記事や広告文、SNS投稿文など幅広い形式の文章に対応しています。
Chat GPTやGeminiと比べると、生成までに時間がかかるといった難点があるものの、UIは非常にシンプルで、必要な入力項目が少なく、複雑な機能もありません。
また、他のユーザーが生成した文章を作品として楽しめるなど、一般的な生成AIにはない魅力もあるのが特徴です。
User Local AI WRITER
User Local AI WRITERは、日本の企業「ユーザーローカル」が提供する無料のAIライティングツールです。SEOに強い記事生成を目指して開発されており、キーワードを入力すると、それに基づいた見出し構成や本文のドラフトを自動で作成してくれます。
日本語の言い回しや文法も自然で、ビジネス用途でも安心して活用できます。ただ、キーワードを入力してから出力されるまでに1~2分要するため、待ち時間が発生してしまうのが難点です。
また、キーワードベースで出力されるため、文字数の調整や方向性の指示、ターゲットの指定などの指定が難しいといった注意点もあります。
Claude
出典:Claude
Claudeは、ChatGPTと似た対話型のスタイルを採用した生成AIツールです。倫理性や安全性を重視して開発されていて、ビジネスシーンでの活用やナレッジ共有にも適した出力内容が期待できます。
誤情報を出力しないためのトレーニングも実施されているため、ファクトチェック段階での大幅な修正リスクが少ない点が魅力です。
プロンプトに対する回答も一貫性があり、文章構成力も高いといった特徴があります。
【有料】記事作成におすすめの生成AIツール5選
ここからは、有料で品質の高い生成AIツールを5選ご紹介します。費用がかかる分、出力文章の品質が高かったり、機能が豊富であったりするツールが多いため、ぜひチェックしてみてください。
TACT SEO
出典:TACT SEO
TACT SEOは、記事構成から本文執筆までをAIが支援するSEO特化型ツールです。主にBtoB企業やコンテンツマーケティングを本格的におこないたい企業向けに設計されています。キーワードの入力だけでSEOを意識した構成案や本文を自動生成できるのが特徴です。
また、AIによる見出し・構成の提案機能だけでなく、関連ワードや上位表示記事の傾向分析機能も搭載されています。そのため、企画からライティング、入稿までのフローにおいて、活用することが可能です。
トランスコープ
出典:トランスコープ
トランスコープは、SEOのプロも活用するSEO記事作成支援ツールです。単なる文章生成ではなく、競合調査や検索ニーズの分析、見出し案の提案、記事構成、さらには文章の自動生成までがワンストップでおこなえるのが特徴です。
特にSEOに強い構成案を出力できる機能が優れており、マーケティングやメディア運営などの現場でも広く導入されています。
Catchy
出典:Catchy
Catchyは、Webライティング・SNS投稿・広告コピー・動画スクリプトなど、あらゆるコンテンツ作成をAIで支援する万能なツールです。生成パターンが豊富で、テンプレートの種類も100種類以上に及びます。
専用のフォームが設けられているため、プロンプトに慣れていない初心者でも、目的に合わせた高品質なテキストを出力してもらえます。
Catchyの有料プランでは、月間の生成文字数が拡張されるほか、出力された文章を再編集・複製・保存するなどの便利機能も使用可能です。マーケティング業務や中小企業の広報活動においても使いやすいツールでしょう。
Articoolo
出典:Articoolo
Articooloは、もともと英語圏で活用されていた自動記事生成ツールです。AIが与えられたキーワードから自然な構成と文章を瞬時に作成してくれます。
日本語には対応しているものの、テーマによっては出力された文章に違和感が生じてしまう場合があります。ただ、英語で記事を量産したいなど、グローバルな展開を視野に入れている方にはピッタリの生成AIツールです。
英文であれば、有料ならではの品質の高さが期待でき、コストパフォーマンスにも優れているため、英語メディアを運営している方は検討してみてください。
RakuRin(ラクリン)
RakuRin(ラクリン)は、SEO対策用の記事をスピーディーに量産したい方向けのAIライティングサービスです。見出しを入力すると、AIが記事構成と本文を自動で作成してくれるため、生成AIの操作に不慣れな人でも簡単に操作できます。
また、日本語特化型のため自然な文章が出力されやすく、記事納品までの時間を大幅に短縮できる点が魅力です。有料プランでは、複数アカウント管理やライターへの共有・出力フォーマットの柔軟な対応など、チーム利用にも最適な設計がなされています。
まとめ
今回は、生成AIで記事を作成するメリットやデメリット、注意点のほか、便利なプロンプト、おすすめツールなど、幅広くご紹介しました。
高品質な文章を生成するAIが増え、ビジネスシーンでも問題なく利用できるケースが増えてきています。
ただ、一方で出力文章の情報が誤っているリスクや、適切なプロンプトが必須である点など、不安な点が多いのが現状です。
THINkBALでは、そんな記事作成に悩む企業様向けに、コンテンツ制作サービスを提供しています。生成AIでは不安が残る専門性の高いコンテンツも、プロのライター及び編集者が正確な情報に基づいて制作することが可能です。
ぜひ、記事作成でお悩みの方は、一度THINkBALまでご相談ください。
リード獲得につながるコンテンツ制作
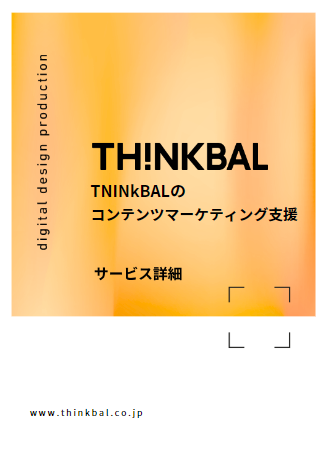
コンテンツ制作やリード獲得で悩んでいませんか?
- Webからの売り上げを増やしたい
- コンテンツの制作をしてリードを増やしたい
- 潜在的な顧客を獲得したい
コンテンツマーケティングの制作なら
THINkBALにお任せください
Works
事例紹介

Relation 関連記事

- Web制作
2023/10/9Webサイト改善におすすめの施策12選|陥りやすい失敗についても紹介
- Web制作
2023/10/1【売上向上に効果的面!】コーポレートサイトの改善のポイント20項目
- コンテンツマーケティング
2024/9/16ホワイトペーパーの効果3選!主な6つの種類と効率的な作成方法とは
- SEO
2025/5/14【保存版】SEOを用いたサイト改善の全手順|よくある失敗パターンと成功のコツ
- コンテンツマーケティング
2025/1/31リライトの注意点は?検索順位を下げないための対策
- SEO
2025/10/22戦略設計なしでSEOを進めると100%失敗する?具体的な設計方法とは
What's New 新着情報

- Web制作
NEW2026/1/31パーソナルジムのホームページ制作で集客する方法とおすすめ制作会社8選
- Web制作
NEW2026/1/31WordPress制作会社おすすめ25選!費用相場と選び方を徹底解説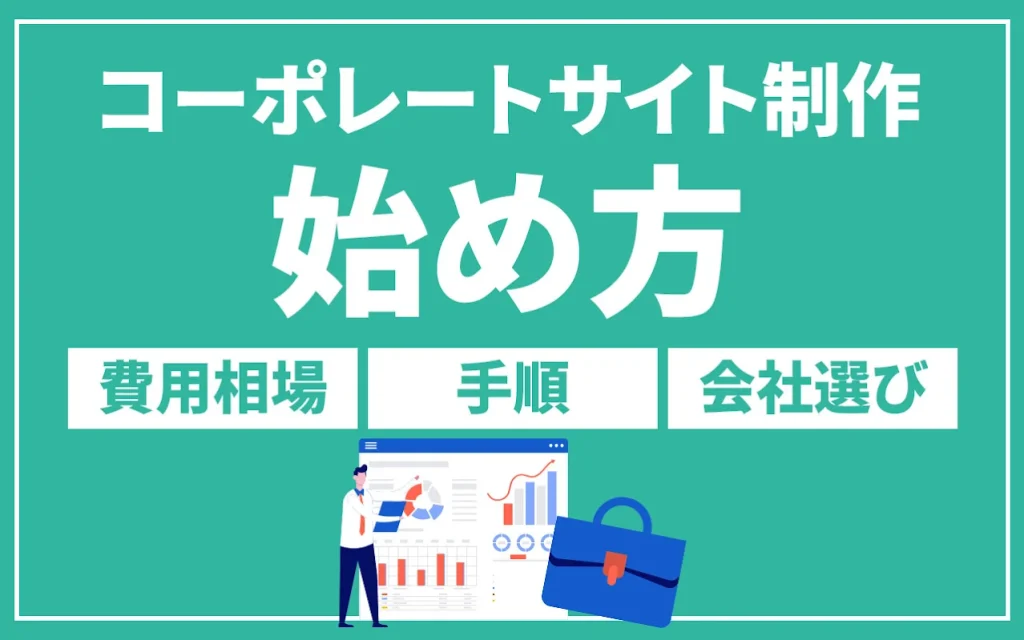
- Web制作
2026/1/31コーポレートサイト制作の始め方|費用相場・手順・会社選びを解説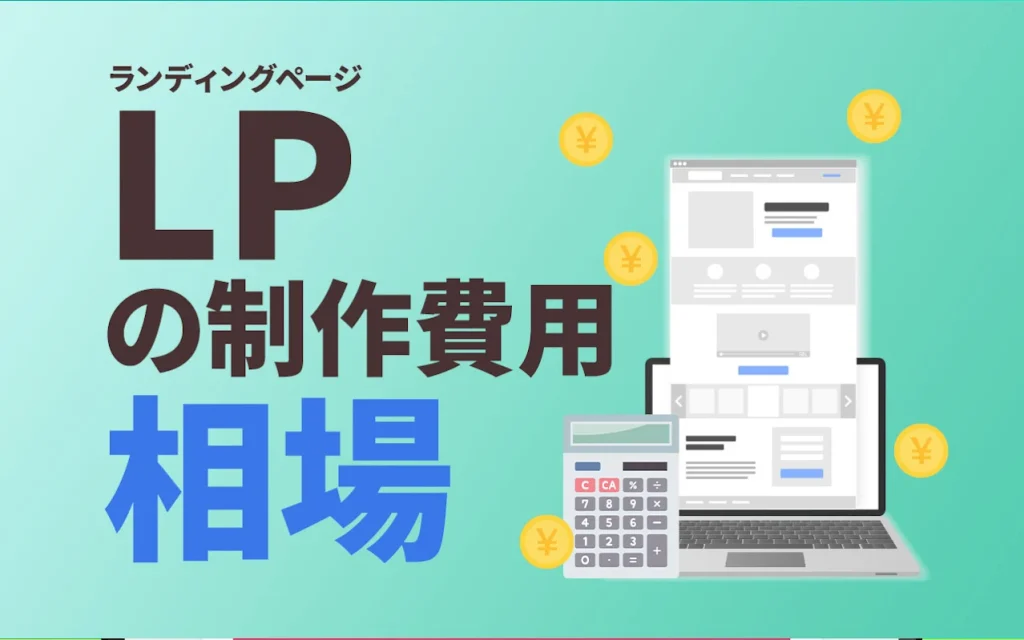
- Web制作
2026/1/31ランディングページの制作費用の相場は?内訳や料金事例を徹底解説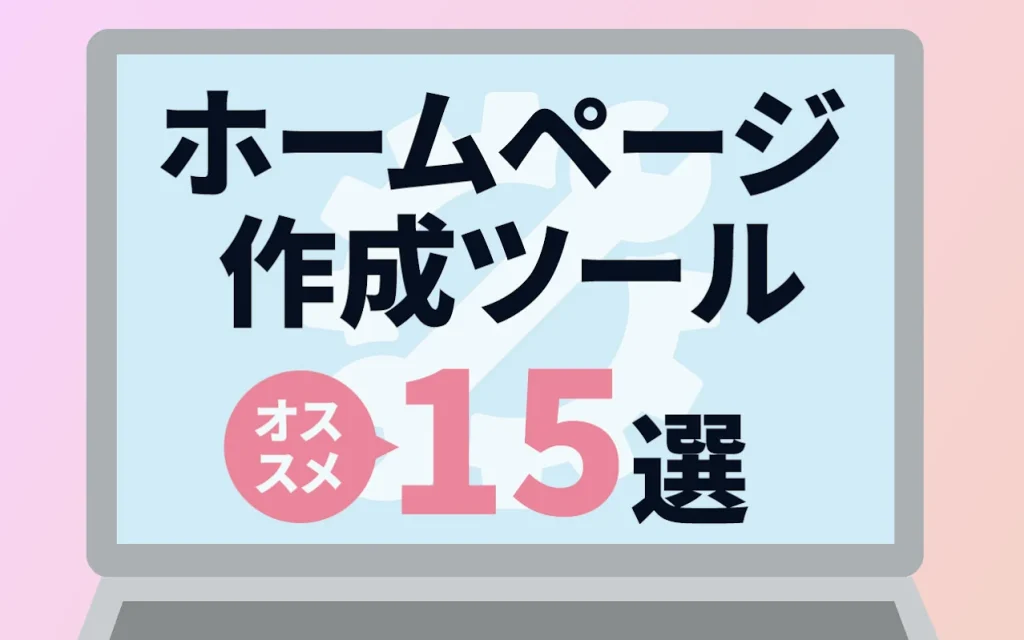
- Web制作
2026/1/31ホームページ作成ツールおすすめ15選【2026年最新版】無料・有料のツールを用途別に徹底比較!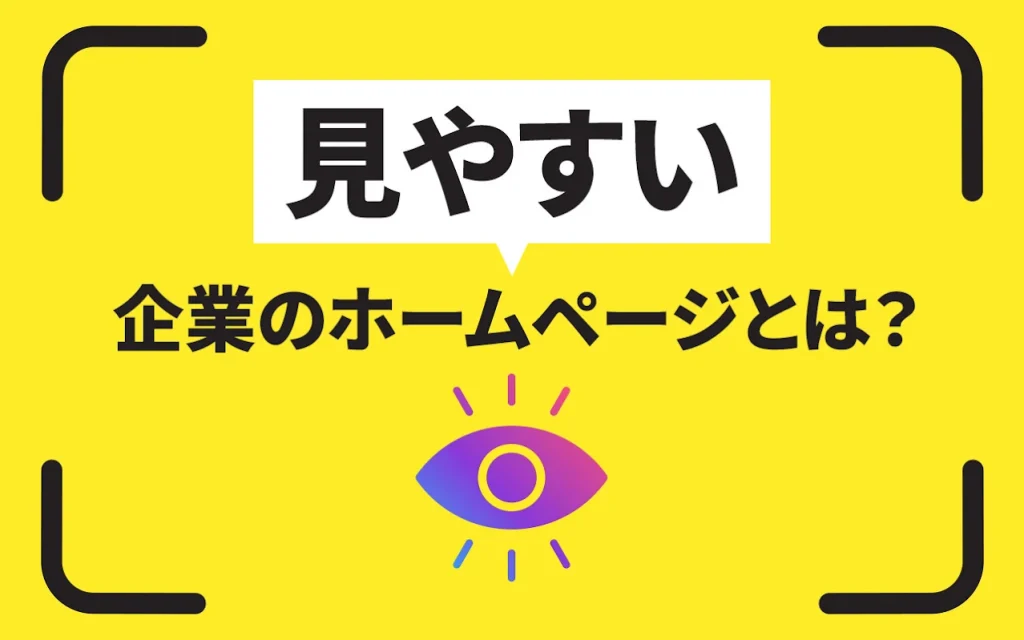
- Web制作
2026/1/31見やすい企業のホームページとは?参考例やポイントを解説!
Recommend オススメ記事
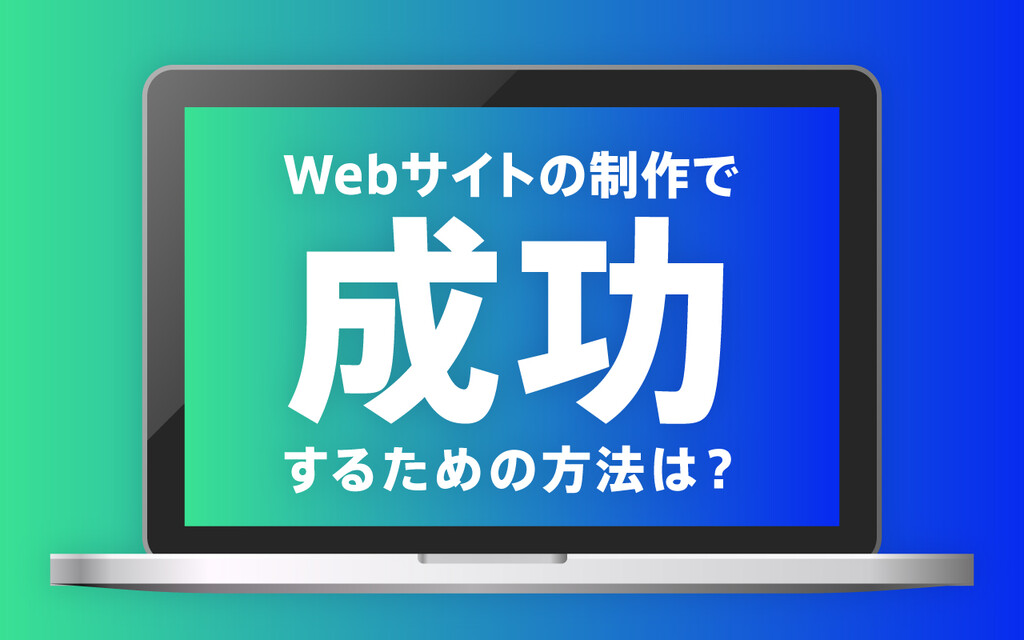
- Web制作
2025/9/19BtoBサイトでおすすめの制作会社15選|BtoBビジネスで成功するには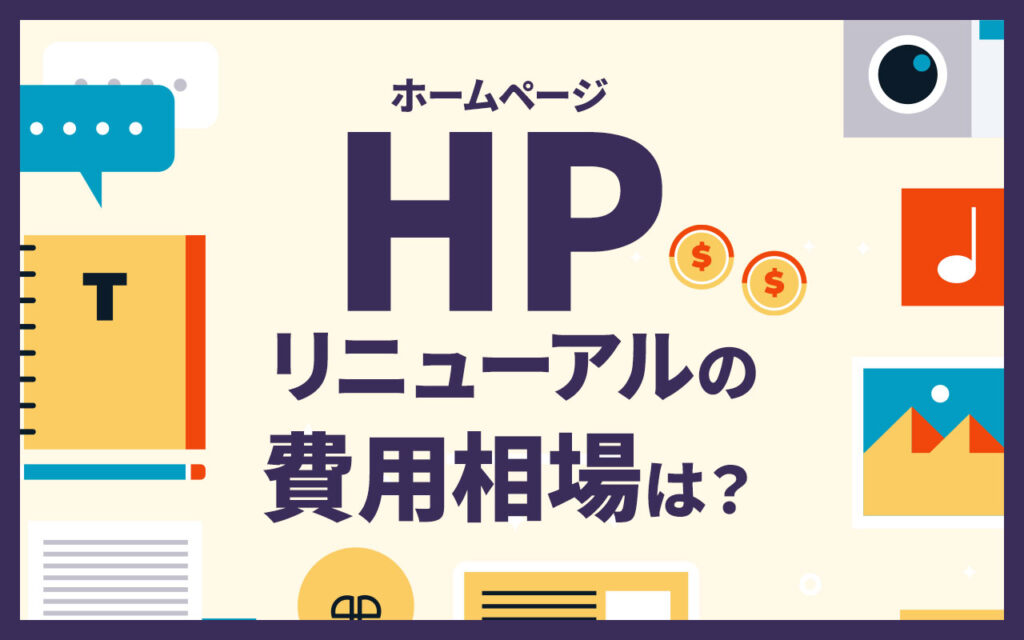
- Web制作
2025/10/2ホームページリニューアルの費用相場は?内訳と安く抑えるポイントを解説
- Web制作
2024/4/28採用サイトの集客方法5選!採用に必要なコンテンツは?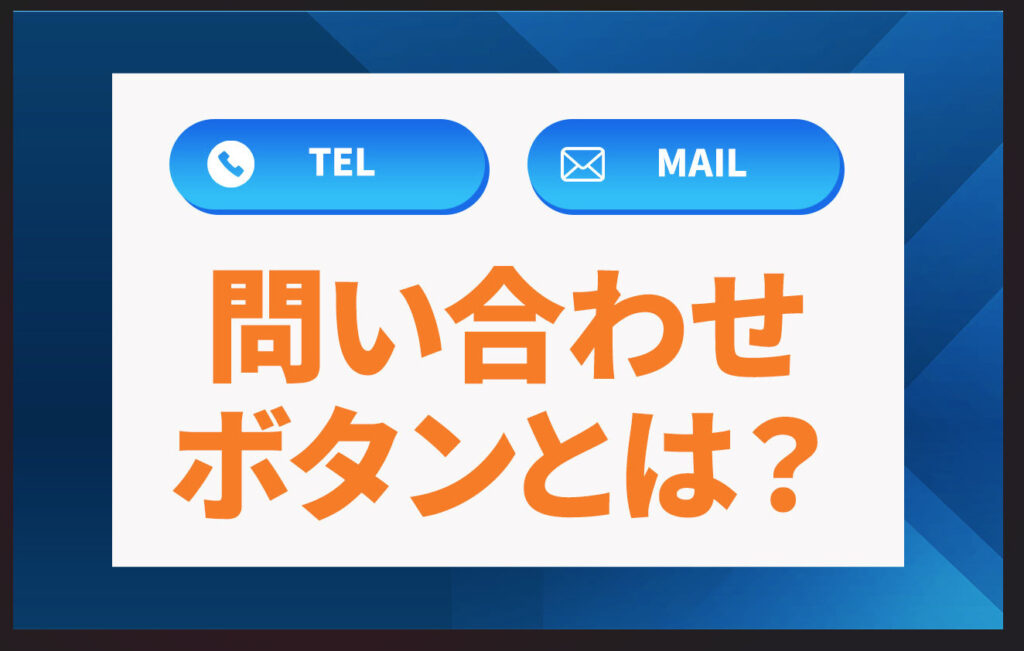
- UX/UIデザイン
2025/11/30問い合わせボタンとは?効果的なデザインと作り方・参考事例10選を徹底解説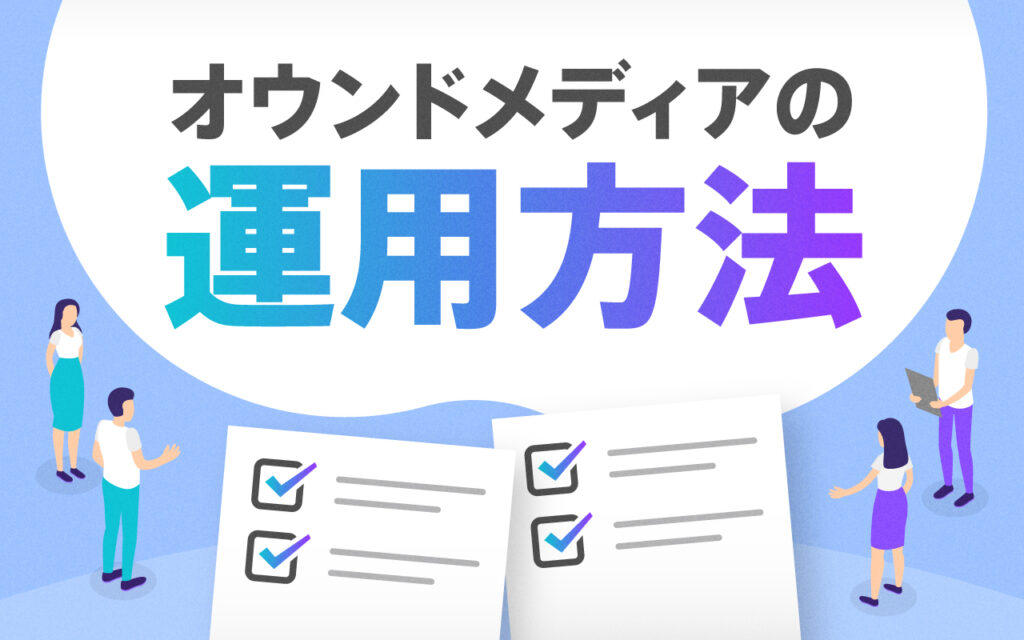
- Web制作
2024/9/19オウンドメディアの運用方法|成果の出るポイントを押さえて運用しよう
- Web制作
2026/1/5ブランドサイト事例15選!デザイン参考例と制作の流れを徹底解説
- Web制作
2025/9/30コーポレートサイトのSEO対策は必要?対策方法や注意点
- Web制作
2024/5/5採用サイトの改善方法とは?課題の見つけ方やリニューアルのポイントについても解説
- コンテンツマーケティング
2024/4/6コンテンツマーケティングの効果的な進め方とは?3つの成功事例も紹介