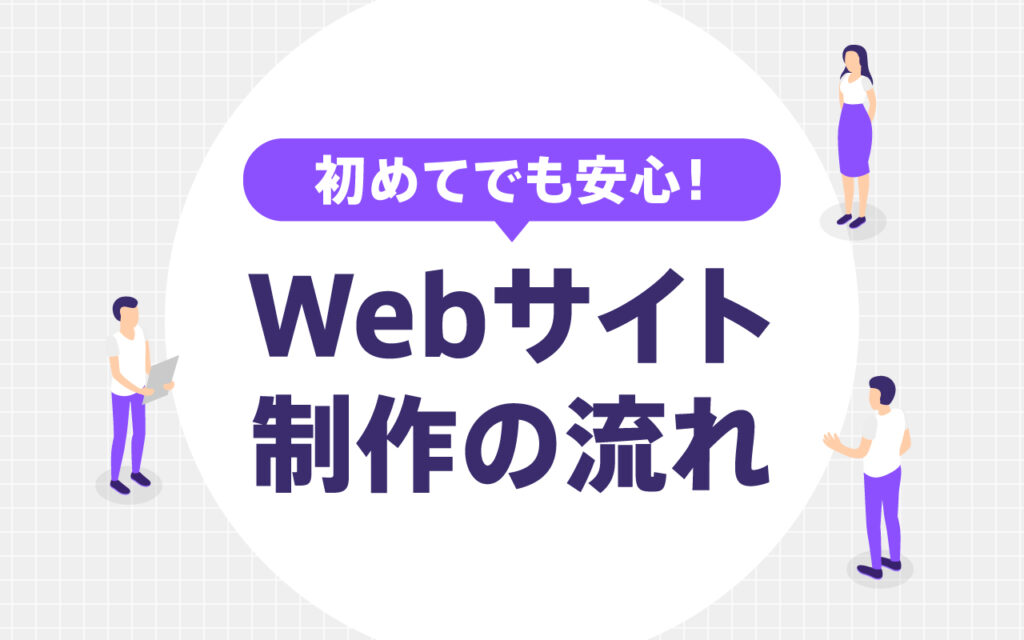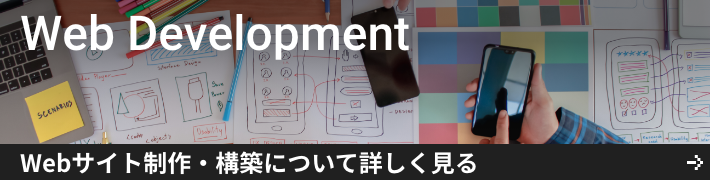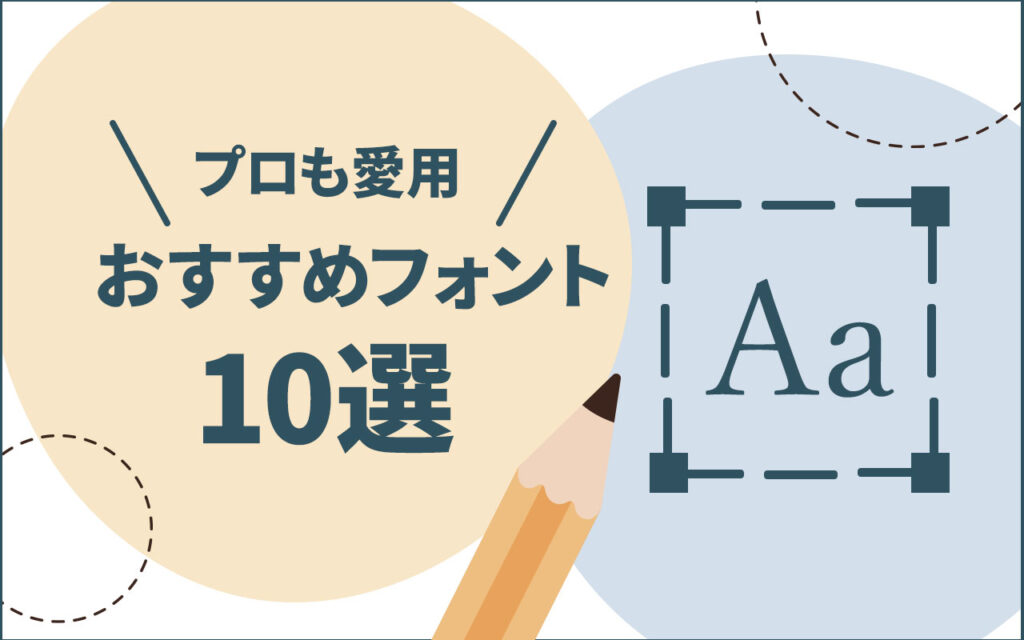Webサイト制作の契約書の重要チェックポイントと具体的な書き方
Webサイト制作に関する契約書について詳しく知りたい、契約書の中身って何を書けばいいのかわからないなど、こういった悩みを抱えた人も多いのではないでしょうか。
この記事では、Webサイトを発注する上で秘密保持契約書や業務委託契約書といった契約書の書き方がわからないと悩んでいる人に向け、下記を紹介していきます。
- 契約書を作成する意味を知りたい人
- 契約書に記載する項目と具体的な内容を知りたい人
- 契約書を作成する際の注意点について知りたい人
契約書の書き方を誤ってしまうと、後になって大きなトラブルにつながってしまう危険性があります。本記事で紹介する注意点を押さえ、業務をスムーズに進行させられる良い契約書を作成していきましょう。
Webサイト制作の契約書は主に2種類

Webサイト制作で交わす契約書は主に以下の2つです。
- 秘密保持契約書
- 業務委託契約書
以下では、それぞれの契約書に記載する内容、契約を交わす意味などについて解説していきます。
秘密保持契約書
秘密保持契約書とは、制作会社からサイトの制作や運営に関わる情報を入手した際、それを第三者に公表しないことを求める契約です。
制作会社が公開してほしくない情報とは、たとえば、制作にかかる詳細な費用や制作会社が独自に所有するノウハウなどを指します。
これらの情報が口外されてしまうと制作会社は利益に関わるため、秘密保持契約書を交わします。なお、秘密保持契約に違反があった場合、制作会社側から損害賠償の請求を受けることもあります。
業務委託契約書
業務委託契約書は、制作会社が遂行する業務内容を記載し、その内容をお互いが承認したことなどを記した契約書です。
ホームページ制作、サイト制作の場合においては、
- 費用
- 納品日
- 検収期間
- 作業範囲
などを記載します。
口頭での約束だと納品後にトラブルを招く可能性があるため、サイト制作を依頼する場合は必ず契約書を作成しましょう。
Webサイトを制作する際に契約書が重要になる理由

Webサイトを制作する際に契約書が重要になる2つの意味は下記の通りです。
- 契約書がないと作業負担が不公平になる可能性がある
- 作業が始まってからのトラブルを減らすため
これらの理由について少し詳しく解説していきます。
契約書がないと作業負担が不公平になる可能性がある
契約書がないと遂行すべき業務が不明確になり、制作会社と依頼主側での作業負担が曖昧になってしまうでしょう。どちらが進めるべき作業なのか、事前に決めておくことで制作をスムーズに進めることができるのです。
また、制作会社によっては業務委託契約ではなく、リース契約を持ち掛けてくるケースがあります。リース契約は、業務ではなく「モノ」を借りる契約を指すため、契約満了時には制作したWebサイトを返却することになるので注意しておきましょう。
作業が始まってからのトラブルを減らすため
制作費用に関する契約をチェックしておかないと、追加発注した際に想定していなかった費用が上乗せされる可能性があり、これがトラブルへとつながることもあります。
たとえば、制作会社にサイトを納品してもらったあと、イメージと違ったとなり、デザインの変更を制作会社に依頼したとします。制作会社側はデザイン変更を追加発注とするので費用を請求します。こういった事象が生じたときに、契約面での記載があると非常に進めやすいでしょう。
どういった内容の変更であれば費用がかかるのか、明確にしておくのがおすすめです。
Webサイト制作の契約書に含みたい内容はこれ!項目別に内容を紹介

Webサイト制作の契約に記載する8つの内容は下記の通りです。
- 外注先にどこまで任せるのか作業範囲を決める
- オプションや追加費用の有無
- 費用の設定や支払い時期
- 修正作業と検収作業の規定
- 契約解除や存続についての規定
- 納品物の納品方法や納品時期などについての規定
- 納品後のフォローについての規定
- 作業中の納品物の著作権の規定
それぞれの項目ごとに記載すべき内容について詳しく解説していきます。
外注先にどこまで任せるのか作業範囲を決める
契約書には、制作会社に任せる作業の範囲を明記します。契約書に記載されていない作業を発注する場合は別途料金が発生かかるという点に留意しておきましょう。
自社でおこなう作業と制作会社に任せる作業を事前に決めておいて、打ち合わせの際などに先に話し合ったりして、入念にチェックしておきましょう。
こちらの記事では、Webサイト制作の基本的な作業内容や流れについて詳しく書かれています。作業範囲を決める際の参考にしてください。
オプションや追加費用の有無
作業範囲を決めたら、オプションや追加費用に関する記載も忘れずに行いましょう。
たとえば、契約書に「サイト全体のデザイン」「トップページに配置する画像の作成」「テストチェック」と記載している場合、ロゴ作成などはオプション料金として追加で請求されることになります。
どこからが追加費用になってしまうのか、明確に記載しておくと後々トラブルにならずに済むでしょう。
費用の設定や支払い時期
支払い時期や方法は制作会社によって異なります。サイトの制作が決まれば着手金として、一部の金額を支払う会社もあれば、作業のフェーズ毎に支払いをおこなう会社もあります。また、納品後は納品すれば支払いなのか、修正も完了した検収後での支払いなのか方法は会社にさまざまです。
契約書に明記しておくと、どういった支払い形態なのか確認することができるので、こちらも記載しておくと良いでしょう。
修正作業と検収作業の規定
検収とは、納品してもらったサイトが「依頼内容に沿ったものであるか」「望んだ効果を得られるか」といったことを見定めるための期間を指します。
検収期間が短く設定されていると、望んだ効果を得られているのかといった点が十分に精査できない可能性があるため、ある程度の日数を確保しておくこと重要です。
契約解除や存続についての規定
契約の解除、存続についての規定も明記します。
まず契約の解除については、依頼する側が強制的に契約を解除できるケースを記載します。依頼主が不利にならないよう、あらゆるケースを考えた上で記載するのがポイントです。
次に、存続についての期間も明記します。依頼内容がホームページの制作のみである場合は、契約の終了日のみを書いておけば問題ありません。しかし、SEO対策やWebサイトの管理などを同時に委託する場合は「どの期間が契約期間になるのか」を明記しておく必要があります。
納品物の納品方法や納品時期などについての規定
契約書には、納品物の納品方法や納品時期などについても詳しく記載します。
納品時期を記載する際のポイントは、制作会社が業務しやすいように配慮することです。納期の設定を早くしすぎてしまうと制作会社を焦らせることになり、完成度の低いWebサイトになる可能性があります。
また、納品の状態を詳しく記載しておくことで認識の違いを防ぐことができるため、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能です。事前に制作会社と話し合い、できるだけ細かく書けるようにしておきましょう。
納品後のフォローについての規定
納品後のフォローについての規定も記載しておきましょう。
Webサイト制作の場合、サイト内のデザイン修正、SEO対策、管理・運用、が納品後のフォローにあたります。納品後のサポート内容は各制作会社によって異なるため、事前に話し合っておくようにしてください。
また、フォローの継続期間を明確にしておきます。無料のサービスとしてフォローをおこなってもらう場合でも契約書には必ず記載しておきましょう。
作業中の納品物の著作権の規定
著作権の規定についてもチェックしておきましょう。一般的に、契約書に明記がなければ、サイト制作においては制作会社側に著作権があります。
支払いをして、制作をしてもらっても著作権が自動的に移転するわけではありません。契約書に発注者への移転を明記しておかなければ、別途著作権の譲渡費用を請求される可能性があります。
制作物の著作権については契約書で明らかにしておきましょう。
Webサイト制作の契約書で注意する点は?作成時のポイント

Webサイト制作の契約書を作成する際に注意するポイントは下記の通りです。
- 不明確な部分を失くしておく
- テンプレートを利用する場合でも自社用になっているか確認をする
- どこまでの費用が予算に含まれるのか明確にしておく
それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
不明確な部分を失くしておく
不明確な部分は必ず失くしておきましょう。
具体的には、
- 契約の金額についての詳細
- 契約期間はいつからいつまでなのか
- 制作会社と自社はそれぞれの作業範囲
などといったことについて再度確認します。
契約書は原則、合意した内容をもとに作成する必要がありますから、事前に話し合うことを忘れないようにしましょう。不明確な部分をなくしてから作業に入るとスムーズなので、契約書の作成は重要です。
テンプレートを利用する場合でも自社用になっているか確認をする
契約書のテンプレートを使用する場合、細かい項目などは自社用に変更や追記をおこないます。Webサイト制作用の契約書のテンプレートを利用する場合でも、自社用の内容になっているか、確認をして必要な項目は足しましょう。
どこまでの費用が予算に含まれるのか明確にしておく
サイト制作から運用・フォローまでのフェーズにかけて、どこまでが予算に含まれているのかを明確にしておいてください。
オプションなど、制作会社によってかかる費用はさまざまなので、細かい部分まで記載を確認しておく必要があるでしょう。
こちらの記事では、Webサイト作成における費用相場や費用の内訳について解説をしています。契約を結ぶ際、内訳なども知っておくとスムーズに進められるので、ぜひ参考にしてください。
Web制作を考えている人はTHINkBALにご相談ください
Webサイトの制作をお考えの人は、ぜひTHINkBALにご相談ください。THINkBALでは、お客様が抱える課題やサイト制作の目的に寄り添い、より的確で精度の高いWebサイトを提供します。
密なコミュニケーションで制作を進めていきますので、初めての方でも安心してご依頼ください。まずは何か分からないことがありましたらお気軽にご相談ください。
まとめ
本記事では、Webサイト制作の際に交わす契約書について解説してきました。
秘密保持契約と業務委託契約、どちらもお互いが同意した内容を記載するという点には十分留意しておきましょう。
分からない点、不明瞭な点はその場で確認し合い、お互いに了承した上で契約書に記載することが大切です。契約に関してわからないことがありましたら、THINkBALにお気軽にお問い合わせください。
信頼できるWeb制作会社を選び、理想のWebサイトを作る

課題解決に向けて動く、信頼できるWeb制作会社に依頼してみませんか?
- Webサイト制作会社の選び方がわからない
- Webサイト制作を失敗したくない
- 信用できるWeb制作会社を探している
Webサイト制作なら
THINkBALにお任せください
Works
事例紹介

Relation 関連記事

- Web制作
NEW2026/1/31WordPress制作会社おすすめ25選!費用相場と選び方を徹底解説
- Web制作
2025/11/30【2025年版】採用サイト制作会社おすすめ15選|失敗しない選び方と成果を出すパートナー探し完全ガイド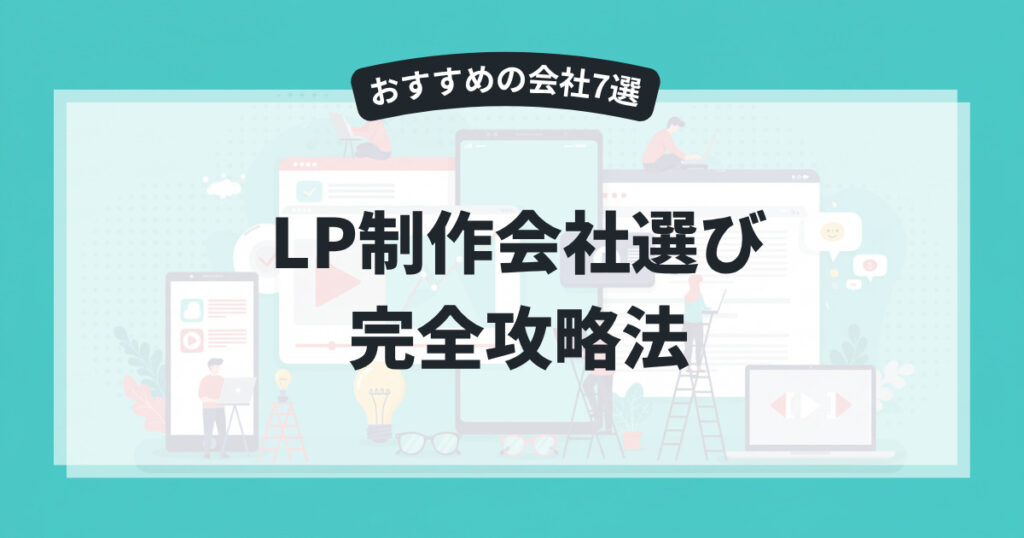
- Web制作
2025/9/12LP制作会社選びの完全攻略法|事業パートナーを見極める実践的7ステップ
- Web制作
2024/7/8IT・ソフトウェア業界におすすめの制作会社5選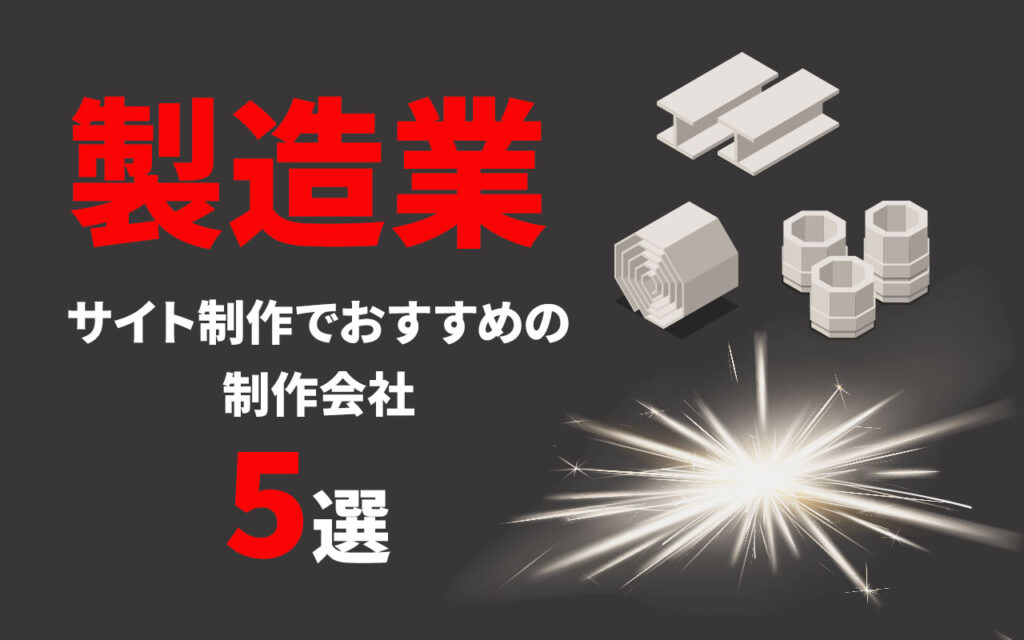
- Web制作
2025/9/7製造業のホームページ制作で成果を出す方法|おすすめのサイト制作会社も紹介
- Web制作
2024/6/30金融サイト制作でおすすめ制作会社5選|依頼先の4つの選び方のポイント
What's New 新着情報

- Web制作
NEW2026/1/31パーソナルジムのホームページ制作で集客する方法とおすすめ制作会社8選
- Web制作
NEW2026/1/31WordPress制作会社おすすめ25選!費用相場と選び方を徹底解説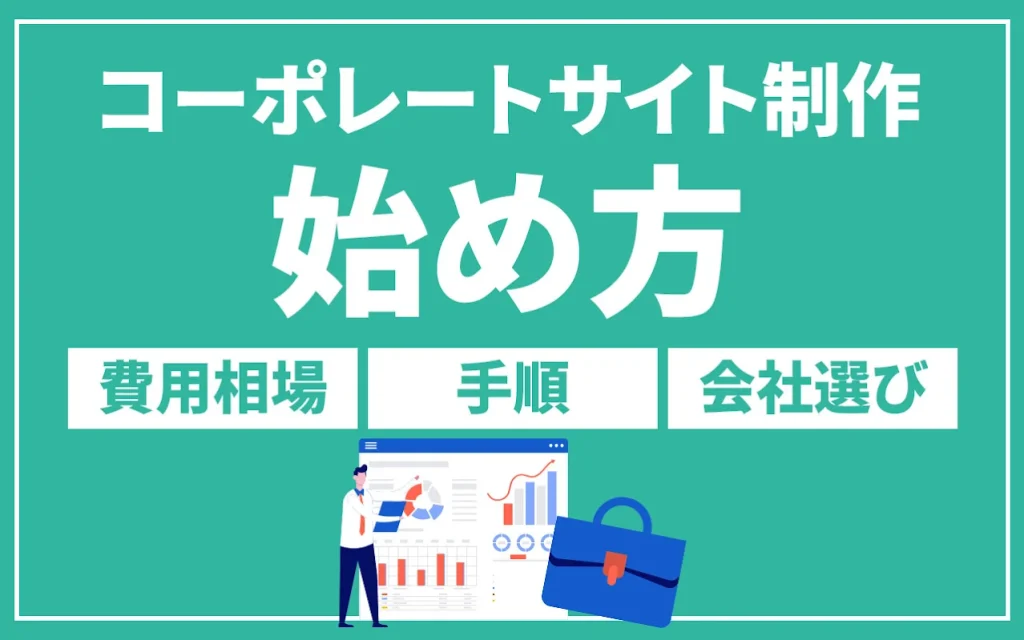
- Web制作
2026/1/31コーポレートサイト制作の始め方|費用相場・手順・会社選びを解説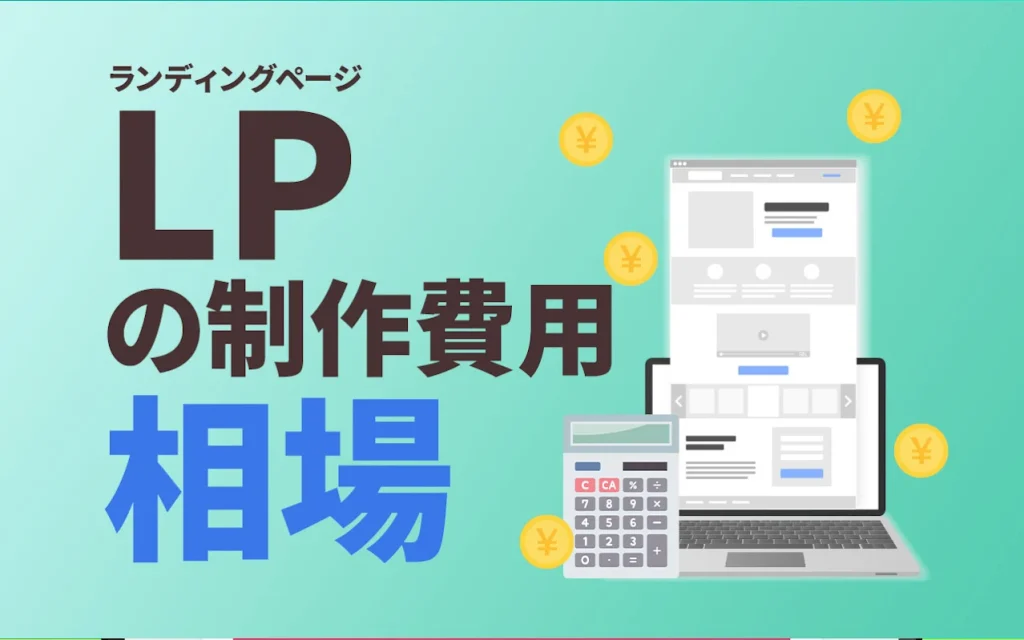
- Web制作
2026/1/31ランディングページの制作費用の相場は?内訳や料金事例を徹底解説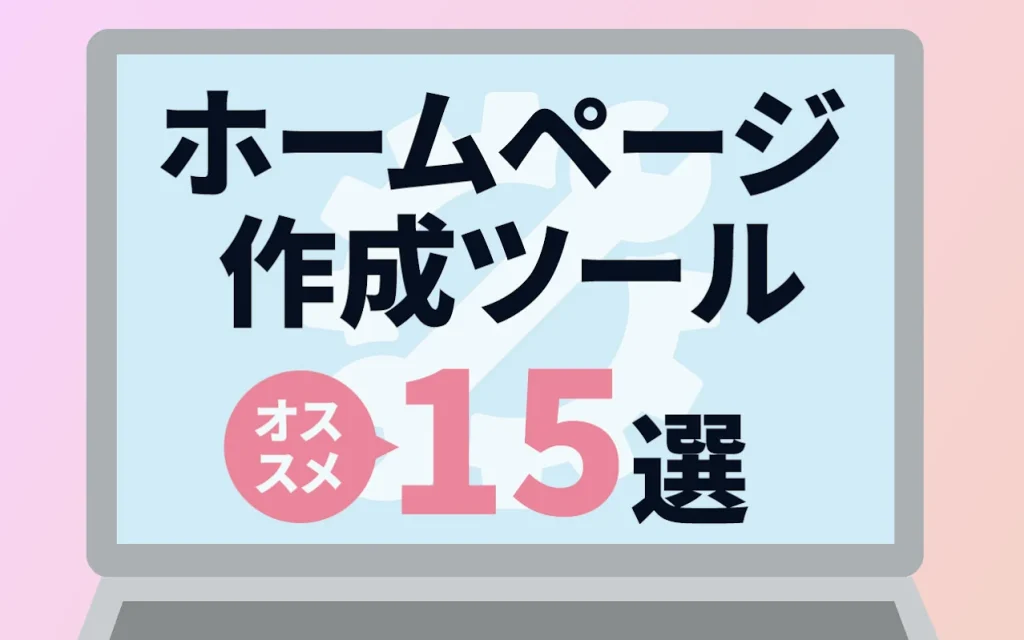
- Web制作
2026/1/31ホームページ作成ツールおすすめ15選【2026年最新版】無料・有料のツールを用途別に徹底比較!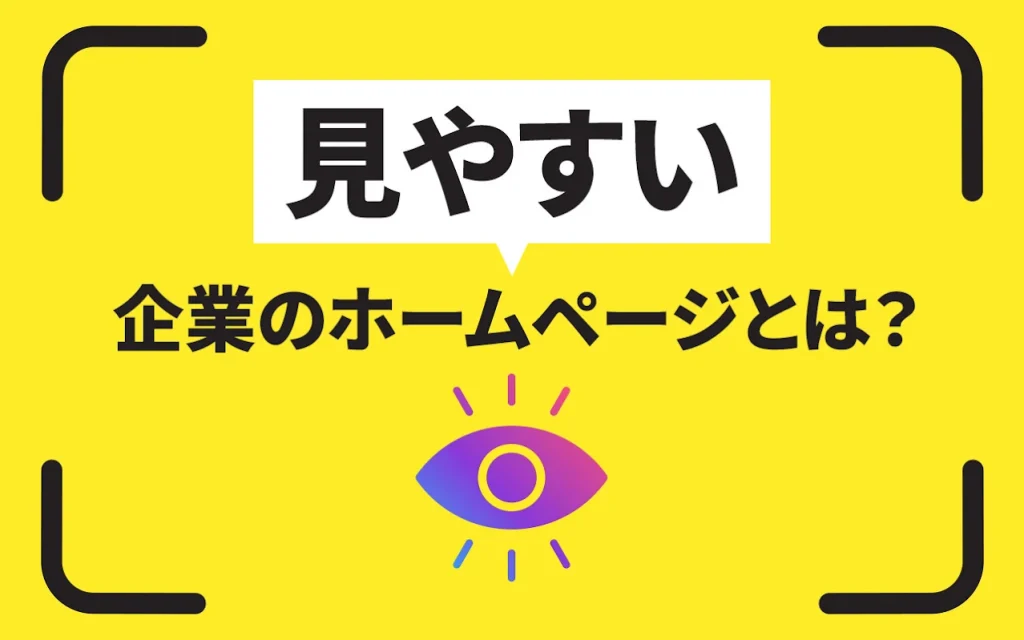
- Web制作
2026/1/31見やすい企業のホームページとは?参考例やポイントを解説!
Recommend オススメ記事
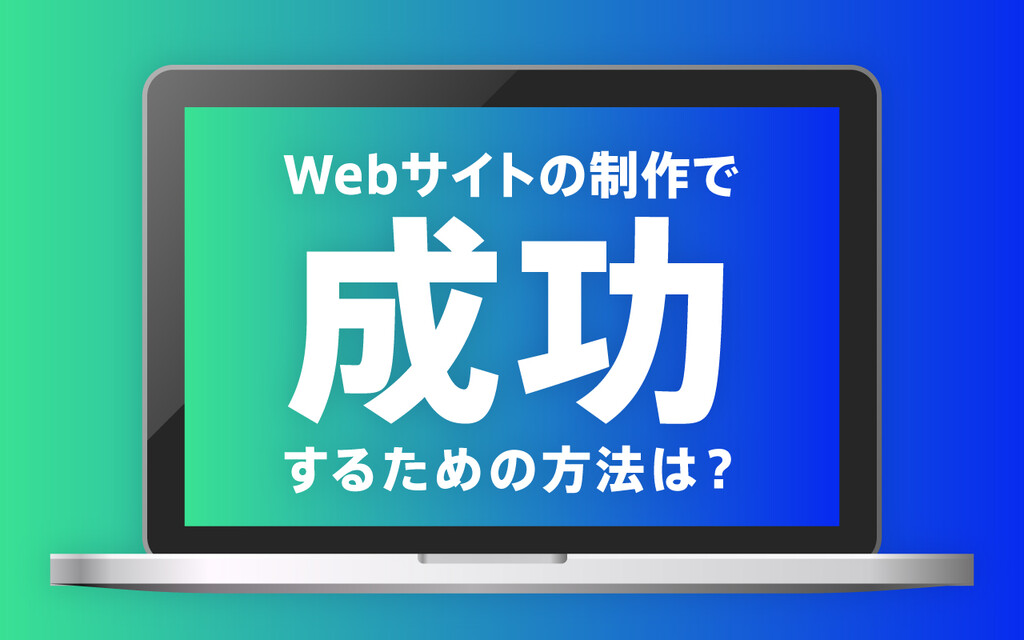
- Web制作
2025/9/19BtoBサイトでおすすめの制作会社15選|BtoBビジネスで成功するには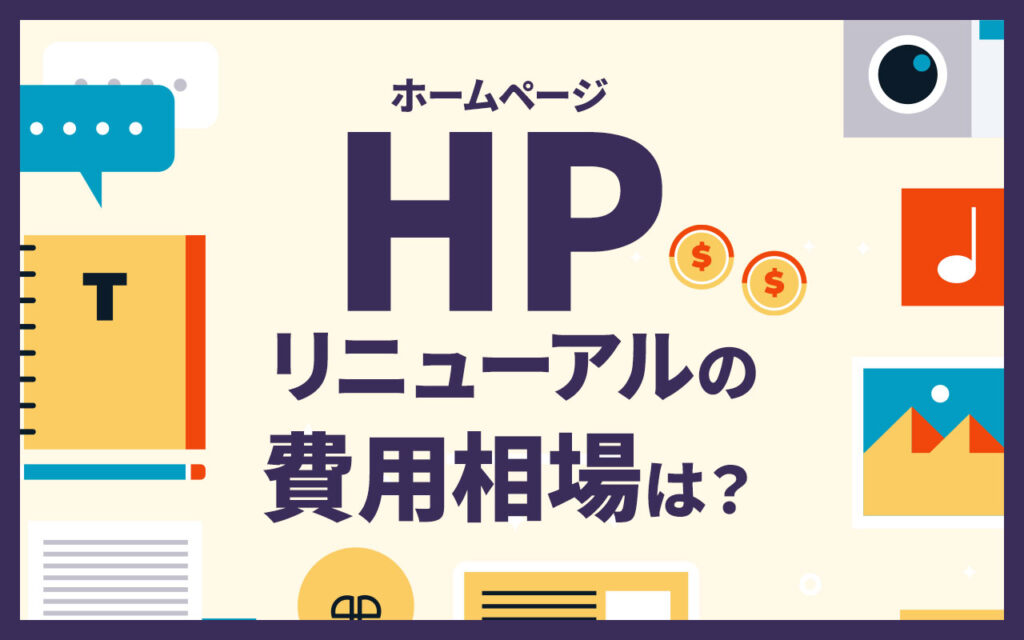
- Web制作
2025/10/2ホームページリニューアルの費用相場は?内訳と安く抑えるポイントを解説
- Web制作
2024/4/28採用サイトの集客方法5選!採用に必要なコンテンツは?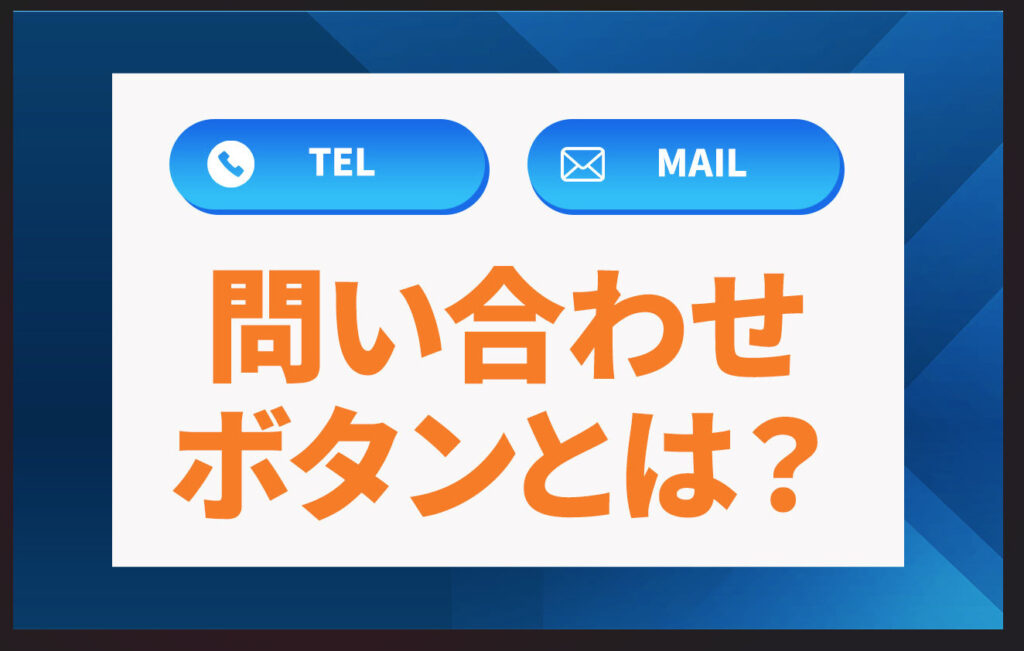
- UX/UIデザイン
2025/11/30問い合わせボタンとは?効果的なデザインと作り方・参考事例10選を徹底解説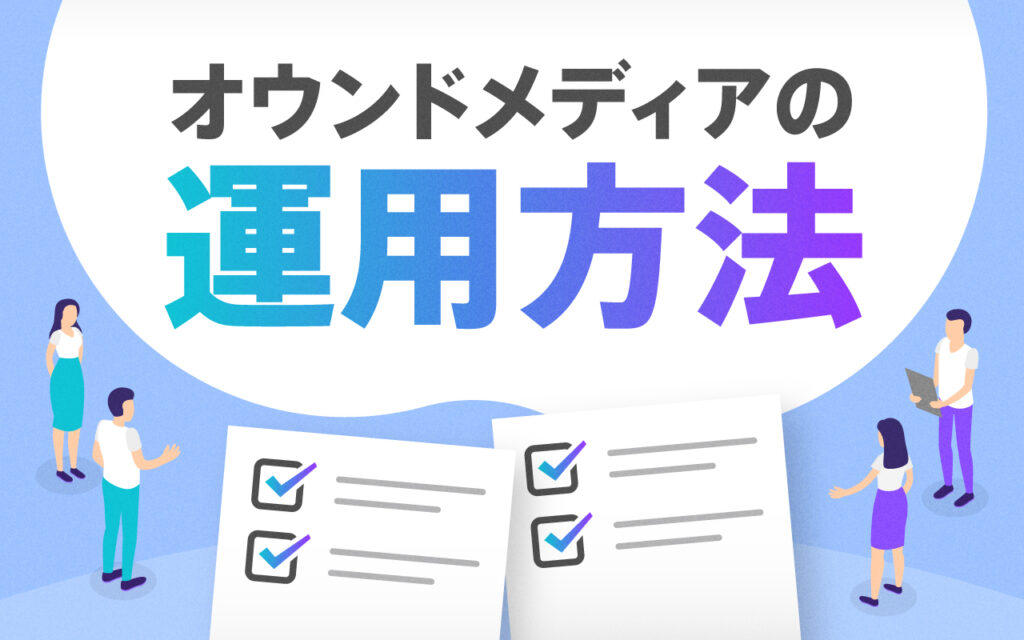
- Web制作
2024/9/19オウンドメディアの運用方法|成果の出るポイントを押さえて運用しよう
- Web制作
2026/1/5ブランドサイト事例15選!デザイン参考例と制作の流れを徹底解説
- Web制作
2025/9/30コーポレートサイトのSEO対策は必要?対策方法や注意点
- Web制作
2024/5/5採用サイトの改善方法とは?課題の見つけ方やリニューアルのポイントについても解説
- コンテンツマーケティング
2024/4/6コンテンツマーケティングの効果的な進め方とは?3つの成功事例も紹介