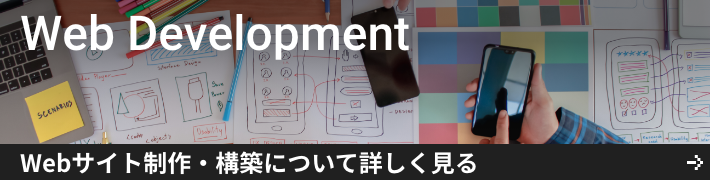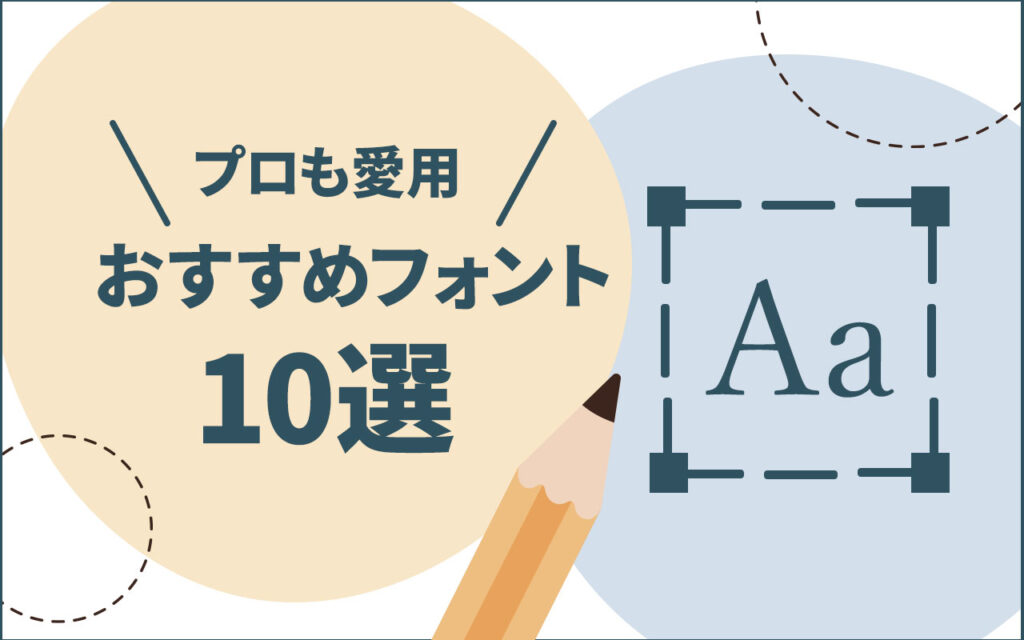Googleの嫌う「重複コンテンツ」とは?調べ方や対策方法、おすすめのチェックツールを紹介
Web上には企業が作成したページをはじめ、無数のページが存在しています。一方で近年においては「重複コンテンツ」が問題となっており、検索エンジンを運用するGoogleなども対策を講じている現状です。重複コンテンツは自社のWebサイトにさまざまな影響を及ぼすため、きちんと理解しておく必要があります。
重複コンテンツは、悪質とみなされると権利の侵害となる場合があり、賠償責任が発生する可能性もあるため、企業の担当者様などは理解を深めておきましょう。
- 重複コンテンツについて理解を深めたい人
- Googleのペナルティを避けたい人
- Webサイトの評価を上げたい人
googleのペナルティともなる重複コンテンツとは?

重複コンテンツの考え方は、人によってさまざまです。しかし盗用やコピーなどのように、悪質な場合にはトラブルに発展することもあります。実際にgoogleでは、重複コンテンツに対してペナルティを設けています。自社ページが罰則を受ける対象とならないように、まずは重複コンテンツの定義、ペナルティとなる理由について知っておきましょう。
- サイト内の他のコンテンツと似ているコンテンツ
- 他のサイトのコンテンツと似ているコンテンツ
サイトの内の他のコンテンツと似ているコンテンツ
重複コンテンツとは、テキストやタイトルなどの内容が同じ、もしくは非常に似ているコンテンツのことです。定義は人によって異なる場合がありますが、「サイト内の他のコンテンツと完全に同じ、非常によく似たコンテンツのブロックを指す」と定義されています。現在、同ジャンルの記事を多数制作していくと、類似するコンテンツが増えやすくなるため、注意が必要です。
他のサイトのコンテンツと似ているコンテンツ
重複コンテンツは、自社のサイト内だけで類似しているものだけではなく、他のサイトのコンテンツと似ている場合も該当します。
例えば「歯磨き」というキーワードで記事を作成したとすれば、「口内をキレイに洗浄すること」などの内容になるでしょう。
他の方が同じキーワードで記事を作成する場合にも、似たような内容になりがちです。
盗用や真似をしたことがうかがえるようなものは、重複コンテンツとみなされかねません。重複コンテンツだと扱われるケースについては、以下のようなものが挙げられます。
- URLは異なるが内容の一致する箇所が多い
- 文章は異なるが記述が酷似している
- 使用しているキーワードは異なるが検索意図が酷似している
上記に該当するときは、重複コンテンツだと判断される可能性があります。重複コンテンツだと判断されないようにするためには、サイト内容が他と異なる印象を与えられるような工夫が必要です。
重複コンテンツがペナルティになる理由
重複コンテンツだと判断されると、ペナルティの対象となる場合があります。ペナルティが課せられるのには、いくつかの理由があります。
作成者の権利を保護する
重複コンテンツをペナルティとする理由は、作成者の権利を保護するためです。盗用されたコンテンツやコピーされたサイトを許してしまうと、考える手間も必要なく誰でも簡単に同じものが作れてしまいます。
それでは、オリジナルを作成した方の利益を侵害する可能性があります。これはWebページに限った話ではありません。制作物には作成者の権利を保護するために、著作権など作成者を保護する法律が定められています。
ユーザーに不利益を及ぼす
ユーザーに不利益を及ぼすことも、重複コンテンツがペナルティになる理由です。Web上に盗作やコピーコンテンツがあふれていては、ユーザーに有益な内容が提供できている状況とはいえません。ユーザーに不利益を与えないためには、コピーなどの悪質なコンテンツの排除が必要です。悪質なコンテンツを排除するために、ペナルティが設けられています。
スパム・盗用などのリスクがあるため
重複コンテンツの中には、意図的に他サイトの内容をコピーし、検索結果で上位を狙おうとするスパム的な行為も含まれます。
こうした手法は、ユーザーに価値を提供しないばかりか、検索結果の品質を著しく損なうため、Googleでは厳しく取り締まっています。
特に、大量のコピーコンテンツを生成する自動化ツールや、複数サイトに同一記事をばらまく行為などは、「検索品質評価ガイドライン」にも違反する可能性が高く、最悪の場合はインデックス削除や検索圏外に飛ばされるケースもあります。
健全なサイト運営をおこなうためには、「独自性」「一次情報」「読者への価値提供」を軸にコンテンツを構成することが不可欠です。
重複コンテンツを避けるわけ
重複コンテンツは、Webサイトにさまざまな悪影響を及ぼします。重複コンテンツを避けた方が良いとされるのは、Webサイト運用にも影響が出るためです。
例えばGoogleのアルゴリズムでは、Webサイトを評価する際、コンテンツの質が重視とされています。実際に盗用やコピーが発覚し、悪質な内容と判断されると、罰則の対象となる場合があります。コンテンツが類似していると、すぐにコピーとみなされるわけではありませんが、似ているとの印象を与えないような対策が必要です。
必要な情報部分は類似してしまいますが「言い回しを変える」、「追加情報を記載する」など、独自性が出るような工夫を凝らしましょう。オリジナリティあふれるコンテンツを作成すれば、内容が似ていても重複コンテンツと判断されるリスクを減らせます。
重複するとどうなる?

重複コンテンツと扱われてしまうと、自社のWebサイトにさまざまな悪影響を及ぼします。特に悪質と判断された場合には、Webページが削除の対象となる可能性もあるため注意が必要です。なお重複と判断されたときには、主に以下のような影響があります。
- Googleからの評価が分散されてしまう
- Googleからペナルティを受けてしまう
- 上位表示しにくくなる
- ユーザーに届けたい内容が届かなくなる
Googleからの評価が分散されてしまう
重複コンテンツだと判断されると、Googleにおける被リンクの評価が分散してしまう可能性があります。評価が分散してしまうと適切な評価が得られず、検索順位などに影響を及ぼしかねません。
Googleでは内容が似たURLが複数存在している場合、ページにある被リンクの効果が分散してしまうことがあります。被リンクはページの評価に影響を与えるものであるため、評価が下がるとページ自体の評価が下がってしまいます。分かりやすく言い換えると、「本来100点の評価を得るはずが、分散したことにより50点の評価になった」という状態です。
このような事態が発生するとGoogleが対処してくれるときもありますが、必ずしも対応してもらえるとは限りません。常に適切な評価を受けるには、重複コンテンツとみなされないような対策をおこなうことが大切です。
Googleからペナルティを受けてしまう
重複したコンテンツだと判断されれば、Googleが対処するペナルティの対象となる場合があります。Googleが公表している「品質に関するガイドライン」によると、違反が発見されたWebサイトには、いくつかの罰則が課せられるようです。具体的にはインデックス削除により検索画面表示されなくなる、検索順位の低下などが挙げられます。検索が表示されなくなったり、検索順位が低下したりすると、サイトの集客や売上に甚大な影響を与えかねません。そういった事態を回避するためにも、コンテンツが重複しないように気をつけておきましょう。
なおGoogleのペナルティには、「自動ペナルティ」と「手動ペナルティ」の2種類が存在します。自動ペナルティは検索エンジンにより、自動的に課せられる罰則のことです。検索エンジンが違反を発見次第、自動的に処理されます。一方で手動ペナルティとは、Googleの担当者の判断により手動で課せられる罰則です。課せられる際にはGoogle Search Consoleへ、該当サイトについて警告メッセージが送信されます。
上位表示しにくくなる
重複コンテンツを作成してしまうと、検索順位で上位表示されにくくなります。Google側の検索エンジンは独自のアルゴリズムを採用しており、ユーザーに有益なページをバランスよく表示させる仕組みです。
近年ではユーザーのニーズも多様化しています。どれも似た内容のコンテンツがあふれていると、多様化したユーザーのニーズを満たすことができません。一部の方しか満足できないようなサービスでは、検索エンジンの利用価値も低くなってしまうでしょう。
そのような事態を防ぐためにGoogleでは、同じ内容と判断されたコンテンツが上位表示されにくい仕組みとなっています。重複コンテンツは索引される可能性が低いため、検索エンジンに重複とみなされないコンテンツの作成が必要です。
ユーザーに届けたい内容が届かなくなる
重複コンテンツだと判断されると、ユーザーに情報を届けられる機会が減ってしまいます。重複コンテンツだと判断されたページは、検索上位には表示されにくい状態です。検索結果画面にも表示されにくいため、ユーザーが目にする機会が多くはないでしょう。それではページの存在を認知してもらえず、どれだけ良質なコンテンツを作成しても、ユーザーに届けることはできません。
検索エンジンは、ユーザーの求める情報を提供することが主な目的です。Web上に似たページが存在するときは、アルゴリズムが有益と判断したページから表示されます。ユーザーに情報を留めるためには重複とみなされず、検索エンジンに有益と判断されるような、コンテンツ作成を目指すことが大切です。
重複コンテンツのチェック方法

重複コンテンツだと判断されると、Webページにさまざまな悪影響を与える可能性があるため、重複しないように注意しなければなりません。コンテンツの重複を避けるためには、公開前および定期的に確認することが大切です。なお重複コンテンツのチェック方法には、以下のようなものがあります。
- 重複チェッカーツールを利用する
- 検索エンジンでチェックする
- siteで検索する
重複チェッカーツールを利用する
重複コンテンツのチェックをおこなう際、よく利用されるものがチェッカーツールを用いたチェックです。ツールを活用すれば重複コンテンツの確認だけでなく、改善点などの把握・分析がおこないやすくなります。
チェッカーツールはさまざまな種類があるため、比較しながら自社の方向性にマッチするツールを活用しましょう。
検索エンジンでチェックする
続いて、検索エンジンで重複コンテンツを確認する方法です。Googleの場合では、検索結果URLの末尾に「&filter=0」を入力し、再検索することで重複コンテンツをチェックできます。
また、この手法は、自社サイトの状況を確認する際にも有効です。内容が似ているコンテンツとみなされた場合、検索結果画面に表示されないことがあります。このようなときにも、対象キーワードにおける検索結果URLの末尾に「&filter=0」を入力し、再検索をおこないます。すると検索結果画面に表示されなかったページを、意図的に表示させることが可能です。
なお手間は掛かりますが検索エンジンでは、他サイトと文章の重複チェックもできます。30文字以内の文章であれば、検索をおこなうことで他サイトと同じ文章がないか確認が可能です。
siteで検索する
Googleの検索コマンド「site」を利用したチェック方法です。この機能を活用することで、検索結果にインデックスされているページ数を調べることができます。
例えば10ページほどしか公開していないにもかかわらず、100ページのインデックスが確認されたとします。このようなときは、コンテンツの重複が発生している可能性が高い状況です。反対に100ページを公開しているのに、10ページしかインデックスされていなければ、クロールやインデックスに問題が生じている可能性があります。
なお「site」コマンドは、他のコマンドと組み合わせて使用できることが特徴です。トップページの重複を調査するときなどは、「intitle」と組み合わせて使われることがよくあります。
重複コンテンツの対策方法
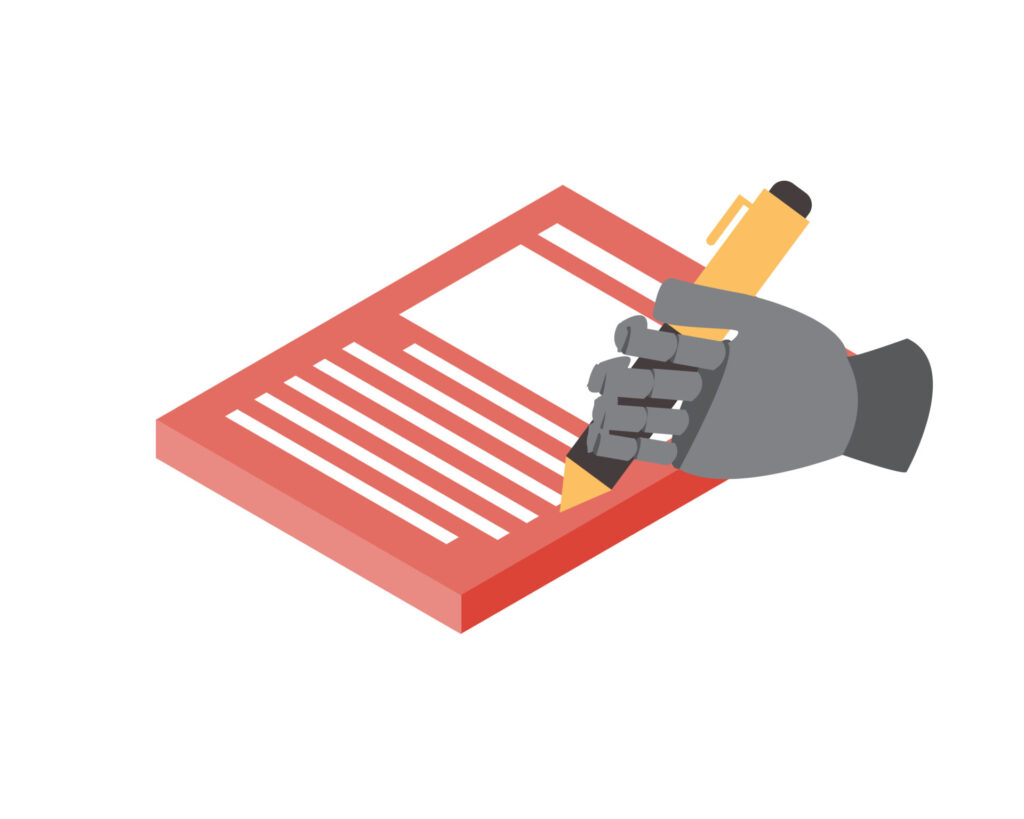
重複コンテンツには、「自社重複」と「他社重複」という2つのパターンがあります。それぞれで効果的な対策が異なるため、パターンごとに適切な対策を講じることが重要です。適切な対策を講じることで、重複コンテンツになるリスクを抑えられます。コンテンツが重複することを防ぐためにも、パターンごとに適した対策を把握しておきましょう。
- 自社重複の場合
- 他社重複の場合
自社重複の場合
重複コンテンツは「www」の表記や自動作成ページの設定など、サイトの仕様によって生じるケースがあります。そのため自社でも気付かないうちに、重複コンテンツに該当しているケースも少なくありません。自社のコンテンツが重複した場合でも、検索エンジンの評価に影響を与えるため注意が必要です。
自社コンテンツの重複を防ぐ対策としては、以下のものが挙げられます。
コンテンツ制作の際にしっかりチェックしておく
自社コンテンツの重複を避けるには、制作時におけるチェックの強化が有効です。例えばECサイトを運用する場合、価格や商品のみを差し替えたページなどは、重複コンテンツだと判断されることがあります。重複と判断されないためにはページの構成や内容、デザインについてチェックすることが重要です。
似た内容になるキーワードを避ける
重複と判断されるのを避けるには、キーワードの選定も大切です。同サイト内にある複数のページで、同じキーワードを何度も使用していると、重複コンテンツとして扱われる可能性があります。そのため各ページのキーワードは、重複しないように気を付けながら選定をおこないましょう。
定期的にチェックをする
サイト運用をおこなっていくにつれ、ページ数が増えていくことがあります。ページ数が多くなると似たページの存在に気付かなかったり、問題点を見落としたりするケースも少なくありません。そういった事態に陥らないためにも、Webサイトは定期的にチェックすることが大切です。
他社重複の場合
自社では他社サイトとの重複に十分な対策を講じていても、他社が自社サイトと類似したコンテンツの作成をしている場合があります。放置しておくと自社サイトも重複コンテンツと判断される可能性があるため、然るべき対処をおこなうことが必要です。主な対処としては、以下のものが挙げられます。
作成者に削除依頼をする
自社に類似したコンテンツを発見した場合、作成者に削除依頼をしてみましょう。ただし削除依頼をおこなうときには、自社コンテンツがオリジナルであることを証明する必要があります。
Googleに著作権侵害の報告をする
削除依頼をおこなっても、必ず先方が応じてくれるとは限りません。また自社の風評などを考慮すると、先方に直接申し出をおこなうことをためらう場合もあるでしょう。このようなときには、Googleに著作権侵害の報告をおこなうことも有効です。Googleが著作権侵害にあたると判断すれば、該当のページは削除してもらえます。
canonical設置をする
他社に対応してもらうのが難しい場合は、自社での対策も必要です。重複コンテンツが存在するときは、「canonical」タグを設置しましょう。canonicalタグとは、URLを正規化するためのHTMLタグです。タグを設置することで、検索エンジンから適切な評価を受けられることに期待できます。
Googleからのペナルティ対策に!重複コンテンツチェックツール3選
Googleのペナルティ対策のためにも、重複コンテンツチェックツールの活用は必須です。ここからは、一般的に使われている3つのツールをご紹介します。
Google Search Console
Google Search Console(サーチコンソール)は、Google公式の無料ツールで、自社サイトに対するGoogleの評価やエラー情報を確認できます。
直接「重複コンテンツ検出」機能はありませんが、レポートの中で、自動的に検出された重複ページを通知してくれます。
この情報をもとに、canonicalタグの見直しや、類似ページの統合・リライトを検討できます。Google側の視点で重複をどう扱っているかを把握できるのが魅力です。
sujiko.jp

sujiko.jpは、日本語テキストの重複率を簡単に調べられる無料ツールです。
URLをコピペするだけで、比較対象先のページとの一致率を数値で確認できるため、他サイトからの流用チェックや、自社内でのコンテンツの違いの確認に活用できます。
外注ライターから納品された記事の品質チェックや、社内で似たテーマを複数人が執筆している場合などに便利です。
CopyContentDetector
CopyContentDetectorは、特にWebコンテンツの盗用チェックに定評のある無料ツールです。文章を入力すると、インターネット上の既存ページと照らし合わせて類似コンテンツを検出し、スコア付きで重複度を表示してくれます。
最大で8,000文字程度(有料の場合)まで対応しており、文章ボリュームのある記事でも安心です。特に、外部からライティングを委託している企業や、SEO記事の納品チェックをおこなう編集者にとっては、納品物の独自性確認に非常に有効です。ログイン不要で使える手軽さも魅力で、日常的な運用に取り入れやすいツールです。
まとめ
重複コンテンツは、Webサイト・Webページにさまざまな悪影響を及ぼすものです。Webマーケティングで成果を出すためには、重複コンテンツと判断されることを避けなければなりません。重複コンテンツにならないように、以下のポイントに気を付けましょう。
- 他ページの盗用やコピーの疑いがあるものは、重複コンテンツと判断される可能性がある
- 重複コンテンツに該当するとペナルティをはじめ、自社サイトにさまざまな悪影響がある
- 自社重複、他社重複それぞれに適切な対策を講じることで、重複するリスクを減らせる
オリジナリティあふれる内容を考案し、クオリティの高いWebページの作成を目指しましょう。
Googleペナルティにならない重複のないコンテンツ制作
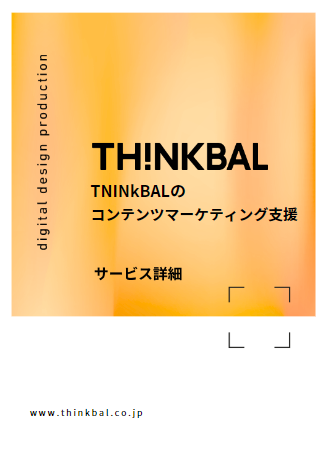
高品質なオリジナルコンテンツ作成をプロに依頼してみませんか?
- 重複コンテンツの見つけ方が分からない
- 検索順位が急激に落ちて、問い合わせが減った
- 重複コンテンツにならないように改善を依頼したい
コンテンツマーケティング支援なら
THINKBALにお任せください
Works
事例紹介

Relation 関連記事

- SEO
2025/5/14【保存版】SEOを用いたサイト改善の全手順|よくある失敗パターンと成功のコツ
- コンテンツマーケティング
2026/1/19【無料あり】記事作成におすすめの生成AIツール10選!活用メリット・デメリットも解説
- SEO
2025/2/26ドメインランク(ドメインパワー)とは?効果的に上げる方法とGoogleの評価を解説
- Web制作
2025/1/31ドメインの強さとSEOの関係性は?ドメインパワーの詳細を解説
- コンテンツマーケティング
2025/1/31リライトの注意点は?検索順位を下げないための対策
- SEO
2024/12/24SEOに有効な更新頻度って?量よりも質な最近のSEOの傾向についても紹介
What's New 新着情報

- コンテンツマーケティング
2026/1/19【無料あり】記事作成におすすめの生成AIツール10選!活用メリット・デメリットも解説
- Web制作
2026/1/5ヘッダーの作り方完全版!HTML・CSS・スマホアプリで作る手順を解説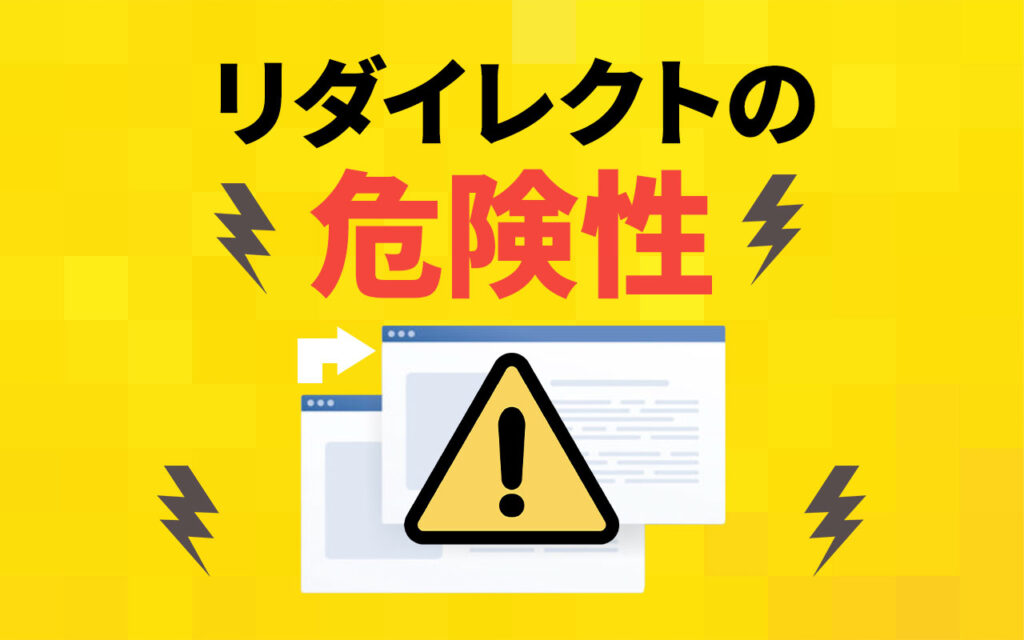
- Web制作
2026/1/5リダイレクトの危険性│ユーザーやSEOにおけるリスクや注意点について解説
- Web制作
2026/1/5グローバルメニューとは?優れたデザイン事例とクリックされる設置のコツ
- Web制作
2026/1/5初心者でも分かるStudioの使い方|プロが教える設定手順と事例
- Web制作
2026/1/5ホームページ公開までの流れを5ステップで解説!公開前後でやるべきチェックリストも紹介
Recommend オススメ記事
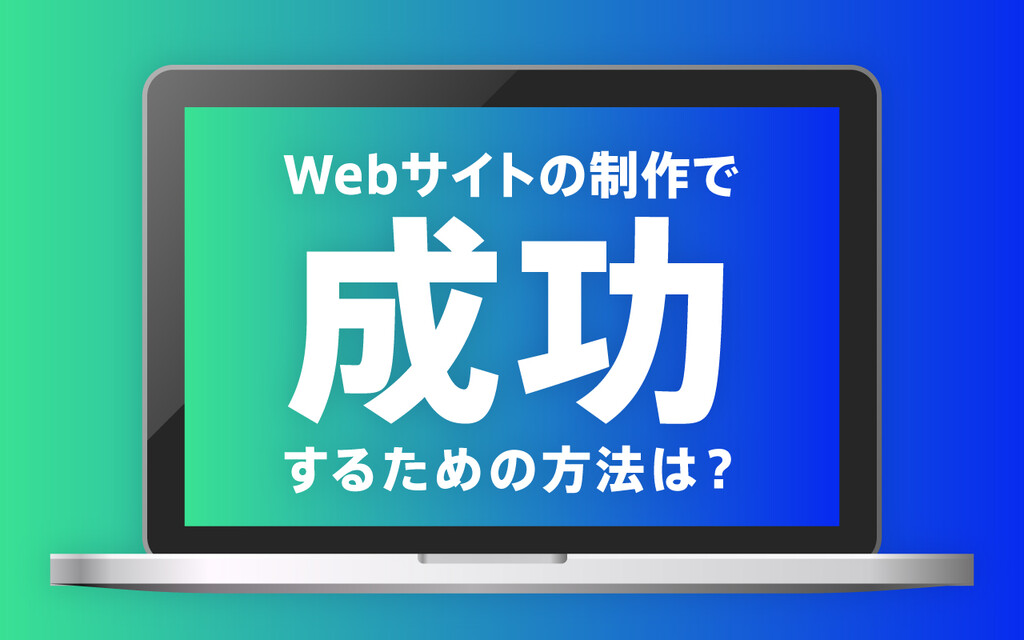
- Web制作
2025/9/19BtoBサイトでおすすめの制作会社15選|BtoBビジネスで成功するには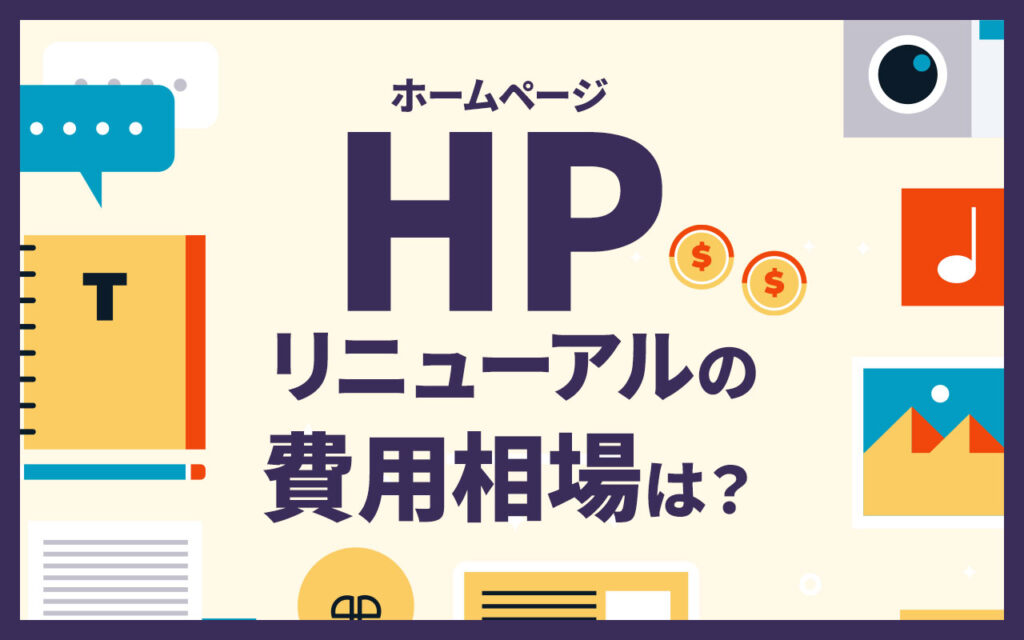
- Web制作
2025/10/2ホームページリニューアルの費用相場は?内訳と安く抑えるポイントを解説
- Web制作
2024/4/28採用サイトの集客方法5選!採用に必要なコンテンツは?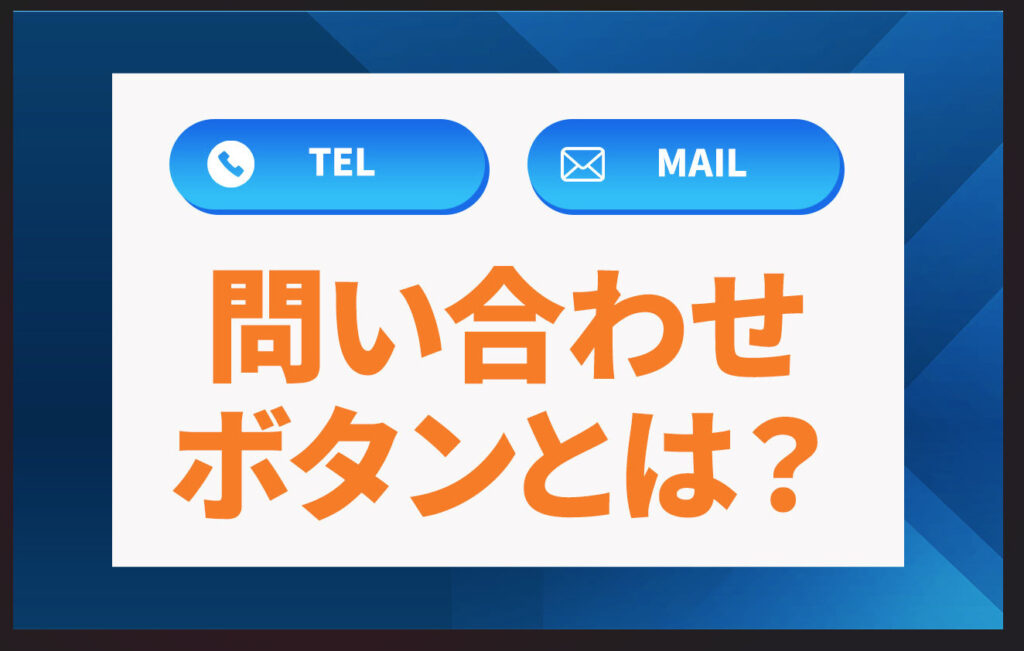
- UX/UIデザイン
2025/11/30問い合わせボタンとは?効果的なデザインと作り方・参考事例10選を徹底解説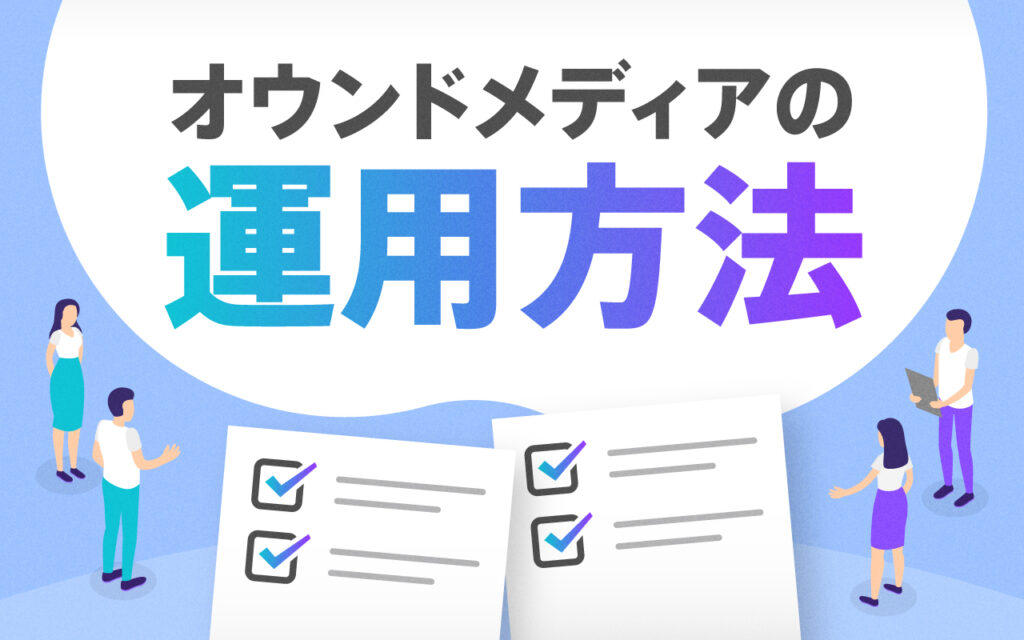
- Web制作
2024/9/19オウンドメディアの運用方法|成果の出るポイントを押さえて運用しよう
- Web制作
2026/1/5ブランドサイト事例15選!デザイン参考例と制作の流れを徹底解説
- Web制作
2025/9/30コーポレートサイトのSEO対策は必要?対策方法や注意点
- Web制作
2024/5/5採用サイトの改善方法とは?課題の見つけ方やリニューアルのポイントについても解説
- コンテンツマーケティング
2024/4/6コンテンツマーケティングの効果的な進め方とは?3つの成功事例も紹介