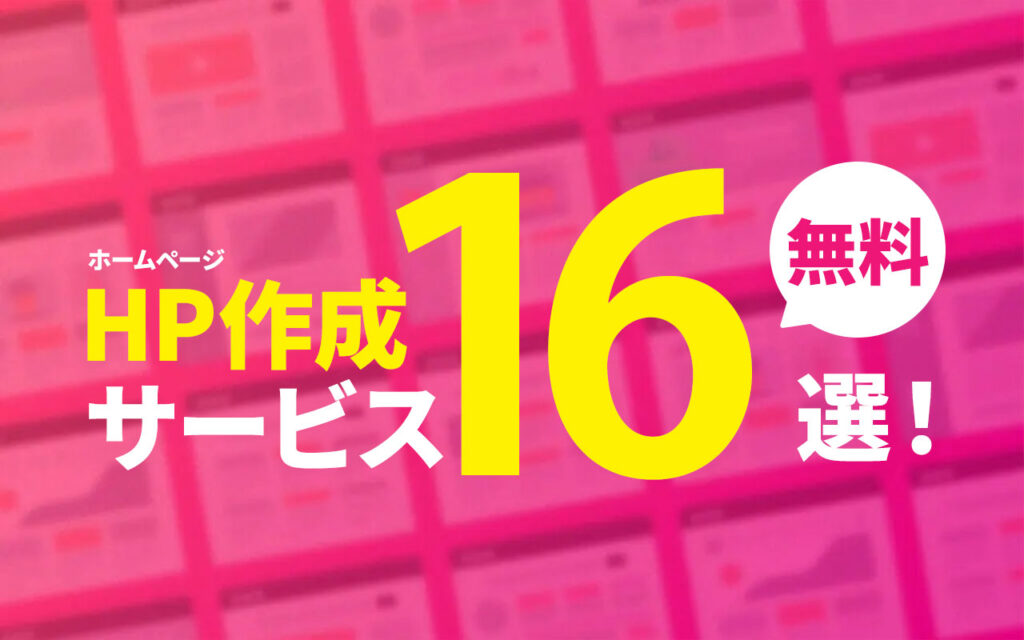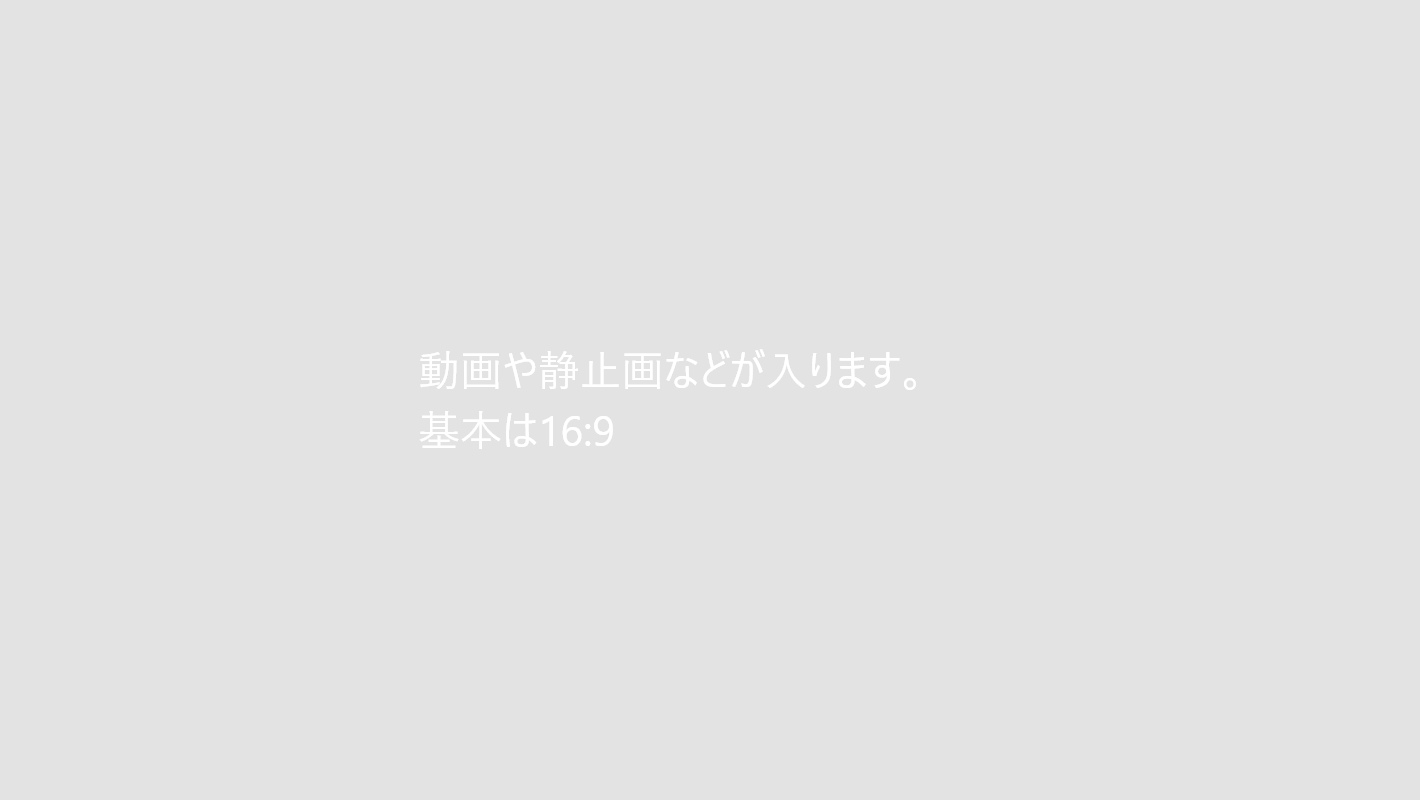
【2025年最新】ワイヤーフレーム作成の教科書|初心者でも失敗しない5ステップとツール選び
ワイヤーフレームを作ってと言われたけど、どこまで作れば良いの?」「せっかく作ったのに、後から『思っていたのと違う』と言われてしまった...」という経験はありませんか?
プロジェクト失敗の8割は認識のズレが原因です。
- ワイヤーフレームの作成方法で悩んでいる人
- 便利なワイヤーフレーム作成ツールを探している人
- ワイヤーフレームにおける作成のコツを知りたい人
この記事では、初心者でも確実に成功できる5ステップの作成手順から、効率を10倍にするAI・テンプレート活用術、よくある失敗事例の対処法まで、現場で本当に使える実践的なノウハウを完全網羅して解説します。
明日からすぐに実践できる具体的な方法で、あなたのワイヤーフレーム作成を成功に導きます。
- ワイヤーフレームとは?なぜ今重要なのか
- 【重要】ワイヤーフレームは「どこまで」作るべきか?
- 失敗しないワイヤーフレーム作成の5ステップ
- 【目的別】ワイヤーフレーム作成ツール選択ガイド
- ワイヤーフレーム作成の効率を10倍に!?テンプレート・AI活用術
- ワイヤーフレーム作成の工数はどう決まる?費用対効果を測るポイント
- 作成するワイヤーフレームの質を劇的に向上させる3つのコツ
- 実際の失敗事例から学ぶ!ワイヤーフレーム作成のよくあるNG例と対処法
- サイト制作に伴うワイヤーフレーム作成でお困りならTHINkBAL
- THINkBAL流「成果から逆算する」ワイヤーフレーム術
- THINkBALでワイヤーフレーム作成まで含めて担当した〇〇制作の事例
- まとめ:ワイヤーフレームで必ずプロジェクトを成功させる
ワイヤーフレームとは?なぜ今重要なのか
ワイヤーフレームとは、Webサイトやアプリケーションの骨組みを示す設計図のことです。色やデザインを排除し、コンテンツの配置や機能の関係性をシンプルな線と箱で表現します。
プロジェクト失敗の8割が「認識のズレ」に起因する中、ワイヤーフレームは関係者全員の共通理解を築く最重要ツールとなっています。
ワイヤーフレームの本質的な目的
ワイヤーフレームの最も重要な役割は、チーム全体が「同じ船に乗る」ための共通言語を提供することです。デザイナー、エンジニア、クライアントが同じ画面を見て議論できる状態を作り出します。
また、手戻りを防ぎ、開発時間とコストを最小化する効果があります。「思っていたものと違う」を事前に回避し、プロジェクトの成功率を大幅に向上させます。
デザインカンプ・モックアップとの違い
ワイヤーフレームは情報の構造と配置に特化した設計図です。一方、デザインカンプは色や装飾を含む完成形の見た目を示し、モックアップはクリック可能な動作も含みます。
ワイヤーフレームは「何をどこに配置するか」、デザインカンプは「どう見せるか」、モックアップは「どう動くか」を表現する違いがあります。この役割分担を理解することで、適切な制作フローを構築できます。
【重要】ワイヤーフレームは「どこまで」作るべきか?
ワイヤーフレームを「どこまで詳細に作れば良いか分からない」というのは最も多い質問です。
作りすぎると時間の無駄遣いになり、適当すぎると後工程で混乱が生じます。プロジェクト規模と関係者の理解度に応じて、最適な粒度を判断することが重要です。
完璧を求めるのではなく、議論のたたき台として機能するレベルを目指すのが現実的なアプローチです。
サイト規模で変わるワイヤーフレームの適切な作り込みレベル
ワイヤーフレームに求められる情報の詳しさは、制作するサイトの規模によって大きく異なります。小規模なサイトなら簡単な構成図で十分ですが、ページ数や関わる人が増える大規模なプロジェクトでは、認識のズレや手戻りを防ぐために、より詳細な「設計図」としての役割が求められるのです。
自社のプロジェクトがどの規模に該当し、どのレベルまで作り込むべきか、以下の表で確認してみましょう。
| サイト規模 | ページ数 | 作成すべき要素 |
| 小規模サイト | 5ページ以下 | ヘッダー、メインコンテンツ、フッターの3要素のみ |
| 中規模サイト | 6~20ページ | トップページ、一覧ページ、詳細ページなど、ページ種別ごとのテンプレート化 |
| 大規模サイト | 21ページ以上 | 各要素の機能や制約を明記した、詳細な注釈付きの設計書レベル |
「注釈」で認識のズレを完全に防ぐ書き方
注釈は後工程のデザイナーやエンジニアが迷わないよう、具体的で実用的な情報を記載します。
例えば「画像エリア(推奨サイズ:600×400px、縦横比維持で自動トリミング)」「ボタン(hover時は透明度70%、スマホでは指タップ領域44px以上確保)」といった形で記述します。
曖昧な表現を避け、実装者が判断に迷わない明確な指示を心がけることが重要です。
失敗しないワイヤーフレーム作成の5ステップ
初心者でも確実に成功できる実証済みの手順を段階別に解説します。各ステップで明確な目標を設定し、次の工程に進むべき判断基準を提示します。
- いきなり作らない!事前準備で9割が決まる
- 手書きラフスケッチで自由なアイデア出し
- 主要ページのレイアウトパターン決定
- ツールで清書・共有可能な形に
- 関係者との合意形成・フィードバック収集
急がば回れの精神で、事前準備から丁寧に進めることで、後工程での手戻りを劇的に削減できます。経験豊富なプロフェッショナルも実践する王道のプロセスです。
STEP1:いきなり作らない!事前準備で9割が決まる
成功するワイヤーフレームの9割は事前準備で決まります。
まず、ターゲットユーザーの課題とニーズを整理し、サイトマップで全体の情報構造を可視化します。
次に、各ページに掲載する情報の優先順位付けとグループ化をおこないます。この段階で関係者と認識合わせをおこなうことで、制作段階での混乱を防げます。
準備時間を惜しまないことが最大の時短につながります。
STEP2:手書きラフスケッチで自由なアイデア出し
まず紙とペンを使った手書きのラフスケッチから始めます。ツールの操作に気を取られず、純粋にアイデアに集中できるためです。
5分程度で素早く複数パターンを描き、量より速度を重視します。完璧を求めず、思いついたアイデアをどんどん形にしていきます。
この段階では他人に見せることを考えず、自分の思考整理に専念することが重要です。
STEP3:主要ページのレイアウトパターン決定
ユーザーの視線動線を意識したレイアウト設計をおこないます。
Z型動線(左上→右上→左下→右下)を活用し、重要な情報を動線上に配置します。
F型動線(左から右へ、上から下へ)を考慮し、テキストコンテンツの読みやすさを確保します。トップページ・一覧ページ・詳細ページなど、主要なページパターンを決定し、一貫性のある情報設計を構築します。
STEP4:ツールで清書・共有可能な形に
手書きラフを基に、デジタルツールで清書します。デザイン的な装飾は一切加えず、グレーの箱と線のみでシンプルに表現します。
文字情報は実際のコンテンツまたは具体的なダミーテキストを使用し、「ここに文章が入ります」といった抽象的な表現は避けましょう。
共有時に誤解が生じないよう、必要に応じて注釈やメモを追加します。
STEP5:関係者との合意形成・フィードバック収集
完成したワイヤーフレームを使って関係者との合意形成をおこないます。
「このワイヤーフレームを見て、どのような完成形をイメージしますか?」という質問から始め、認識のズレがないか確認します。
意見の対立が生じた場合は、ユーザーの利益を最優先に判断基準を設けます。建設的なフィードバックを収集し、必要に応じて修正を加えながら全員が納得する形に調整していきます。
【目的別】ワイヤーフレーム作成ツール選択ガイド
膨大なツールから「あなたに最適な1つ」を見つける完全ガイドです。機能の豊富さではなく、チーム構成・予算・プロジェクトの特性に応じた最適解を提案します。
- 初心者・予算重視なら「身近なツール活用法」
- チーム作業重視なら「コラボレーション特化ツール」
- プロレベルなら「高機能デザインツール」
「高機能=良いツール」ではなく、目的に対する適合性を重視した選択が重要です。無料ツールでも十分なクオリティを実現できる場合が多く、コストパフォーマンスを慎重に検討すべきです。
初心者・予算重視なら「身近なツール活用法」
PowerPointやGoogleスライドは、多くの人が既に使い慣れている最も身近なワイヤーフレーム作成ツールです。図形挿入機能を使って箱と線を配置し、テキストボックスで説明を追加できます。
Excel・Googleシートも表組み機能を活用すれば、整理されたワイヤーフレームを作成可能です。手書きをスマートフォンで撮影し、画像として共有する手法も、シンプルで効果的なアプローチです。
チーム作業重視なら「コラボレーション特化ツール」
コラボレーション特化ツールの代表格のFigmaは、無料で高機能、かつリアルタイム共同編集が可能な最強のコラボレーションツールです。複数メンバーが同時に編集でき、コメント機能でフィードバックのやり取りもスムーズにおこなえます。
MiroやMuralは、ホワイトボード感覚の直感的な操作が特徴で、ブレインストーミングからワイヤーフレーム作成まで一貫しておこなえます。
チーム導入時は操作方法の共有と、ファイル管理ルールの策定が成功の鍵となります。
プロレベルなら「高機能デザインツール」
Adobe XDやSketchは、ワイヤーフレームからプロトタイプまで一貫した制作が可能な本格的なデザインツールです。
コンポーネント機能により、共通パーツの一括更新ができ、大規模プロジェクトでの効率性が向上します。
既存のワークフローとの統合も容易で、デザインシステムの構築にも対応しています。導入コストは高いものの、ROI(投資対効果)を考慮すると、本格的な制作環境には必須のツールです。
ワイヤーフレーム作成の効率を10倍に!?テンプレート・AI活用術
「ゼロから作る苦労」から解放される最新の効率化手法を紹介します。
高品質なテンプレートの活用により、考慮漏れを防ぎながら大幅な時短を実現できます。AI技術を使った自動生成も実用レベルに達しており、初期アイデアの創出に威力を発揮します。
ただし、AIの出力をそのまま使用するのではなく、プロジェクトの要件に合わせた調整が必要です。
厳選無料ツール&テンプレート活用でワイヤーフレーム作成を高速化
高品質なワイヤーフレーム作成は、無料ツールとテンプレートの活用が成功の鍵です。
テンプレートには優れたサービスで採用済みのUIパターンが組み込まれており、ユーザーにとって使いやすい画面設計の土台を素早く作れます。考慮漏れを防ぎ、デザインの一貫性を保つ上でも有効です。
特に以下の5つのツールは、日本語対応の高品質なテンプレートが豊富で即戦力になります。
- Figma Community: 豊富なUIキットが揃うデザイン共有基盤
- Canva: 直感的な操作が可能な万能デザインツール
- Miro: 共同編集に強いオンラインホワイトボード
- Cacoo: 国産ならではの使いやすい作図ツール
- draw.io: 完全無料で高機能なブラウザ完結型ツール
これらのツールをプロジェクトに応じて使い分けることが重要です。
例えば、チームでの共同作業ならMiro、デザインの作り込みまで見据えるならFigma、非デザイナーでも手軽に作成したいならCanvaといったように、目的やメンバーのスキルに合わせて最適なツールを選択することが、プロジェクト成功の近道です。
ChatGPTをはじめとした生成AIでワイヤーフレーム作成を自動化
ChatGPTを活用したワイヤーフレーム自動生成の実用的なプロンプト設計を解説します。
「○○業界の△△サイトのトップページワイヤーフレームを作成してください。ターゲットは□□で、主要コンテンツは××です」といった具体的な指示により、実用的な構成案を生成できます。
AI出力結果を実用レベルに仕上げるには、人間による戦略的な判断と調整が不可欠です。AIは「思考のショートカット」として活用し、最終的な品質管理は人間がおこなうという役割分担が重要です。
ワイヤーフレーム作成の工数はどう決まる?費用対効果を測るポイント
ワイヤーフレーム作成の工数(時間・費用)は、サイトの「機能の複雑さ」と「要求される設計の緻密さ」で決まります。
例えば、表示するだけのページと、ユーザーが情報を入力するフォームのあるページとでは、後者の方が設計工数は格段に増えます。
この工数を「コスト」と捉えるのではなく、「将来の損失を防ぐための投資」として考えることが重要です。ワイヤーフレーム作成に20時間かけたとしても、それによって開発段階での100時間分の手戻りを防げるかもしれません。
事前に詳細な設計図を固めることこそが、プロジェクト全体で最も費用対効果の高いリスク管理策なのだと理解しておきましょう。
作成するワイヤーフレームの質を劇的に向上させる3つのコツ
「伝わる設計図」に変身させる実践テクニックを3つ解説します。
- デザインしない・モノクロでシンプルに
- 「ユーザーファースト」を絶対に忘れない
- 完璧を目指さず「たたき台」として割り切る
多くの初心者が陥る「装飾への誘惑」を断ち切り、情報構造の議論に集中させる技術が重要です。クライアントや上司の要求に振り回されず、常にエンドユーザーの視点で検証する姿勢を貫くことで、本質的に価値のあるワイヤーフレームを作成できます。
完璧主義を捨て、建設的なフィードバックを引き出すツールとして活用する考え方が成功の秘訣です。
コツ1:デザインしない・モノクロでシンプルに
ワイヤーフレームでは色・フォント・装飾を一切使用しません。グレーの濃淡のみで要素の重要度を表現し、情報の階層構造を明確にします。
美しく見せることではなく、機能と配置を正確に伝えることが目的です。装飾に時間をかけるほど、本来議論すべき情報構造から関係者の注意がそれてしまいます。
あえて「未完成感」を残すことで、建設的な意見やアイデアを引き出しやすくする効果もあります。
コツ2:「ユーザーファースト」を絶対に忘れない
ワイヤーフレーム作成時は、常にエンドユーザーの行動パターンと目的を念頭に置きます。
クライアントの要望や会社の都合よりも、実際にサイトを使用するユーザーにとって最適な構成を優先します。ユーザビリティテストの結果やアクセス解析データがある場合は、それらを根拠に設計判断をおこないます。
「この配置でユーザーは迷わないか?」「重要な情報に素早くアクセスできるか?」を常に自問自答しながら設計を進めることが重要です。
コツ3:完璧を目指さず「たたき台」として割り切る
ワイヤーフレームは完成品ではなく、チームでの議論を活発にするためのコミュニケーションツールです。60%程度の完成度で関係者と共有し、フィードバックを収集しながら改善していくアプローチが効果的です。
最初から完璧を目指すと、時間がかかりすぎる上に、他者の意見を受け入れにくくなります。「まだ途中ですが、方向性はどうでしょうか?」というスタンスで提示することで、建設的な議論を促進できます。
実際の失敗事例から学ぶ!ワイヤーフレーム作成のよくあるNG例と対処法
現場のリアルな失敗談から、「こうなったらどうする?」の具体的な解決策を提示します。
- 「思っていたのと違う」と言われた場合
- デザイナーから「これじゃ作れない」と言われた場合
- クライアントが途中で要求を変更してきた場合
トラブルが発生してからの対処法だけでなく、事前の予防策も含めた完全対策マニュアルです。失敗は避けられないものと受け入れ、早期発見・早期対処のシステムを構築することが重要です。
チーム内でのコミュニケーション不足が最大の要因であることを理解し、情報共有の仕組みづくりに力を入れましょう。
NG例1:「思っていたのと違う」と言われた場合
クライアントから「思っていたのと違う」と言われた時は、まず具体的にどこが期待と異なるのかを明確にします。感情的な反応ではなく、客観的な事実を整理することから始めます。
次に、最初の要件定義に立ち返り、認識のズレがどこで生じたかを特定します。修正時は、同じ問題を繰り返さないよう、より詳細な注釈と複数のパターン提示をおこない、段階的に合意を形成していきます。
NG例2:デザイナーから「これじゃ作れない」と言われた場合
デザイナーから実装困難を指摘された場合、技術的制約と要件のバランスを再検討します。エンジニアも交えた三者会議を開催し、実現可能な代替案を模索します。
重要なのは要件の本質的な目的を維持しながら、実装方法を柔軟に変更することです。今後は、ワイヤーフレーム作成段階でデザイナーの意見を取り入れ、技術的実現性を事前に確認するプロセスを導入します。
NG例3:クライアントが途中で要求を変更してきた場合
要求変更は避けられない現実として受け入れ、変更管理のルールを明確にします。変更による影響範囲(時間・コスト・品質)を定量的に示し、クライアントに判断材料を提供します。
小規模な変更は柔軟に対応し、大規模な変更は別途プロジェクトとして扱う境界線を設定します。変更履歴を記録し、後から「言った・言わない」の議論にならないよう、書面での確認を徹底することが重要です。
サイト制作に伴うワイヤーフレーム作成でお困りならTHINkBAL

Webサイト制作の成功は、その土台となるワイヤーフレームで決まります。私たちは、ただ線を引いて配置を決めるだけではありません。お客様のビジネスが成功するための「勝てる設計図」を、目的の整理から一緒に考え抜きます。
成果から逆算して、誰に何を伝えるべきか、情報や機能の骨組みを戦略的に固めるため、「作った後に『思っていたのと違う』となる失敗」を根本から防ぎます。サイト制作の最も重要な工程だからこそ、ぜひ一度THINkBALにご相談ください。
THINkBAL流「成果から逆算する」ワイヤーフレーム術
一般的なワイヤーフレームが情報の配置整理に留まるのに対し、私たちのワイヤーフレーム作成は、常にビジネスの最終成果から逆算して設計します。
最初におこなうのは、「このWebサイトで達成すべき最も重要な数値目標(KPI)は何か」という定義です。例えば「質の高い問い合わせを月20件獲得する」というゴールを設定した場合、配置する一つひとつの要素に対して「これは目標達成に貢献するか?」と問い続けます。
ユーザーをゴールへと導く動線上にないコンテンツや、意思決定を迷わせる不要なリンクは、この段階で徹底的に削ぎ落とします。これにより、ワイヤーフレームは単なる骨組みではなく、ビジネス課題を解決するための「成功への設計図」となるのです。
THINkBALでワイヤーフレーム作成まで含めて担当した〇〇制作の事例

アパレル関連のOEM/ODM事業などを展開するAMS株式会社様のコーポレートサイト制作を担当しました。多岐にわたる事業の強み、特に「ECからOMOまで」を網羅する包括的なソリューションを分かりやすく伝え、企業の先進的な姿勢を表現することが制作の課題でした。
私たちはまず、複雑な事業内容を整理し、拡張性のあるECシステムから店舗・倉庫運営までを含む同社の提供価値を「SOLUTION」として明確に提示する情報設計から着手しました。
デザイン面では、黒と金を基調とした配色で企業の格の高さと信頼性を表現。ファーストビューで力強いメッセージと実績を伝えつつも、サイト全体ではユーザーが直感的に情報を理解できる、シンプルで洗練された構成を目指しました。
企業の持つ本質的な価値と、業界をリードするソリューションパートナーとしての未来へのビジョンが伝わるよう、細部までこだわって制作しました。
まとめ:ワイヤーフレームで必ずプロジェクトを成功させる
ワイヤーフレーム作成は、プロジェクト成功の要となるコミュニケーションツールです。完璧な設計図を作ることよりも、関係者との認識共有と合意形成を重視することが成功の秘訣です。
5つのステップを着実に実践し、適切なツールとテンプレートを活用することで、初心者でも確実にプロジェクトを前進させることができます。失敗を恐れず、建設的なフィードバックを歓迎する姿勢で取り組んでください。
ワイヤーフレーム作成でお困りなら、ぜひ一度THINkBALにご相談ください。私たちは単なる設計図ではなく、お客様のビジネスが成功するための「勝てる設計図」を、目的の整理からご一緒します。成果から逆算して戦略的に骨組みを固めるため、「思っていたのと違う」という失敗を根本から防ぐことをお約束します。
ワイヤーフレームから対応できるWebサイト制作

ワイヤーフレームからWebサイト制作を依頼しませんか?
- ワイヤーフレームの作成もお願いしたい
- 自社に合うWebサイトを提案してほしい
- 企画から丁寧に対応してほしい
Webサイト制作で実績のある
THINkBALにお任せください
Works
事例紹介

Relation 関連記事

- Web制作
2023/10/9Webサイト改善におすすめの施策12選|陥りやすい失敗についても紹介
- マーケティング
2024/5/7Web集客がうまくいかないのはなぜ?効果的なWeb集客方法や成功事例を紹介!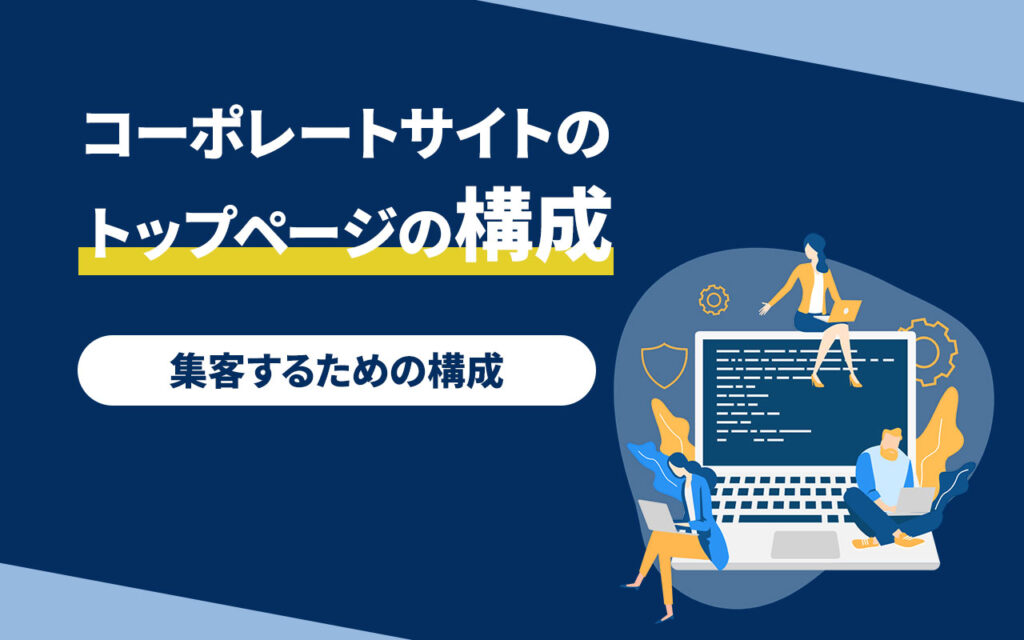
- Web制作
2025/8/9【2025年版】コーポレートサイトデザイン完全ガイド|戦略・運用まで徹底解説
- Web制作
2024/6/30金融サイト制作でおすすめ制作会社5選|依頼先の4つの選び方のポイント
- Web制作
2024/6/30フィットネス系でおすすめの制作会社7選|制作のポイントなども解説!
- Web制作
2024/11/9不動産業界のサイト制作方法は?ポイントや費用、制作会社の選び方
What's New 新着情報

- Web制作
2025/9/10ランディングページの制作費用の相場は?内訳や料金事例を徹底解説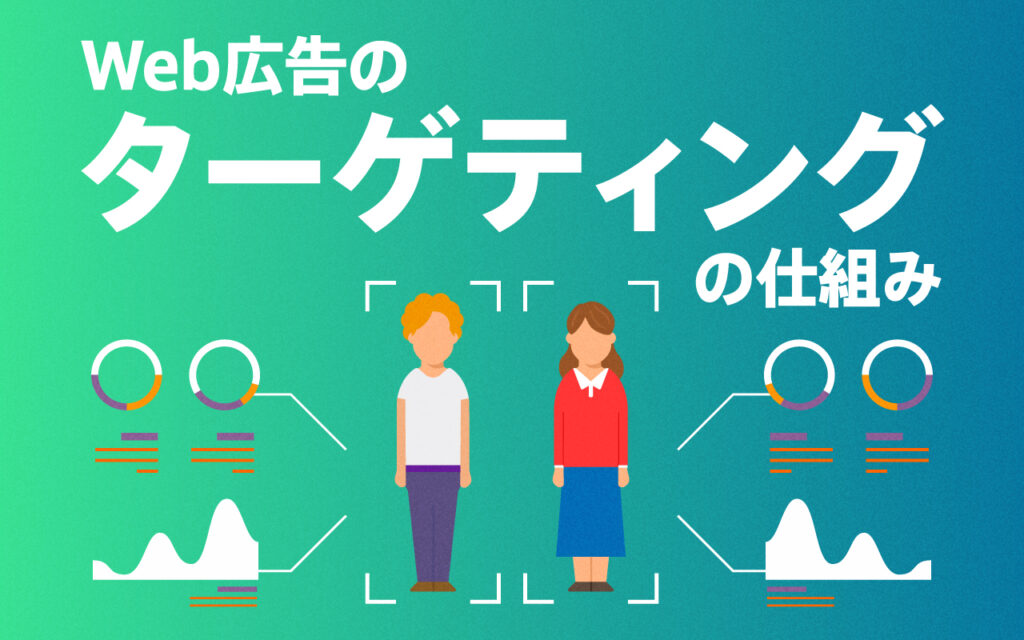
- Web広告
2025/9/10Web広告のターゲティングの仕組みは?種類や運用のメリット・デメリット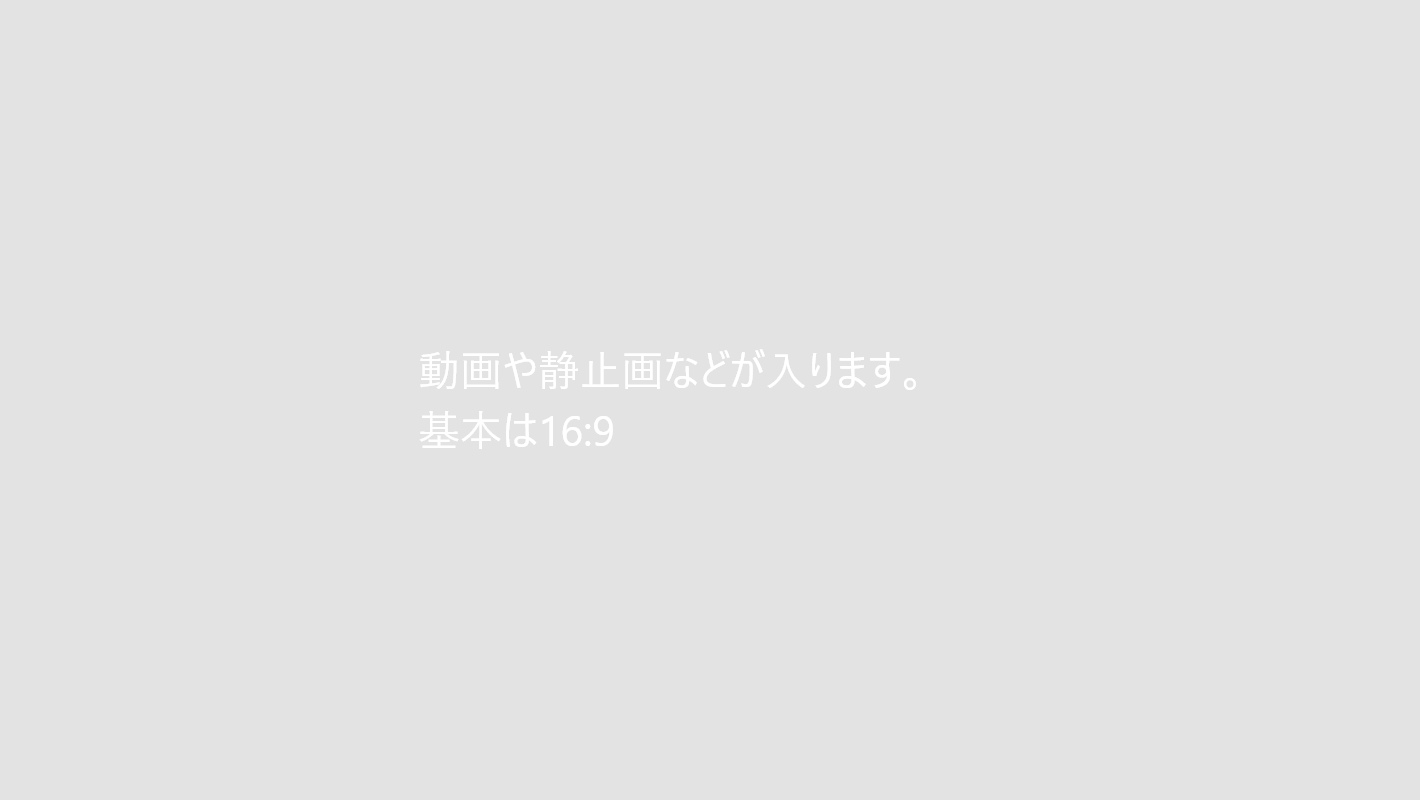 NEW2025/9/7【2025年最新】ワイヤーフレーム作成の教科書|初心者でも失敗しない5ステップとツール選び
NEW2025/9/7【2025年最新】ワイヤーフレーム作成の教科書|初心者でも失敗しない5ステップとツール選び
- Web制作
2025/9/7コーポレートサイトをリニューアルすべきタイミングはいつ?費用や成功事例も解説
- Web制作
2025/9/7見やすい企業のホームページとは?参考例やポイントを解説!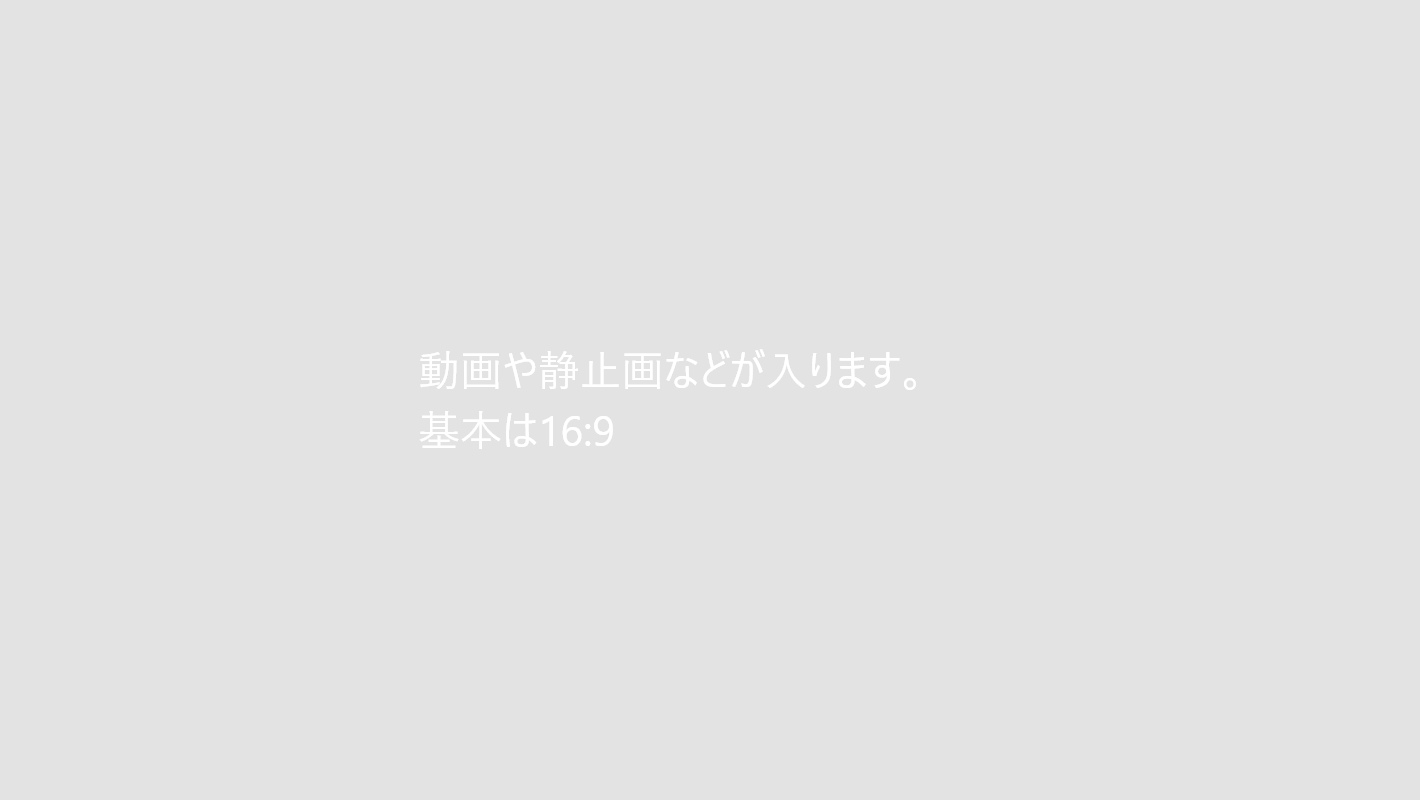 NEW2025/9/7コーポレートサイトとホームページの違いとは?目的別の最適な判断基準と制作で失敗しない質問リストを紹介
NEW2025/9/7コーポレートサイトとホームページの違いとは?目的別の最適な判断基準と制作で失敗しない質問リストを紹介
Recommend オススメ記事
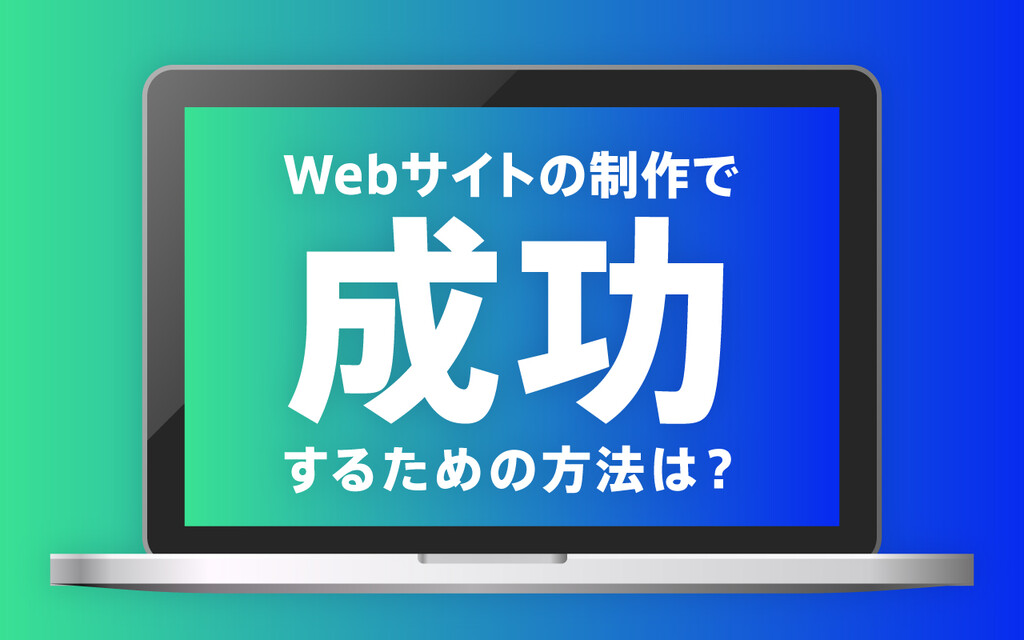
- Web制作
2024/7/1BtoBサイトでおすすめの制作会社14選|BtoBビジネスで成功するには
- Web制作
2024/4/13ホームページリニューアルの費用の相場は?流れ、メリットデメリット、ポイントを解説
- Web制作
2024/4/28採用サイトの集客方法5選!採用に必要なコンテンツは?
- UX/UIデザイン
2024/9/28サイトの問い合わせを増やす施策を8つ紹介!CTAボタンの設置方法も解説!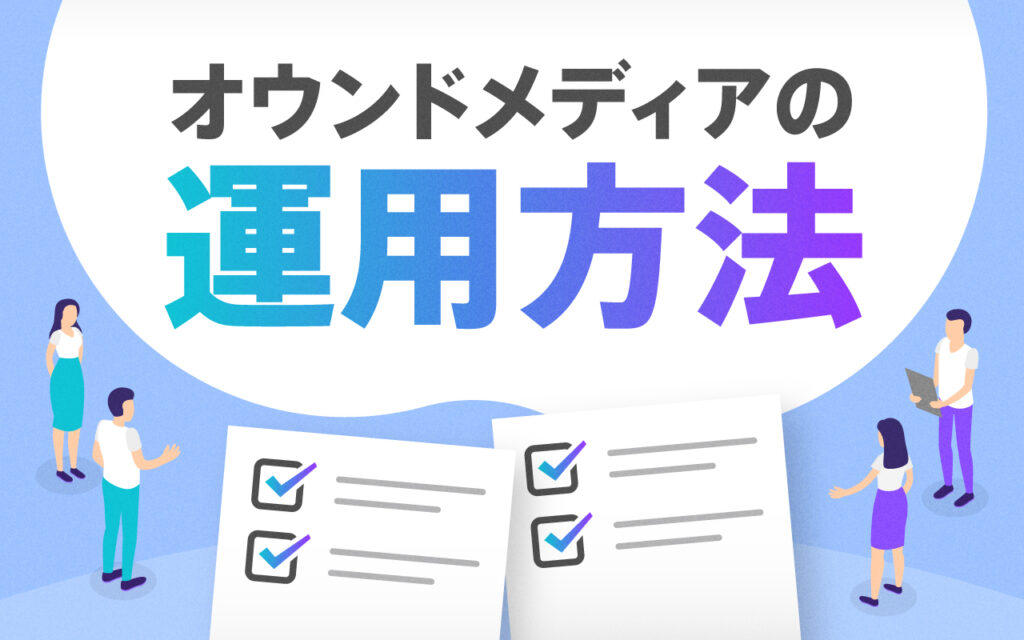
- Web制作
2024/9/19オウンドメディアの運用方法|成果の出るポイントを押さえて運用しよう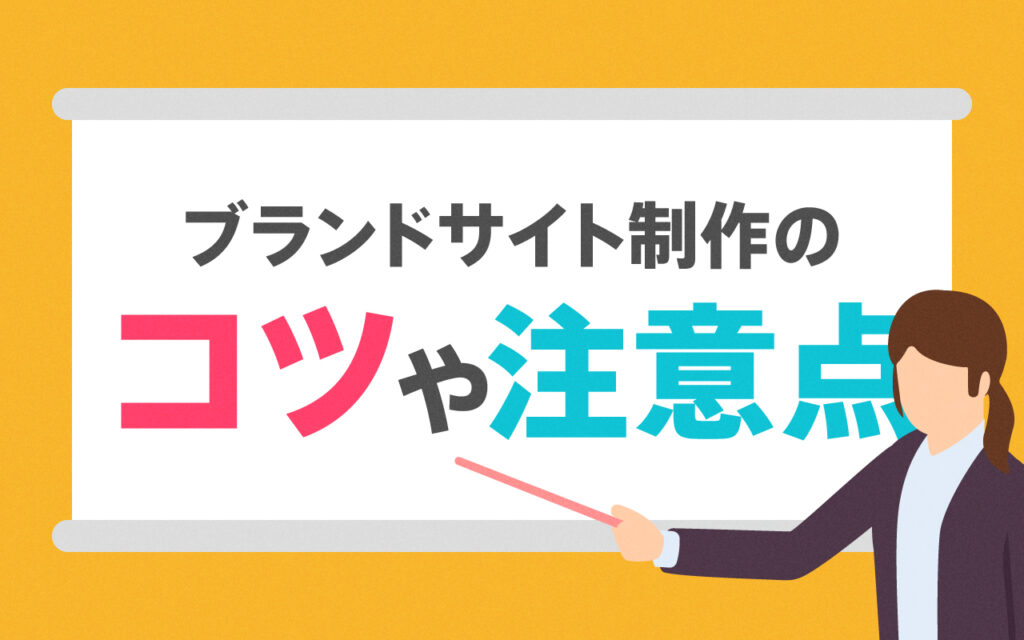
- Web制作
2024/4/28ブランドサイト参考事例10選!制作のコツや注意点についても解説
- Web制作
2024/5/5コーポレートサイトのSEO対策は必要?対策方法や注意点
- Web制作
2024/5/5採用サイトの改善方法とは?課題の見つけ方やリニューアルのポイントについても解説
- コンテンツマーケティング
2024/4/6コンテンツマーケティングの効果的な進め方とは?3つの成功事例も紹介