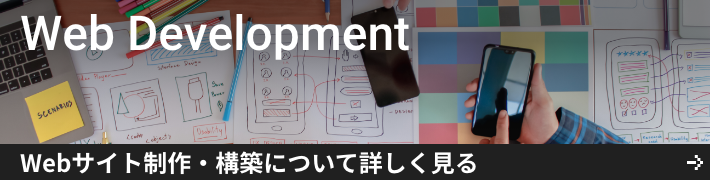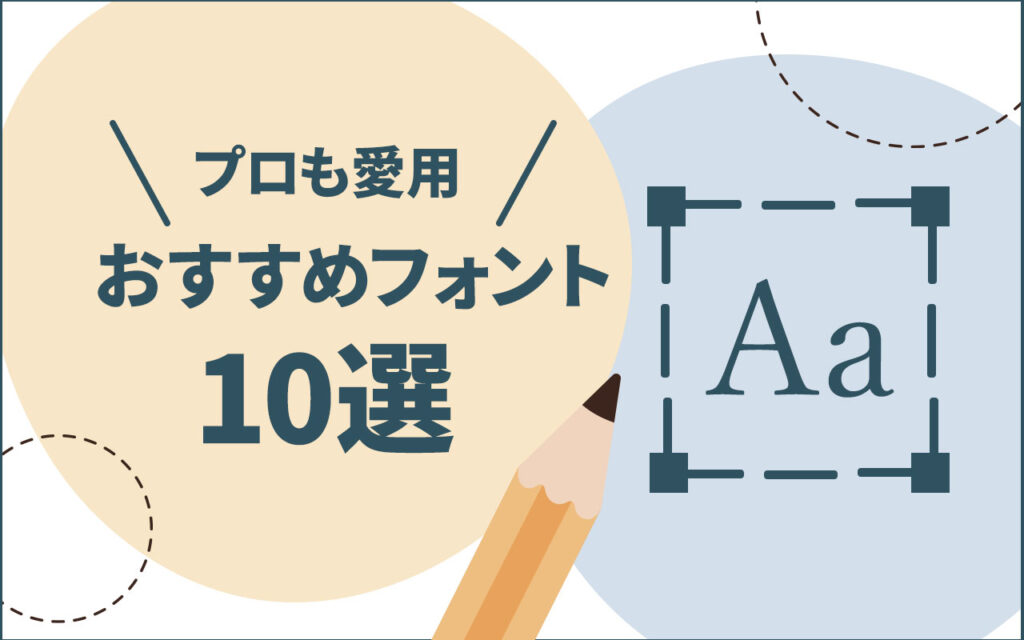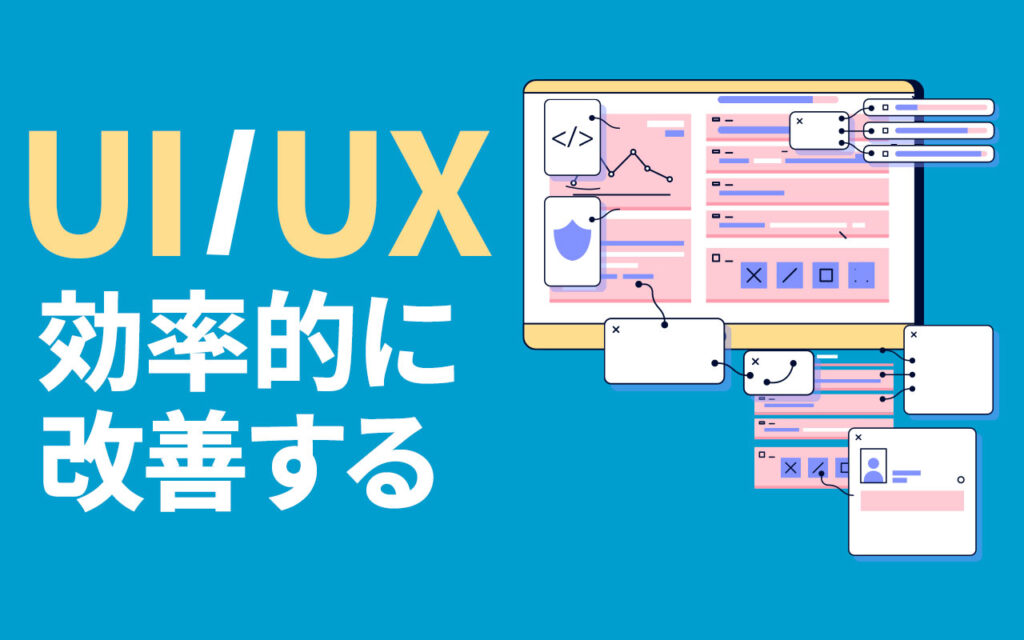
UI/UXを効率的に改善する4つの方法と改善に成功した6社の手法を紹介
近年、ユーザーが企業やサービスに求めるレベルは上がっています。それはWebサイトにおいても例外ではなく、UI/UXの重要性と具体的な改善方法について把握しておくことで、WebサイトやアプリのCV率を向上させることが可能です。
しかし、UI/UXを改善したくても具体的な方法がわからないという人も多いでしょう。
- UI/UXを改善したい人
- UI/UXを改善してユーザー満足度を上げたい人
- そもそもUI/UXがなにかよくわかっていない人
この記事では、UI/UXの重要性と改善策を、成功例を交えてお伝えしていきます。
当社「THINkBAL」は、UI/UX改善を目的としたサイトデザイン・リニューアルを得意としております。自社のWebサイトの使用感に気になる点がある方はお気軽にご相談ください。
データ分析、UX/UI設計に基づく戦略とデザインで伝えたい価値を伝わるカタチに。
ビジネス成果に貢献するUI/UXデザインを提供します。
UI/UXの違い|改善方法を知る前に基礎を抑えましょう

「UI/UXは知っているけど、明確な違いが分からない」という人も多いのではないでしょうか。そこで、以下にてUI/UXの違いについて詳しく解説していきます。
| 表記 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| UI | ユーザーインターフェース | ボタンや画像などユーザーの目に触れるもの全般 |
| UX | ユーザーエクスペリエンス | 画像やボタンなどを通じて得るユーザーの体験 |
UIとは
UIとは、ユーザーインターフェース(User Interface)の略で、ユーザー(人)とのインターフェース(接点)になるもの全てを指します。ここでいうユーザーとは、Webサイトやアプリの利用者で、インターフェースは接点、つながりです。
つまりUIとは、Webサイト上、またはアプリ上にある「画像」「文字」「ボタン」など、ユーザーが目にする全ての要素を指しています。
UXとは
一方のUXとは、ユーザーエクスペリエンス(User Experience)の略で、ユーザーがWebサイトやアプリなどを通して得る体験を指しています。
ここでいう体験とは、たとえば「ボタンが適切な場所に設置されていて使いやすい」「商品の写真がスライド形式で色々なデザインが見えるから使いやすい」などといった体験を指すのが一般的です。
UI/UXの違いについてより詳しく下記にまとめておりますので、あわせてご覧ください。
WebサイトにおいてUI/UXの改善が重要な理由

「UI/UXの改善はサイトの質を向上するうえで重要だ」といわれる理由は下記の通りです。
- かっこいいだけのデザインでは売れなくなった
- ユーザーの行動や心理を考えてデザインしなければならない
- UI/UXがサービス商品の品質にもつながっている
- UI/UXが企業ブランディングにつながる
以下では、それぞれの理由について詳しく解説していきます。
かっこいいだけのデザインでは売れなくなった
まず一つ目の理由として「Webサイトの外観がかっこいいだけでは商品が売れなくなった」という理由があります。
ユーザーが、Webサイトを利用する際には必ず「利用する目的」を持っていますが、その目的は「サイトのデザインがかっこいいから」という理由で解決することはできません。
ユーザーの目的を達成させるためには、かっこいいデザインではなく、ユーザーが望む情報を適切に表すUIや、情報へたどり着くまでのサポートができるUXが必要になります。
したがって、かっこいいデザインのサイトは、ユーザーの満足度を上げる要素としての需要はあるものの、最も重要な「目的の達成」につながらないため、外観のかっこいいサイト作りよりもUI/UXの最適化を優先するべきといえるのです。
ユーザーの行動や心理を考えてデザインしなければならない
UI/UXの改善は、ユーザーの行動や心理を考えて行うデザインであるため、サイトのCV率の向上につながりやすくなります。ユーザーの行動や心理を予測し、先回りすることでエラーを回避したり、ユーザーが欲する情報への導線を的確に引けたりするようになるからです。
たとえば、「ユーザーが好む文字のフォントや大きさ」「画面上に出てくるアイコンが多過ぎてユーザーにストレスを与えていないか」などと考えることで、ユーザーの行動心理を把握することにつながります。
なお、ユーザーは直感的な操作を好む傾向にあるため、マニュアルを読まないと操作できないようなサービスは離脱されやすくなります。注意しておきましょう。
UI/UXがサービス商品の品質にもつながっている
UI/UXを改善することでサービスや商品の品質向上にもつながります。
たとえば、商品が探しやすく、ユーザーに合っているおすすめ商品を定期的に紹介してくれる通販サイトと、お目当ての商品に中々たどり着かず、的外れな商品をおすすめしてくる通販サイト、どちらがユーザーに好まれるかは火を見るよりも明らかです。
そして前者の通販サイトで購入したユーザーには、ただ商品を購入しただけでなく「気持ち良く買い物ができた」という体験が付加されますから、商品の品質も良いように感じるでしょう。逆に、後者の通販サイトで商品を購入したユーザーには「買うのに苦労した…」というネガティブな体験が付加されるため、商品の品質自体も低いように感じさせてしまいます。
このように、UI/UXを改善してユーザーにとっての有益性を良くすることで、商品・サービスの品質を底上げすることにもつながるのです。
UI/UXが企業ブランディングにつながる
UI/UXを改善することは、企業ブランディングにもつながります。これについては皆さんもすでに体験されているのではないでしょうか。
たとえば、暇つぶしにインストールしたアプリの操作性や外観が良く、気に入ったとします。そのアプリを開発した会社から新作のアプリが出たとき、ついつい気になってしまいますよね?
それは、UI/UXの優れたアプリを開発した会社への信頼度が高くなっていたからに他なりません。同じことがWebサイトやソフトウェアなどに言えるでしょう。
このように、UI/UXの優れたWebサイトやアプリケーションを作成することで、その作成元となる企業のブランディングにつながるのです。
ブランディングの成功事例は下記にまとめておりますので、あわせてご覧ください。
自社WebサイトのUI/UX観点でチェックすべき改善ポイント
貴社のWebサイトにおいて、UI/UX観点で主にチェックしたい改善ポイントは以下の5つです。
- メニューはすぐ見つかる場所にあるか
- ボタンの文言はわかりやすいか
- 余白が十分にあるか
- リンク切れやエラーがないか
- スマホで使いやすいか
メニュー(ナビゲーション)はすぐ見つかる場所にあるか
WebサイトのUI/UXにおいて、メニューはすぐ見つかる場所にあるかは非常に重要です。
例えば、多くのサイトで使われている、画面の上部や左上にある「三本線(ハンバーガーメニュー)」のアイコンや、「商品一覧」「会社概要」といった文字が並んだ帯状のメニューは、一般的に「すぐ見つかる場所」とされています。
もし、メニューが画面の下のほうに隠れていたり、非常に小さい文字になっていたりすると、訪問者は次のページへ進むのをあきらめてサイトを閉じる可能性が高くなります。メニューの位置は、訪問者の行動をスムーズにするための基本としてチェックすべき重要なポイントです。
ボタンの文言はわかりやすいか
WebサイトのUI/UXにおいて、ボタンの文言はわかりやすいかも重要といえます。この文言は、クリックする前に「次に何が起こるか」を正確に予想できるくらい、具体的でわかりやすい必要があります。
例えば、「送信」というボタンよりも、「予約を確定する」や「資料をダウンロードする」のほうが、訪問者は行動した後の結果を理解しやすくなります。逆に、「こちら」や「次へ」といったあいまいな言葉だけでは、ボタンを押すのが不安になり、クリック率が下がることがあります。
ボタンの文言を改善することは、訪問者に安心して行動してもらうためのUI/UXの改善に直結します。文言を見ただけで行動する理由と結果がわかるようにすることが大切です。
余白が十分にあるか
WebサイトのUI/UX観点では、余白が十分にあるかも意識しましょう。文章や画像、ボタンといった要素の周りに十分な余白を設けることは、画面を見やすく、読みやすくするために非常に重要です。
もし、文字と文字、または画像と画像がぎゅうぎゅうに詰まっていると、訪問者は情報が多すぎると感じ、どこを読めばいいのかわからなくなってしまいます。その結果、必要な情報を見つけられずに疲れてしまい、サイトから離脱する原因になります。
適切な余白には、一つ一つの情報が独立して見えるようにし、訪問者が視線をスムーズに移動できるようにサポートする役割があるのです。文字と文字の間、見出しと本文の間など、必要な場所にきれいな余白を設けることで、訪問者にとってストレスの少ない快適な体験を提供できます。
リンク切れやエラーがないか
WebサイトのUI/UXでは、リンク切れ(デッドリンク)やエラー(404など)がないかも確かめてください。訪問者がせっかく興味を持ってリンクをクリックしたのに、目的のページにたどり着けないと、サイトの信頼性は大きく損なわれます。
リンク切れは、ページのURLを変更したのに、その古いURLを指したままのリンクが残っていることで発生します。また、サーバー側の問題で一時的にページが表示できなくなることもエラーの原因です。
これらの問題がないかを定期的に確認し、修正することは、サイトの品質を維持するための最低限の作業です。訪問者が常に正しい情報へたどり着けるように、常にサイトの状態を健全に保つことが、基本的なUI/UX改善となります。
スマホで使いやすいか
近年のWebサイトのUI/UXにおいては、スマホで使いやすいか(レスポンシブデザインであるか)も非常に重要です。現在、多くの人がスマートフォンを使ってWebサイトを見ています。そのため、パソコンで完璧に見えていても、スマホの小さな画面で操作しやすいかどうかを必ず確認しましょう。
スマホ対応でチェックすべき主なポイントは、画面の大きさに合わせてレイアウトが崩れていないか、文字が小さすぎて読めなくないか、そしてボタンが指で押しやすい大きさになっているかです。指で操作するスマホの場合、ボタン同士が近すぎると、間違って隣のボタンを押してしまうミス(誤操作)が起きやすくなります。
Webサイトのデザインをスマートフォンに最適化することは、もはや特別なことではなく、必須の改善項目です。訪問者がいつでもどこでも快適にサイトを利用できることが、良いUI/UXの土台となります。
WebサイトのUI/UX改善を成功させるための具体的な進め方
次に、UI/UX改善を成功させるための具体的な進め方を紹介していきます。今回紹介する方法は下記の通りです。
- ステップ1:目的設定時はKGIとKPIを明確にする
- ステップ2:ユーザー調査は定性・定量を組み合わせる
- ステップ3:課題の可視化はチームで共有する
- ステップ4:仮説は「誰のどんな課題をどう解決するか」まで定義する
- ステップ5:A/Bテストとヒートマップで効果検証する
以下では、それぞれの方法について詳しく解説していきます。
ステップ1:目的設定時はKGIとKPIを明確にする
UI/UXの改善を始める前に、まず「何のために改善するのか」という最終的な目的をはっきりと決めることが大切です。その目的を測るための指標がKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)とKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)です。
KGIは、改善活動の最終的なゴール、つまり「Webサイトで達成したい一番重要なこと」を数値で定めます。例えば、「3ヶ月後にWebサイトからの売上を20%増やす」といったものです。
次にKPIは、そのKGIを達成するために、途中の段階で「何をどれだけ進めるべきか」を示す指標です。たとえば、売上アップというKGIに対して、「資料ダウンロード数を月100件にする」や「商品ページを最後まで見た人の割合を5%上げる」などがKPIになります。
このKGIとKPIを最初に決めておくと、改善活動が成功しているかどうかが誰の目にも明らかになり、チーム全員が同じ方向を向いて進めるようになります。あいまいな目標ではなく、具体的な数字でゴールを決めることが成功の第一歩です。
ステップ2:ユーザー調査は定性・定量を組み合わせる
WebサイトのUI/UXを改善するには、「ユーザーが実際にどう使っているか」を知るための調査が欠かせません。この調査には、定性調査(ていせいちょうさ)と定量調査(ていりょうちょうさ)の2種類があり、これらを組み合わせることが重要となります。
定量調査は、数字で集められるデータのことです。たとえば、アクセス解析ツールを使って「何人がサイトを訪れたか」「どのページで何%の人が離脱したか」といった、行動の量や割合を把握します。
一方、定性調査は、数字では表せないユーザーの意見や感情を知るための調査です。例えば、実際にサイトを使ってもらい感想を聞くインタビューやアンケートなどがあります。「なぜこのボタンを押さなかったのか」「どこが使いにくいと感じたか」といった、ユーザーの考えや理由を深く探ります。
この二つの調査を組み合わせることで、「どこで問題が起きているか(定量)」と「なぜその問題が起きているか(定性)」の両方を理解できるようになり、改善の精度が大きく向上します。
ステップ3:課題の可視化はチームで共有する
ステップ2でユーザー調査を行い、Webサイトに存在するさまざまな問題点や改善点を見つけたら、次はそれらを「課題」として誰にでもわかるように書き出して整理し、チーム全体で共有する作業が必要です。これを課題の可視化といいます。
例えば、「スマートフォンでフォームの入力が難しい」という定性的な意見を、「スマホユーザーのフォーム入力完了率が、パソコンユーザーより15%低い」という定量的なデータと結びつけて明確な課題とします。
この課題のリストを、デザイン担当者、エンジニア、マーケティング担当者など、関わるすべての人がいつでも見られる場所に置いておきましょう。もし、課題の認識が人によって異なると、改善の方向性がブレてしまい、努力がムダになってしまいます。
課題を客観的な事実と数字に基づいてまとめ、チーム全員が「これが私たちが今から解決すべき問題だ」と同じ共通認識を持つことが、スムーズで効果的な改善活動につながります。
ステップ4:仮説は「誰のどんな課題をどう解決するか」まで定義する
課題が明確になったら、その課題を解決するための仮説(かせつ)を立てます。良い仮説とは、ただ「こうしたら良くなるだろう」と考えるだけでなく、「誰が」「どんな問題を抱えていて」「それをどう変えたら」解決するのかを具体的に定義したものです。
例として、「スマートフォンで問い合わせボタンが小さくて見逃されている」という課題があったとします。これに対する良い仮説は、「サイト訪問者(誰が)が、画面の下にある小さなボタン(どんな問題)を見落としているため、ボタンを画面の下部に常に表示される大きな固定ボタンに変える(どう解決するか)ことで、問い合わせ数が10%増える」といった形になります。
このように、仮説の中に「誰の」「どんな課題」が「どう解決する」かという要素を含めることで、次のステップである改善策の実行(デザイン変更など)がブレなくなります。また、改善後に検証すべき効果(問い合わせ数10%増)も同時に明確になるため、非常に効率的です。
ステップ5:A/Bテストとヒートマップで効果検証する
改善策を実行したら、それが本当に効果があったのかどうかを客観的に測る必要があります。そのための主な方法がA/Bテストとヒートマップです。
A/Bテストは、Webサイトの一部分(例えば、ボタンの色や文言、レイアウトなど)を変えたパターンAと、変更前のパターンBを、同じ期間に、訪れたユーザーにランダムで見てもらう方法です。どちらのパターンが、設定したKPI(例:購入率やクリック率)を達成できたかを比較することで、改善が成功したかどうかを数字で判断できます。
ヒートマップは、ユーザーがWebサイトのどこをよく見ていて、どこをクリックし、どこまでスクロールして読んでいるかを色の濃淡で示した図です。このツールを使うと、ユーザーが画面上で具体的にどう動いているかが視覚的にわかり、A/Bテストの結果だけでは見えない「なぜうまくいったか/いかなかったか」の理由を探るのに役立ちます。
この2つのツールを使い、仮説が正しかったかを検証し、次の改善につなげるサイクルを繰り返すことが、UI/UX改善を成功させるための最後の重要なステップです。
WebサイトのUI/UXの改善に役立つツール|無料・有料に分けて紹介
ウェブサイトのUI/UX改善は、データに基づいて進めることが成功の鍵です。ユーザーがサイトのどこで迷い、どこに価値を感じているかを客観的に知るために、適切なツール導入は不可欠です。これらのツールは、ユーザーのクリックや離脱といった行動データ、さらには実際の操作状況を提供し、課題の特定と改善効果の検証をサポートします。
ここでは、UI/UX改善活動で特に役立つ代表的な5つのツールを、利用料金と主な用途に分けて紹介します。無料ツールから高度な分析が可能なツールまで、自社の状況に合ったものを選び、データに基づいた効率的な改善サイクルを回しましょう。
| ツール名 | 利用料金 | 用途 |
|---|---|---|
| Google Analytics | 無料 | 訪問者数、コンバージョン率、離脱率などの定量データを分析します。サイト全体のパフォーマンス把握と、ユーザー導線のボトルネック特定に役立ちます。 |
| Microsoft Clarity | 無料 | ヒートマップとセッション録画により、ユーザー行動を視覚的に確認します。個々の操作を録画で見られるため、行動の理由を探る定性分析に有効です。 |
| Hotjar | 一部有料 | ヒートマップ、セッション録画に加え、アンケート機能でユーザーの「生の声」を集めます。行動データと意見から深いインサイトを得るために利用されます。 |
| User Heat | 一部有料 | マウスの動きや熟読度を色で表示するヒートマップに特化したツールです。PC、スマホなどデバイス別に分析でき、無料で5ページまで利用可能です。 |
| Sitest | 有料 | 純国産のLPOツールで、ヒートマップ分析、A/Bテスト、EFOなど多機能を提供します。コンバージョンに近い領域のデータ収集と検証を一元的に行えます。 |
これらのツールを効果的に活用することで、UI/UXの改善に必要なデータ収集、課題の深掘り、そして検証プロセスをスムーズに進めることができ、最終的なウェブサイトの成果向上につながります。
WebサイトのUI/UXの改善に役立つフレームワークの使い方・選び方
UI/UXの改善に役立つ主なフレームワークは、以下の通りです。
- カスタマージャーニーマップ
- サービスブループリント
- バリュープロポジションキャンバス
- ストーリーボードとプロトタイプ
それぞれのフレームワークの概要のほかに、使い方・選び方も解説するのでぜひ参考にしてください。
カスタマージャーニーマップ|体験の流れを時系列で把握する
カスタマージャーニーマップは、お客様(ユーザー)が商品やサービスを知ってから利用するまでの一連の体験の流れを、時間軸に沿って図で表すためのものです。ユーザーの行動、思考、感情の変化を可視化します。
| 項目 | 内容 |
| 概要(どのようなものか) | お客様(ユーザー)が商品やサービスを知ってから利用するまでの一連の体験の流れを、時間軸に沿って図で表すためのものです。ユーザーの行動、思考、感情の変化を可視化します。 |
| どんな場面で使うか | Webサイト全体を通して、「ユーザーがどこで満足し、どこで不満を感じているか」を特定したいときに使います。訪問から問い合わせや購入完了までの長い道のりに課題がないかを探るのに有効です。 |
| どんな場面で選ぶか | ユーザー体験のどの部分に課題があるかまだ絞り込めていないときや、Webサイトの全体的なユーザー導線を見直したいときにこのフレームワークを選びます。 |
サービスブループリント|表と裏のプロセスを見える化する
サービスブループリントは、Webサイトで提供するサービスが、お客様の目に触れる「表面のプロセス」と、企業の裏側で行われている「裏面のプロセス」の両方をまとめて可視化するためのフレームワークです。
| 項目 | 内容 |
| 概要(どのようなものか) | Webサイトで提供するサービスが、お客様の目に触れる**「表面のプロセス」と、企業の裏側で行われている「裏面のプロセス」**の両方をまとめて可視化するためのフレームワークです。 |
| どんな場面で使うか | ユーザーの問い合わせや予約がWebサイトで受け付けられた後、社内のチームやシステムがどのように動いてサービスを提供しているかを確認したいときに使います。 |
| どんな場面で選ぶか | Webサイトの改善が、企業の裏側の仕組みや業務効率にまで影響を与える可能性があるときや、オンラインとオフラインが連携するサービス(例:実店舗予約)の改善を行うときに選びます。 |
バリュープロポジションキャンバス|課題と価値のズレを確認する
バリュープロポジションキャンバスは、Webサイトが提供する「顧客への価値」と、ユーザーが実際に「抱えている課題やニーズ」がしっかりと一致しているかを確認するためのフレームワークです。
| 項目 | 内容 |
| 概要(どのようなものか) | Webサイトが提供する「顧客への価値」と、ユーザーが実際に「抱えている課題やニーズ」がしっかりと一致しているかを確認するためのフレームワークです。 |
| どんな場面で使うか | Webサイトのトップページや、商品紹介ページのメッセージやコンテンツが、ユーザーの求めているものと合っているかを確認したいときに使います。 |
| どんな場面で選ぶか | Webサイトのコンバージョン率(CVR)が低いときや、商品の魅力が訪問者にうまく伝わっていないと感じるとき、つまり「提供価値と顧客のニーズのズレ」が疑われる場合に選びます。 |
ストーリーボードとプロトタイプ|UI設計の認識ズレを防ぐ
ストーリーボードとプロトタイプは、新しいWebサイトのデザインや機能のアイデアを、実際の制作に入る前に具体的に確かめ、チームの認識のズレを防ぐためのフレームワークです。
| 項目 | 内容 |
| 概要(どのようなものか) | 新しいデザインや機能のアイデアを、実際の制作に入る前に具体的に確かめ、チームの認識のズレを防ぐためのフレームワークです。ストーリーボードは漫画で、プロトタイプは操作できる試作品を作ります。 |
| どんな場面で使うか | 新しい機能やデザインを開発する前に、「実際に使ったらどうなるか」をチーム内で具体的に議論したいときに使います。また、プロトタイプはユーザーテストでも使います。 |
| どんな場面で選ぶか | 大規模なリニューアルや新機能の追加で、関係者の間で「完成形」のイメージが異なっている可能性があるときや、実際に開発を始める前に手軽にデザインの使いやすさを検証したいときに選びます。 |
UI/UX改善で成功した事例選

最後に、UI/UXで成功した企業の事例を6つ厳選して紹介していきます。
「UI/UXを改善した企業の成功ポイント」を知っておき、自社のコンテンツに活かしていきましょう。今回紹介する企業は下記の通りです。
- 株式会社SUBARU
- 株式会社IDOM
- 株式会社パナソニック
- 株式会社うるる
- 株式会社ライトオン
- 株式会社クラウドワークス
- 株式会社フェリシモ
それでは以下にて「成功ポイント」「どういった改善をしたか」を見ていきましょう。
株式会社SUBARU

株式会社SUBARUの最重要USPである「安全」を軸としたブランドサイト「SUBARU SAFETY BRAND SITE」では、ユーザーが抱く「なぜスバル車は安全なのか?」という疑問を徹底的に解消する導線と構成を作り上げました。
主な改善(UI/UX設計)は以下の通りです。
- 安全性の追求にかける想い、独自の総合安全、最新の安全技術のエビデンスなど、ユーザーが知りたい情報へスムーズにたどり着けるUXデザインを実施
- サイトに来訪すれば、スバル車が安全である理由を完全に理解できるように設計
- ブランドイメージを保ちつつ、情報を明確に伝えるデザインとコーディング
この事例では、単にかっこいいデザインを目指すのではなく、企業の核となる価値(安全)をユーザーの行動や心理を先回りして提示することで、ユーザー満足度と企業ブランドへの信頼度を高めました。
なお、THINkBALが「SUBARU SAFETY BRAND SITE」のUXデザインを担当いたしました。UI/UXにこだわったサイト制作をご希望の企業様は、THINkBALへご相談ください。
「株式会社IDOM」

株式会社IDOMは、中古車を販売している企業です。車の販売は、実店舗で行っているためWebサイトでは相談予約をCVとして運営しています。
同社がUI/UXを改善した成功ポイントは下記の通りです。
- 車種一覧や絞り込み機能を使っている人に対してサイトに掲載していない車を提案するためのUI/UXを作った
- 初心者向けに発信されたコンテンツを行き来している人には「車探しの手伝い」という軸のUI/UXを作成して訴求した
このように同社は、ユーザーのニーズや状況に適したコミュニケーション方法を提案することでCVを増やすことに成功しています。
「株式会社パナソニック」

株式会社パナソニックは、家電製品を販売している企業です。改善したのはテレビ製品を紹介しているWebサイトの直帰率を下げるためのUIでした。
では、成功ポイントを見てみましょう。
- ページ上部から下部へ移動するボタンを設置した
- ヒートマップでユーザーが最も欲している情報を明確にし、ニーズの高かった情報をファーストビューに移動した
こういった改善を成功させたことでWebサイトの離脱率が5%減少し、滞在時間も良好になったそうです。
こういった事例から、ページのボリュームが大きい場合は、下部から上部へのボタンだけでなく、上部から下部へ移動するボタンを設置することの重要性が分かります。
「株式会社うるる」

株式会社うるるは、BPO事業やクラウドソーシング事業を営むIT企業です。同社の成功ポイントを見てみましょう。
- 現場の運用フローを見直し、新しいフロー図を作成した後に本質的な課題を抽出した
- どの機能が売上に直結しているかを精査し、優先度が高いものから実装した
同社のように、本質的な課題が何かを明確にすることは大切です。また、実装する機能が複数ある場合には優先度を立て、それに従って実装するとよいでしょう。
「株式会社ライトオン」

株式会社ライトオンは、ジーンズを中核としたさまざまなカジュアルウエアを販売する企業で、ECサイトを運営しています。同社の成功ポイントは下記の通りです。
- 実店舗に来店したお客さんにアンケートを実施した
- 経営陣を交えて課題整理・アクションプランのすり合わせを行った
- KPIとUI/UXを結びつけることで重要なアクションが何かを明確にした
同社はこれらの施策を行うことでECサイト経由での売上を倍増することに成功しています。本質的な課題を明確にし、優先度の高い施策を積極的に行うことで改善が成功したのだと考えられます。
「株式会社クラウドワークス」

株式会社クラウドワークスは、仕事を探している人と業務を外注したい人をマッチングするプラットフォームを運営しています。同社の成功ポイントは下記の通りです。
- ユーザーの意思決定に関わっている情報が何であるかを調査した
- 求人ページに「掲載日時」「仕事条件の詳細」など意識決定に関わっていた情報を追記した
- 文字サイズ・色合いなどのデザインを読みやすいように改善した
同社はこれらの施策を行ったことで求人への応募率が約20%向上しています。ユーザー分析の重要性が伺える結果といえるでしょう。
「株式会社フェリシモ」
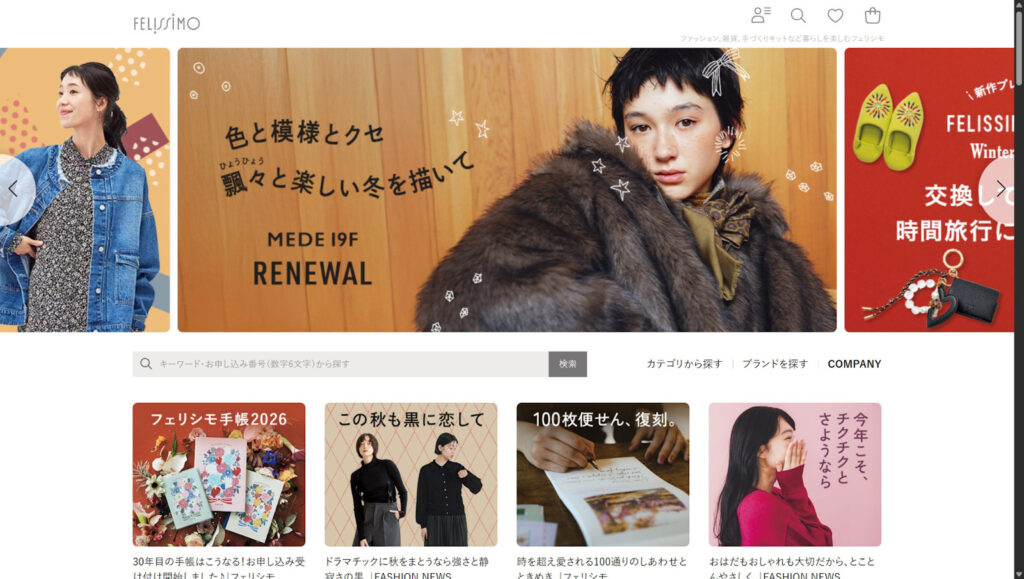
株式会社フェリシモは、子供服や手作り雑貨などを販売するECサイトを運営しています。同社の成功ポイントは下記の通りです。
- 郵便によるDMを休眠顧客に送付した
- DMからアクセスのあったユーザーの行動を分析した
- 分析の結果パスワードを忘れている顧客が多かったためパスワード照会に関するUI/UXを改善した
同社は、これらの施策のおかげで年間にして約1万人の離脱防止に成功しています。新規顧客と休眠顧客では、打つべき施策が異なる点にも注意しておきたいところです。
WebサイトのUI/UX改善でよくある失敗とその対策方法
UI/UX改善でよくある失敗は以下の通りです。
- 見た目だけにこだわって使いにくくなる
- 改善内容が自己満足になってしまう
- データを見ずに変更して効果が出ない
- 頻繁あるいは大幅な変更を加えすぎてユーザーが迷う
- UI/UX改善後のテストを怠る
各見出しで対策方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。
見た目だけにこだわって使いにくくなる
WebサイトのUI/UX改善において、デザインや見た目のかっこよさばかりに注目してしまうのは、よくある失敗です。洗練されたデザインは魅力的ですが、見た目を優先した結果、サイトが使いにくくなってしまうことがあります。
例えば、おしゃれなフォント(文字の形)を使ったために文字が読みにくくなったり、かっこいいアニメーションを多用した結果、ページの読み込みが遅くなったりといった問題です。
Webサイトにとって最も重要なのは、訪問者が目的を達成できることです。ボタンが押しやすい場所にあるか、必要な情報がすぐに見つかるかといった「使いやすさ(UX)」が損なわれては意味がありません。
対策方法としては、デザインを変更する際、必ず「目的達成のしやすさ」を最優先することです。デザイン案ができたら、実際にターゲットとするユーザーに触ってもらい、使いにくくないかフィードバックをもらうことが重要です。
改善内容が自己満足になってしまう
UI/UX改善は、サイトの管理者や制作側が「こうすれば良くなるはずだ」「これが便利だろう」という自分たちの考えだけで進めてしまうと、失敗につながります。これが、改善内容が自己満足に終わってしまうパターンです。自分たちにとっての「使いやすさ」が、実際にサイトを利用する多数のユーザーにとっての「使いやすさ」と異なっていることはよくあります。
ユーザーは、管理者とはWebサイトを見る頻度や目的が違うため、見慣れていないことに対して抵抗を感じることがあります。
対策方法としては、必ず改善の根拠を「ユーザー調査」や「アクセスデータ」に求めることです。ユーザーインタビューやアンケートを行い、実際にユーザーが何を不満に感じているか、何を求めているかを正確に把握してから改善策を立てるようにしましょう。自分の感覚や意見だけを頼りに改善を進めてはいけません。
データを見ずに変更して効果が出ない
WebサイトのUI/UXを改善するとき、アクセス解析ツールなどで現状のデータを確認せずに、思いつきや感覚だけで変更を加えてしまうと、効果が出ずに終わる可能性が高いです。例えば、「このボタンの色を変えたらクリックされそう」と安易に判断して変更しても、その変更が本当にユーザーの行動に良い影響を与えたかどうかがわからず、時間と労力が無駄になってしまいます。
データを見ないということは、「どこに本当の課題があるのか」を特定できていないことを意味します。そのため、課題ではない部分を改善しても、成果は出ません。
対策方法は、変更前に必ずデータで課題を特定することです。Google Analyticsなどのツールを使い、離脱率が高いページ、クリックされていないボタン、訪問者が熟読していない場所など、具体的な問題点を数字で把握しましょう。そして、そのデータに基づいて「この問題を解決するために変更する」という論理的な流れを作ることが重要です。
頻繁あるいは大幅な変更を加えすぎてユーザーが迷う
Webサイトをより良くしようと、デザインやレイアウト、機能などを短期間で頻繁に変えすぎたり、一度に大幅に変更したりするのは、ユーザーを混乱させる失敗です。ユーザーは、いつも利用しているサイトの構成や操作方法を一度覚えると、次からはスムーズに利用できるようになります。
しかし、サイトの見た目やメニューの位置が大きく変わると、ユーザーは「いつもの場所」を見失い、目的の情報にたどり着けなくなってしまいます。その結果、サイトに対する不満が高まり、使い慣れたユーザーほど離脱してしまう可能性があります。
対策方法は、変更を加える際は段階的に行うか、または変更の理由を明確に伝えることです。ユーザーがサイトに慣れるための猶予期間を設け、頻繁な変更は避けましょう。やむを得ず大幅な変更を行う場合は、サイト上で「ここが変わりました」というガイドを一時的に表示するなど、ユーザーが新しい使い方を学べるようなサポートを行うことが大切です。
UI/UX改善後のテストを怠る
UI/UXの改善策を実行した後、「これで良くなったはずだ」と満足して効果検証のためのテストを怠ってしまうのも、大きな失敗の一つです。どんなに良い仮説を立てて完璧なデザイン変更を行ったとしても、実際にユーザーが利用した結果、予期せぬ問題が発生したり、想定していたような効果が出ないことはよくあります。
テストをしないということは、その改善が本当に成功だったのか、それとも失敗だったのかを客観的なデータで判断できないということです。成功か失敗かわからなければ、次の改善活動にも活かすことができません。
対策方法としては、A/Bテストやヒートマップ分析を必ず実施することです。変更を加えた新しいパターンと、変更前のパターンを比較し、どちらがよりコンバージョン率が高いか、離脱率が低いかなどを数字で検証します。テストの結果、効果が低ければ元のデザインに戻すか、さらに別の改善策を検討するといったサイクルを回すことが重要です。
UI/UXを改善してユーザーに好まれるWebサイトを作りましょう

UI/UXは、WebサイトやアプリのCV率向上を図るうえで、必ず向き合わなくてはいけない大切な要素の一つです。優れたコンテンツを発信することも大切ですが、UI/UXを最適化してユーザーに好まれるサイト作りを行うことは更に重要であるといえるでしょう。
「UI/UXの大切さは分かったから専門家に相談したい」「リソース不足で対応できないのでプロに任せたい」とお考えの方は、ぜひTHINkBALにご相談ください。
Webサイト上の改善点の把握と効果的なUI/UXデザインの改善

ユーザーニーズを汲み取り、効果的なUI/UX改善をしてみませんか?
- UI/UXを改善して、ユーザーの満足度を上げたい
- UI/UX改善施策の実施を依頼したい
- UI/UX改善が得意な制作会社を探している
UI/UXデザインなら
THINKBALにお任せください
Works
事例紹介

Relation 関連記事
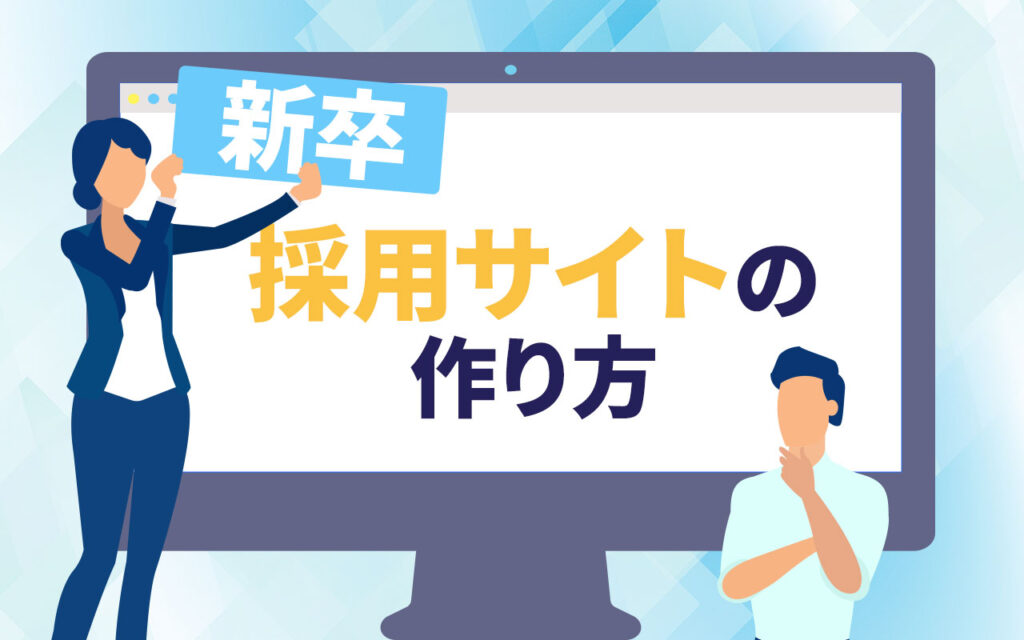
- Web制作
NEW2026/1/5新卒採用サイトの作り方|中途向けとの違いやデザイン事例も徹底解説
- SEO
2025/5/14【保存版】SEOを用いたサイト改善の全手順|よくある失敗パターンと成功のコツ
- コンテンツマーケティング
2026/1/19【無料あり】記事作成におすすめの生成AIツール10選!活用メリット・デメリットも解説
- Web制作
2025/2/26ホームページのリニューアルに使える補助金一覧|補助金を使って低コストでサイト改善
- SEO
2025/2/26ドメインランク(ドメインパワー)とは?効果的に上げる方法とGoogleの評価を解説
- Web制作
2025/1/31ドメインの強さとSEOの関係性は?ドメインパワーの詳細を解説
What's New 新着情報

- Web制作
NEW2026/1/31パーソナルジムのホームページ制作で集客する方法とおすすめ制作会社8選
- Web制作
NEW2026/1/31WordPress制作会社おすすめ25選!費用相場と選び方を徹底解説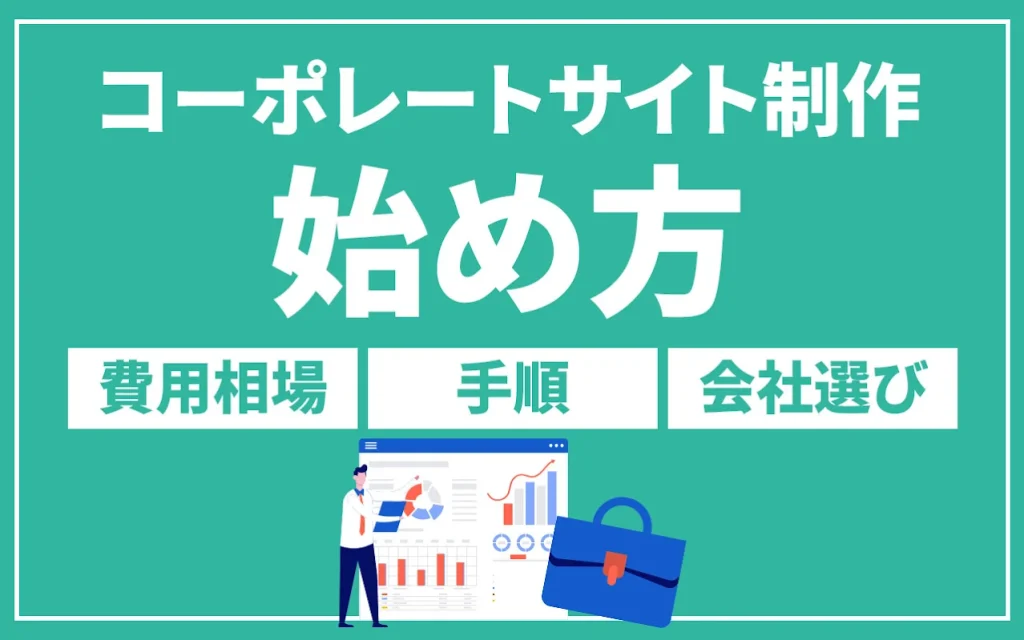
- Web制作
2026/1/31コーポレートサイト制作の始め方|費用相場・手順・会社選びを解説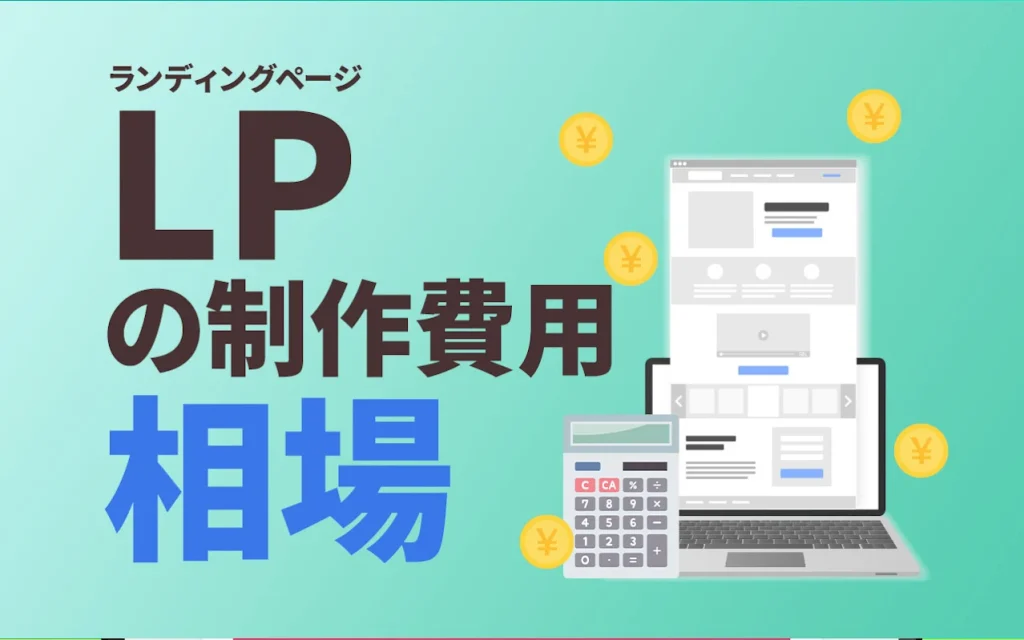
- Web制作
2026/1/31ランディングページの制作費用の相場は?内訳や料金事例を徹底解説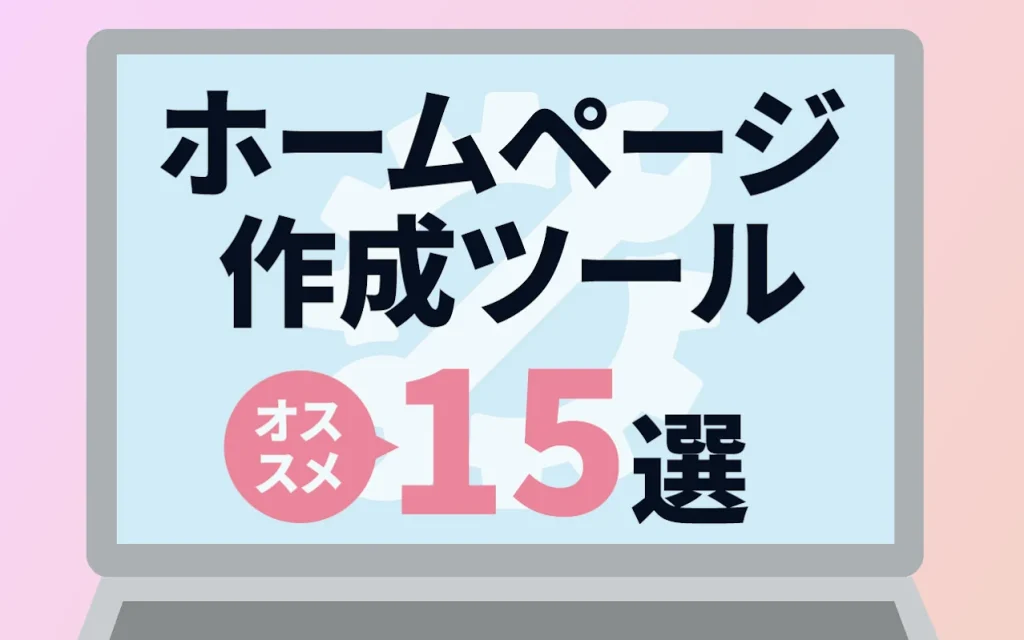
- Web制作
2026/1/31ホームページ作成ツールおすすめ15選【2026年最新版】無料・有料のツールを用途別に徹底比較!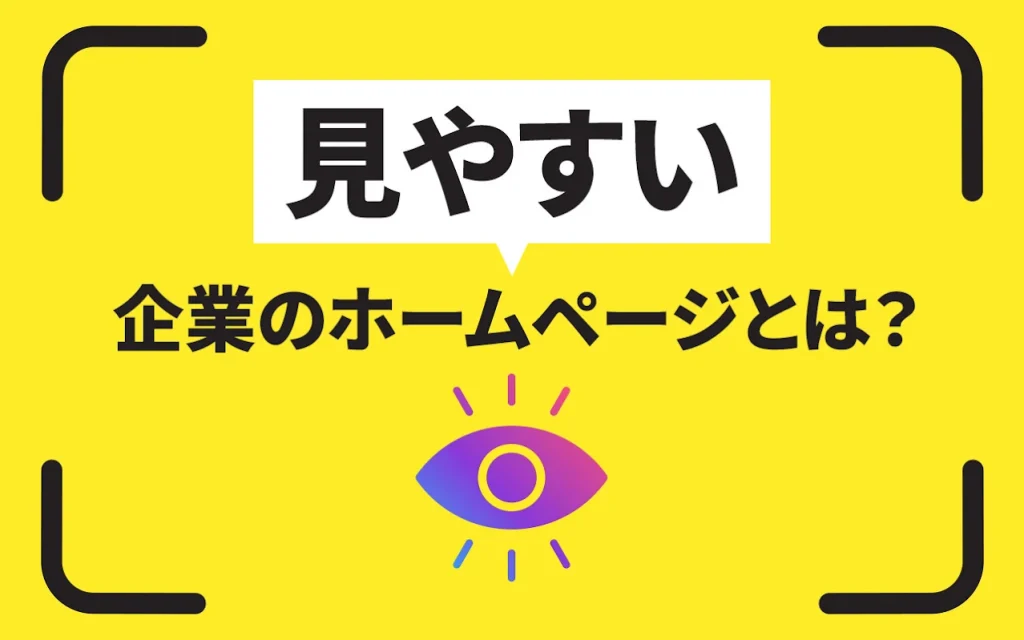
- Web制作
2026/1/31見やすい企業のホームページとは?参考例やポイントを解説!
Recommend オススメ記事
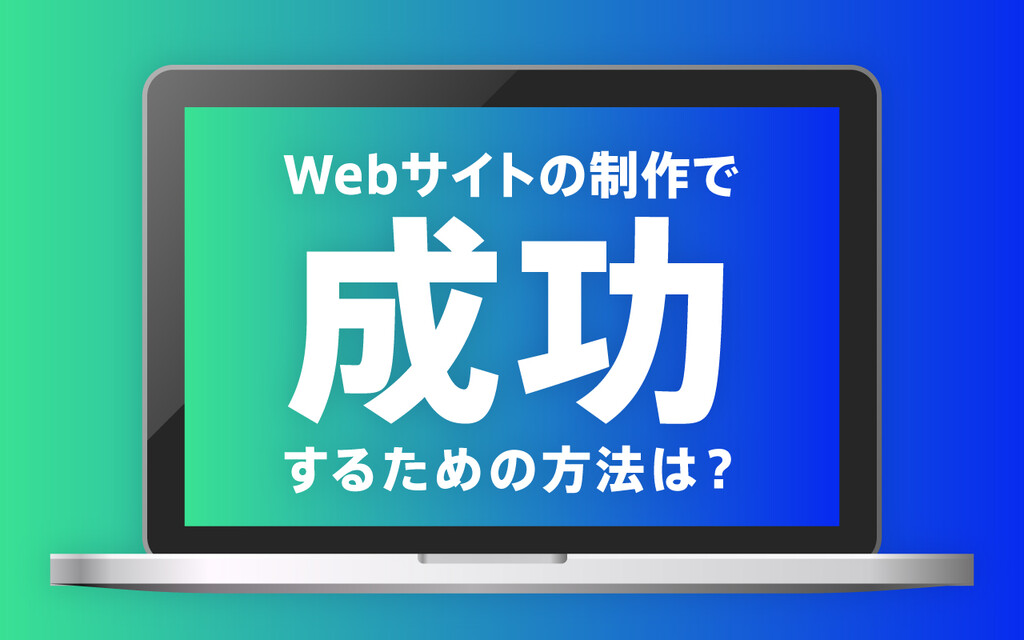
- Web制作
2025/9/19BtoBサイトでおすすめの制作会社15選|BtoBビジネスで成功するには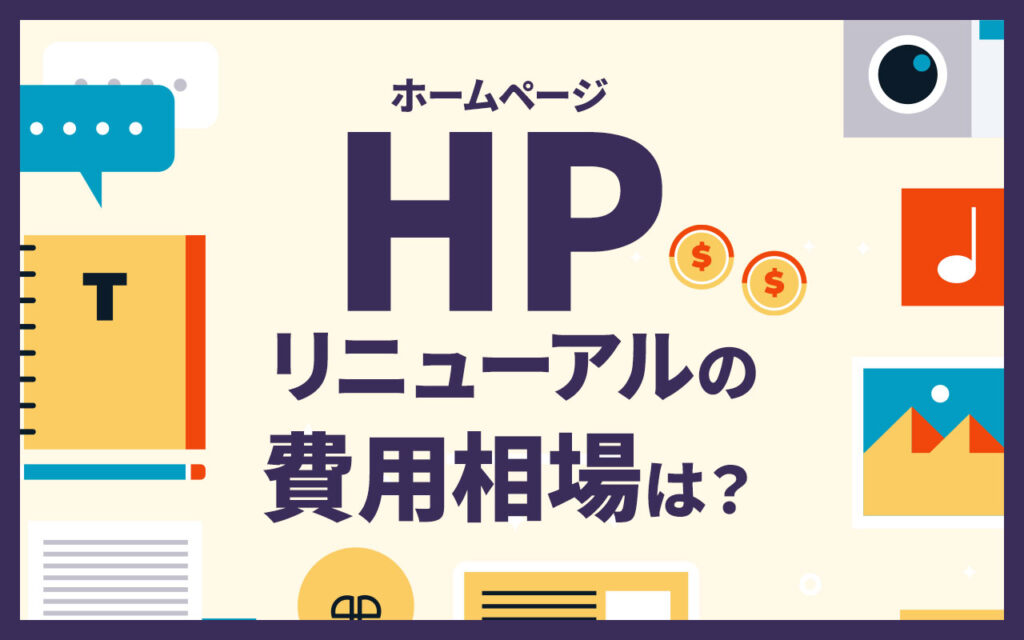
- Web制作
2025/10/2ホームページリニューアルの費用相場は?内訳と安く抑えるポイントを解説
- Web制作
2024/4/28採用サイトの集客方法5選!採用に必要なコンテンツは?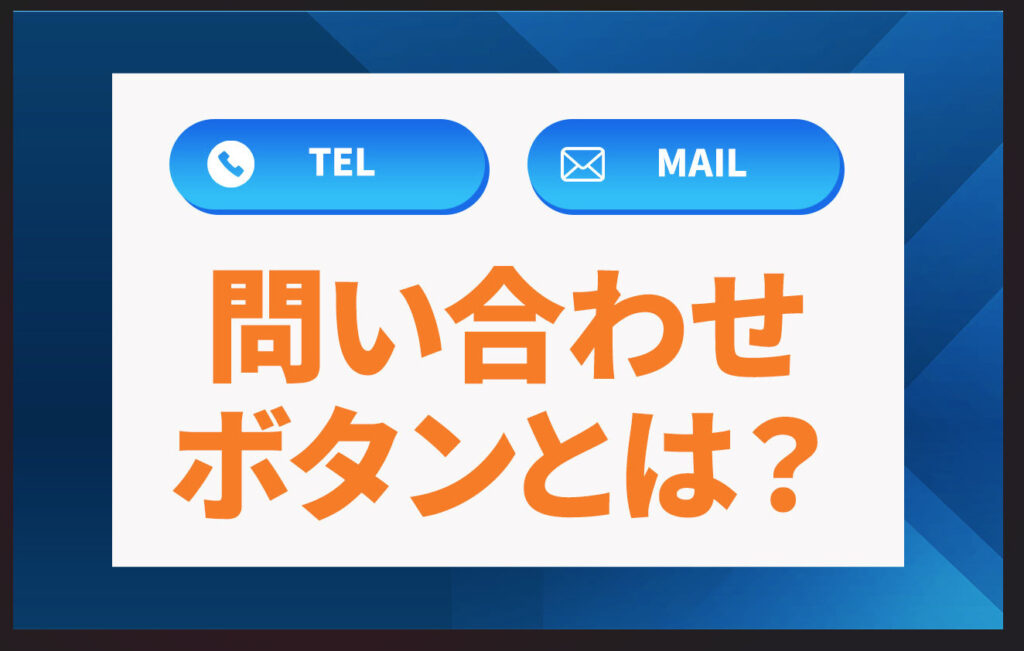
- UX/UIデザイン
2025/11/30問い合わせボタンとは?効果的なデザインと作り方・参考事例10選を徹底解説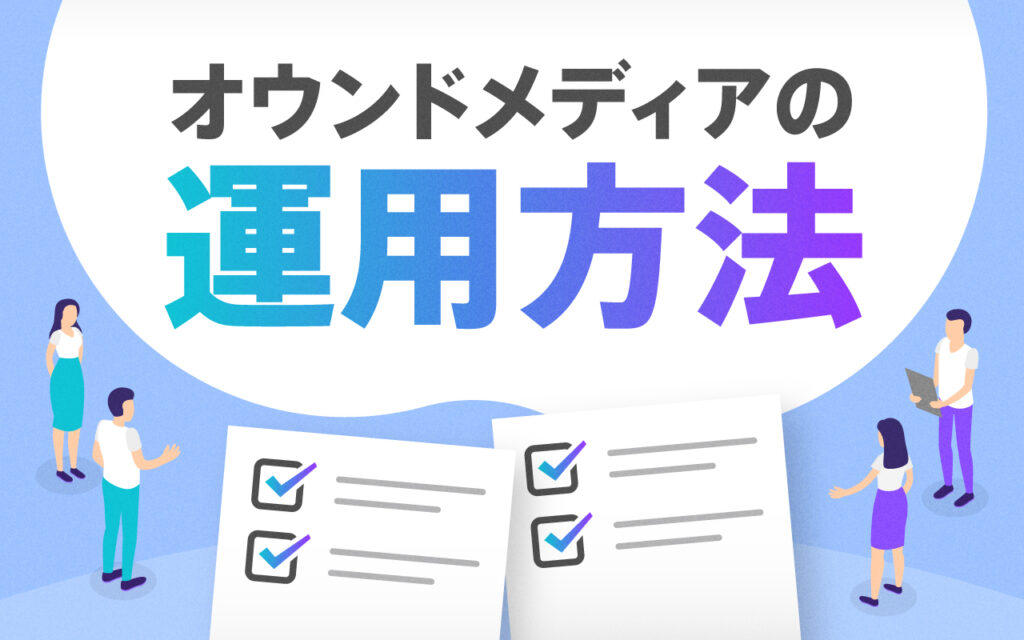
- Web制作
2024/9/19オウンドメディアの運用方法|成果の出るポイントを押さえて運用しよう
- Web制作
2026/1/5ブランドサイト事例15選!デザイン参考例と制作の流れを徹底解説
- Web制作
2025/9/30コーポレートサイトのSEO対策は必要?対策方法や注意点
- Web制作
2024/5/5採用サイトの改善方法とは?課題の見つけ方やリニューアルのポイントについても解説
- コンテンツマーケティング
2024/4/6コンテンツマーケティングの効果的な進め方とは?3つの成功事例も紹介