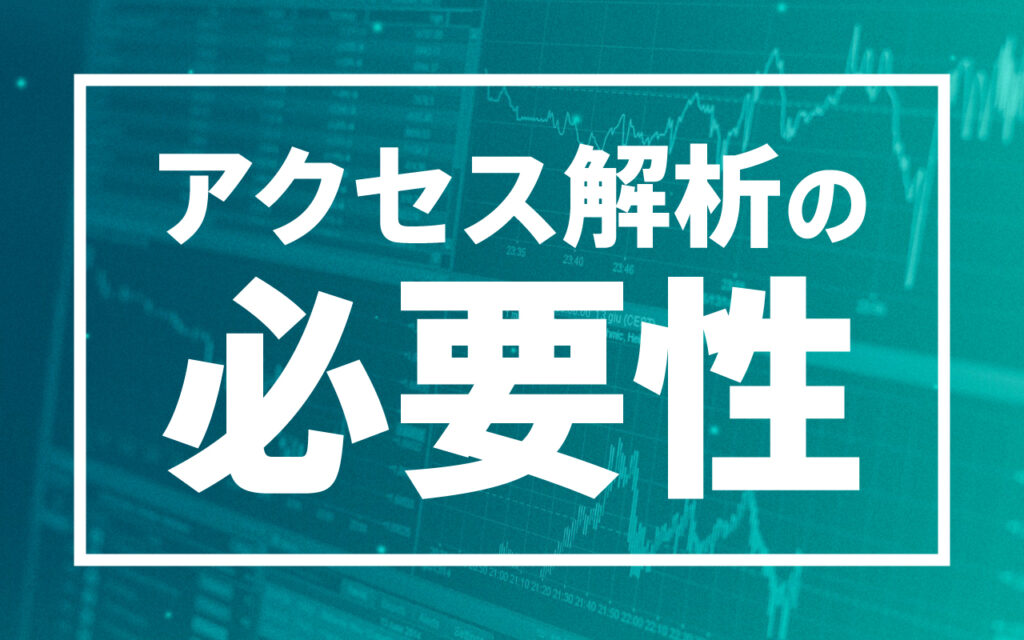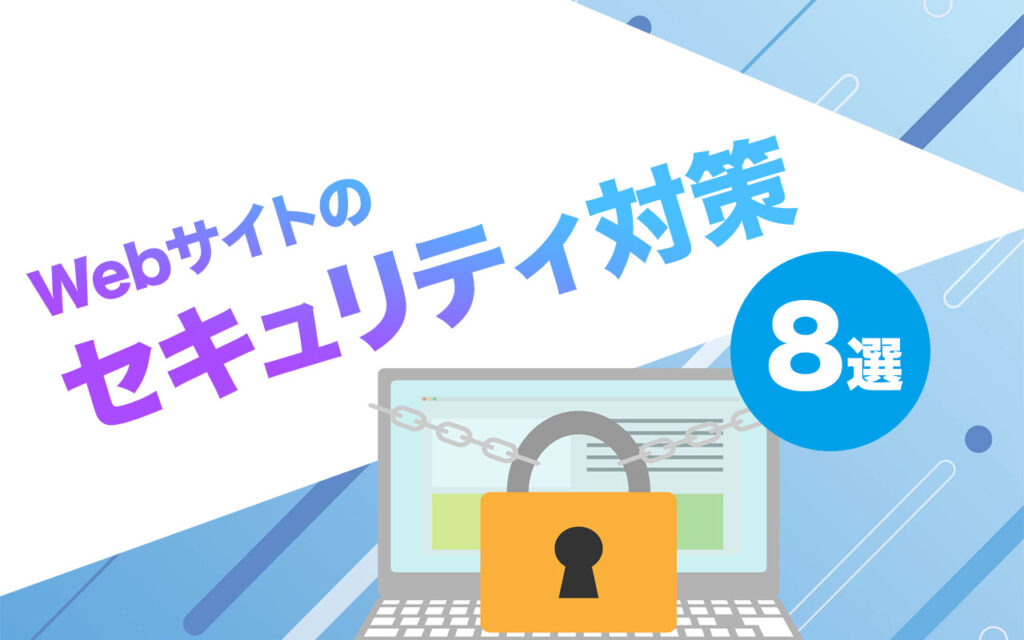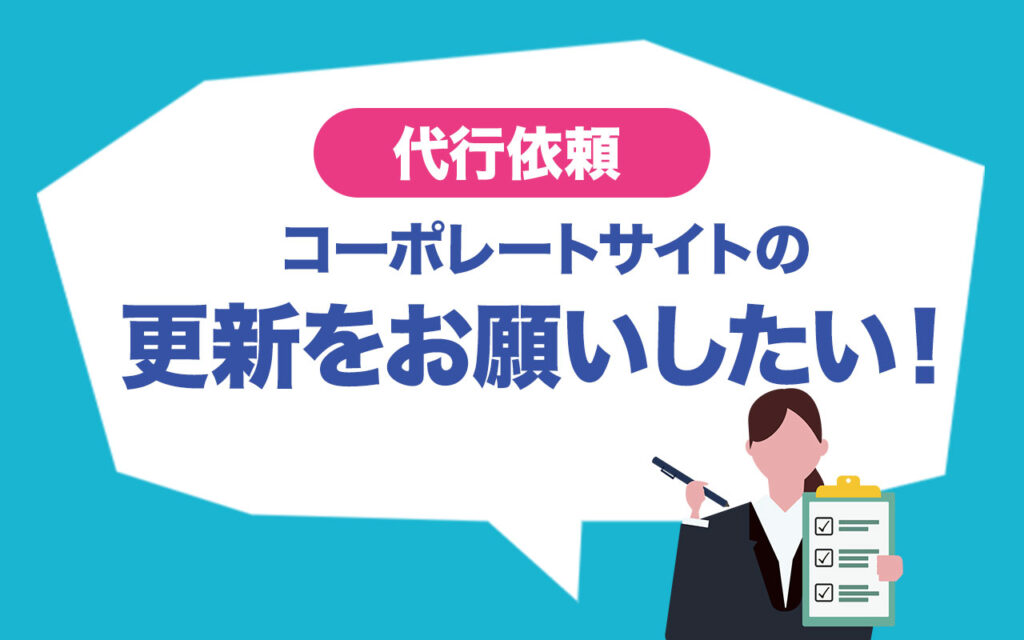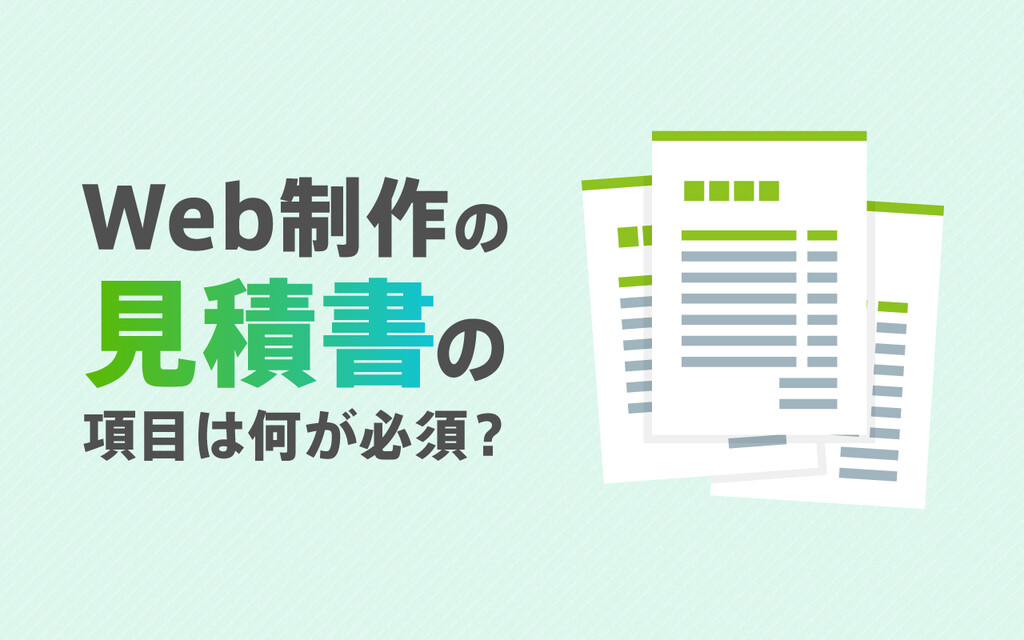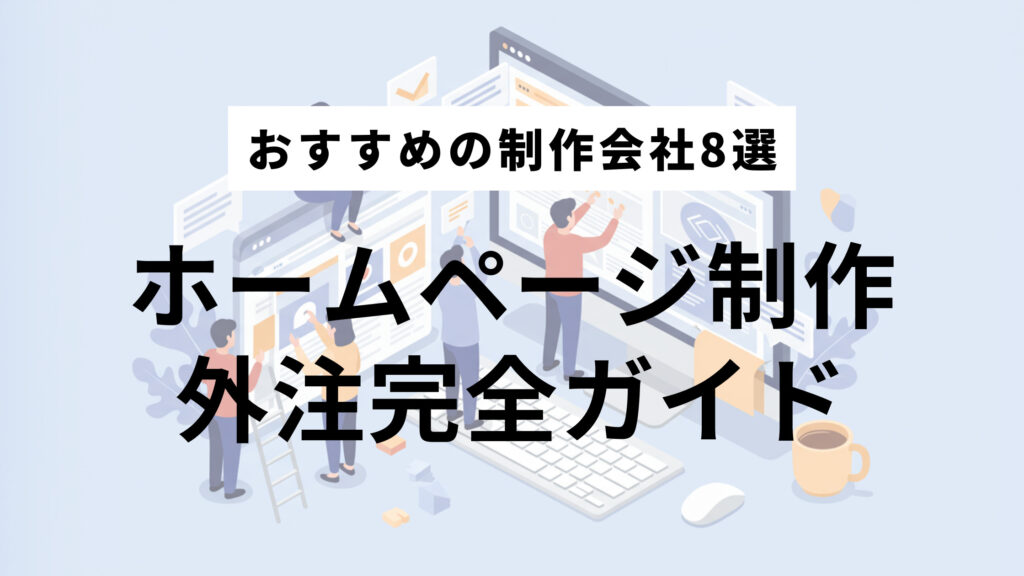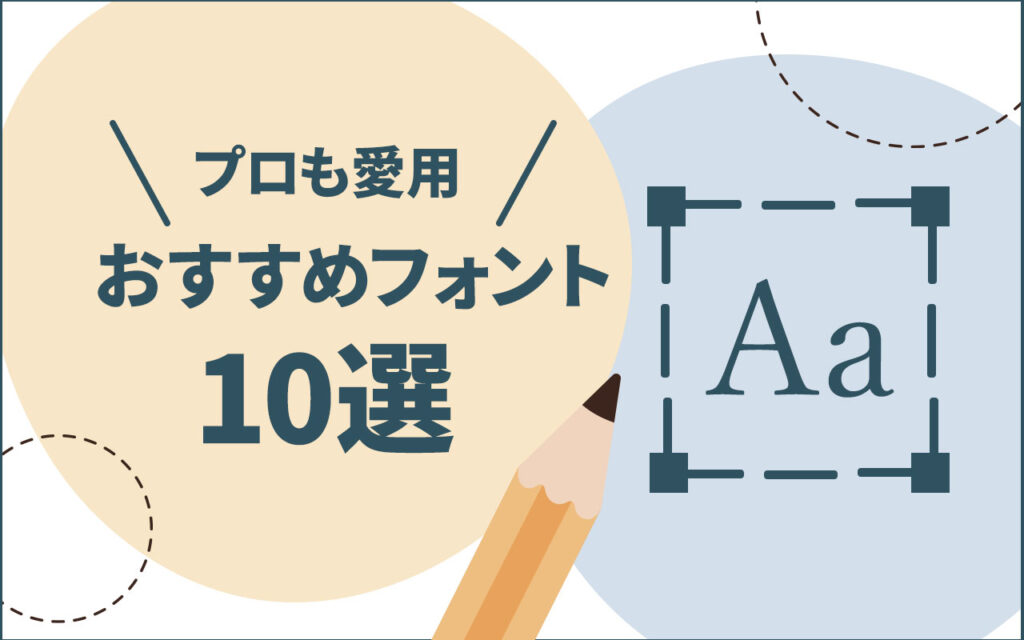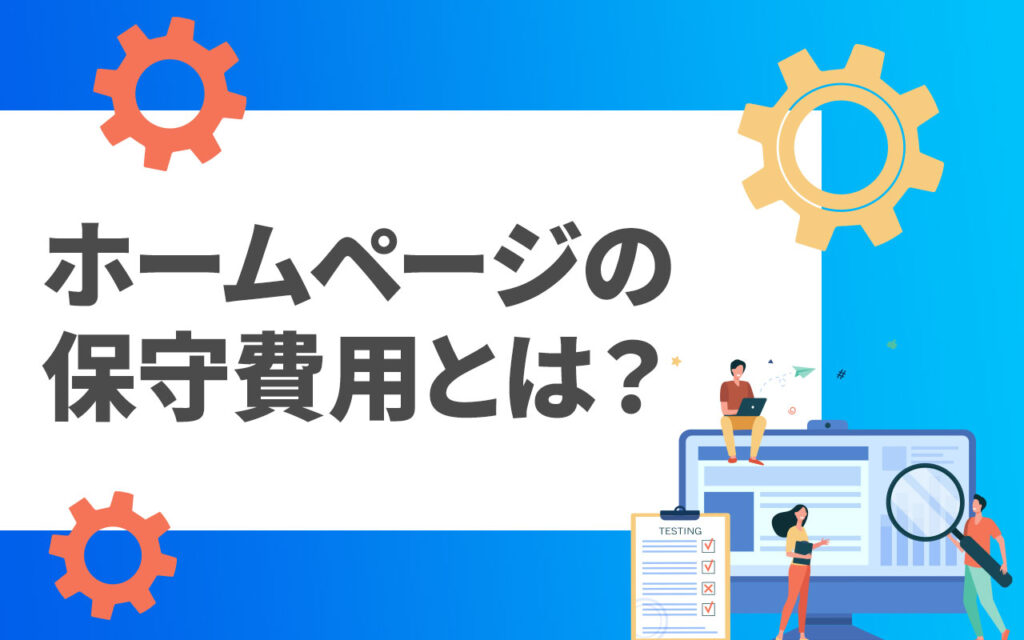
ホームページの保守費用とは?料金内訳や相場、管理における注意点
ホームページの制作や運用には初期費用だけでなく、公開後も継続的な「保守費用」がかかります。
しかし、その内訳や相場、費用が高くなるケースなどは意外と知られておらず、「この金額は妥当なのか?」「もっと安くできないか?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
- 保守運用の必要性を理解したい人
- 保守運用は項目によってかかる費用を知りたい人
- ホームページ運用を外注するメリット・デメリットを知りたい人
本記事では、月額・年間での保守費用の目安をはじめ、内訳、費用が高くなる原因、外注時の選び方、コストを見直す方法までを、わかりやすく解説します。自社で対応する場合と外注する場合の違いも紹介しますので、保守体制の見直しを検討している方もぜひ参考にしてください。
THINkBALでは、ホームページ制作後の保守・運用も含めた一貫対応が可能です。更新対応やセキュリティ対策、改善レポートの提供まで幅広く対応していますので、運用体制にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
データ分析、UX/UI設計に基づく戦略とデザインで伝えたい価値を伝わるカタチに。
ビジネス成果に貢献するホームページの制作・保守運用を提供します。
- ホームページの保守運用とは何をする?費用をかける必要性も紹介
- ホームページ保守費用の相場|月額・年間で平均どれくらいかかる?
- ホームページ保守費用に含まれる主な内訳とその目的
- ホームページ保守費用が高くなるケースとその理由
- 格安のホームページ保守費用サービスを利用する際の注意点
- 自社で対応する場合のホームページ保守費用と必要なスキル
- 外注する場合のホームページ保守費用の選び方と比較ポイント
- ホームページ保守運用まで一貫して依頼をご検討中の方はTHINkBALへご相談ください
- ホームページ保守費用を見直してコストを削減する方法
- まとめ:ホームページ保守費用の相場と内訳を理解して適正価格で運用しよう
ホームページの保守運用とは何をする?費用をかける必要性も紹介
ホームページの保守運用とは、公開後のサイトを安全かつ正常に維持するためにおこなう管理業務全般を指します。
主な業務内容は、以下のとおりです。
- サーバーやドメインの管理
- SSL証明書の更新
- WordPressなどCMSのアップデート
- セキュリティ対策
- バックアップ
- 復旧対応 など
また、文章や画像の修正といった日々の更新作業を代行するケースもあります。これらを怠ると、サイトの不具合やセキュリティ侵害、最悪の場合サイト停止といったトラブルにつながります。
信頼性やユーザー満足度を維持するためにも、保守には費用をかけて外注する価値があるといえるでしょう。
ホームページ保守費用の相場|月額・年間で平均どれくらいかかる?
ホームページ保守費用の相場をサイトの種類別にまとめました。
| サイトの種類 | 月額保守費用の相場 | 年額換算 | 主な保守内容 |
| 個人サイト・小規模事業者向けサイト | 5,000円〜10,000円 | 60,000円〜120,000円 | ・ドメイン・サーバー管理・CMS・プラグイン更新・簡単なテキスト修正 |
| 中小企業のコーポレートサイト | 10,000円〜30,000円 | 120,000円〜360,000円 | ・サーバー・ドメイン管理]・CMS更新・バックアップ・月数回の更新作業]・セキュリティ対策・障害対応 |
| ECサイト | 30,000円〜100,000円以上 | 360,000円〜1,200,000円 | ・商品登録・在庫管理サポート・決済・外部連携管理・高頻度の更新対応・セキュリティ強化・24時間対応 |
| 大規模メディアサイト・情報ポータル系 | 50,000円〜150,000円以上 | 600,000円〜1,800,000円 | ・大量コンテンツの更新支援・サーバー負荷対策・パフォーマンス最適化・データベース保守・分析対応 |
個人サイト・小規模サイト|月額5,000円〜1万円程度
個人や小規模事業者が運営するホームページであれば、保守費用の相場は月額5,000円〜1万円程度が一般的です。これは、ページ数が少なく更新頻度も高くないケースが多いため、保守作業の内容が限定的で済むからです。
この価格帯では、サーバー・ドメインの契約管理、簡単なテキスト修正、CMSやプラグインのアップデートなど、基本的な運用管理が含まれることが多いです。安価なプランでは「更新作業は別料金」となっている場合もあるため、契約前に対応範囲をよく確認することが重要です。
また、サポート対応時間が平日のみ、メールのみなど制限されていることもあります。小規模サイトの場合、必要最低限の保守でも十分なことが多いため、費用と内容のバランスを見極めましょう。
中小企業サイト|月額1〜3万円
中小企業のコーポレートサイトや採用サイトなどでは、ページ数が多く、定期的な情報更新も必要になるため、保守費用は月額1万〜3万円程度が相場です。
この価格帯では、サーバー・ドメイン管理やCMS更新に加え、月数回のテキスト・画像修正、セキュリティ対応、バックアップなどを包括的にカバーすることが多いです。また、障害時の復旧対応が含まれているかどうかも大きなポイントになります。
Webサイトが営業活動の一部となっている中小企業にとって、安定した運用体制は重要であり、保守に一定の投資をおこなう企業が増えています。
ただし、会社によって対応範囲やサービス内容が異なるため、料金だけでなく「何をやってくれるのか」を明確に確認することが大切です。
ECサイト・大規模サイト|月額5万円以上
ECサイトや大規模なメディアサイトでは、扱う情報量やシステムの複雑さにより、保守作業も多岐にわたります。そのため、月額5万円〜10万円以上の費用がかかるケースも珍しくありません。
商品の追加・在庫管理・注文確認などの運用支援や、定期的なUI改善、広告タグの管理、SEO対応、セキュリティ強化など、専門性の高い保守が求められるためです。
また、ECサイトではトラブル対応のスピードが売上に直結するため、24時間対応や即時対応が含まれるプランもあります。
大規模サイトの保守は「売上や成果を守るための投資」と考え、料金だけでなくサポート体制や実績も重視する必要があります。
内部リンク
ホームページ保守費用に含まれる主な内訳とその目的

ホームページの保守運用で発生する費用には、以下のものがあります。
- ドメイン・サーバー管理
- SSL証明書更新・セキュリティ対策
- CMSやプラグインのアップデート
- テキスト・画像の修正対応
- 障害時の復旧・バックアップ
- アクセス解析・改善レポート
ドメイン・サーバー管理費:安定運用のための基盤
ドメインとサーバーはホームページの運用における基盤部分です。ドメインは「住所」、サーバーは「土地」のようなもので、これらがなければWebサイトは表示されません。保守費用の中には、これらの契約更新や設定、動作監視などが含まれる場合があります。
たとえば、サーバーの使用量が増えて表示速度が遅くなったり、ドメインの更新を忘れてサイトが非表示になるといったトラブルを未然に防ぐために、日々の管理が必要です。
これを外注することで、契約忘れやエラー発生時にも対応してもらえる安心感があります。また、サーバー移転や設定変更といった技術的な作業も含まれるケースがあるため、専門的な知識を持つ外部業者に任せることは、運用リスクの軽減にもつながります。
SSL証明書更新・セキュリティ対策:安全な通信を確保するため
SSL証明書は、Webサイトとユーザー間の通信を暗号化し、個人情報の漏えいを防ぐために不可欠なものです。特にお問い合わせフォームやログイン機能を持つサイトでは、SSL未対応だと警告表示が出てしまい、信頼を大きく損ないます。
保守費用には、SSL証明書の取得・更新の手続きだけでなく、有効期限の管理やトラブル時の再設定なども含まれることがあります。また、Webサイトは常にセキュリティ上のリスクにさらされており、WordPressや各種プラグインの脆弱性を狙った攻撃も増加しています。
そのため、定期的な脆弱性チェックや、不正アクセス防止設定(WAF導入など)も含めた総合的なセキュリティ対策を、保守契約に含めておくことが重要です。
CMSやプラグインのアップデート:脆弱性を防ぎ正常に動作させるため
WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)は便利な反面、定期的なアップデートが必要です。アップデートを怠ると、セキュリティホールが放置され、外部からの攻撃やサイトの改ざんといったリスクが高まります。
保守契約の中には、CMS本体の更新、使用中のプラグインのアップデート、テーマのバージョン管理などが含まれることが一般的です。これらはボタン一つでできる作業に見えますが、更新によりレイアウトが崩れたり、プラグイン同士の競合が発生することもあるため、慎重な対応が求められます。
外注先がこれらを事前にテスト環境で確認した上で実施してくれる場合もあり、安定したサイト運営のためには、CMS管理も保守の重要な一部となります。
テキスト・画像の修正対応:最新情報を保ちユーザー満足度を高めるため
保守契約には、ホームページ内のテキストや画像の軽微な修正作業が含まれることが一般的です。たとえば、営業時間や住所の変更、スタッフの追加、キャンペーン情報の差し替えなど、細かな更新は多くのサイトで定期的に発生します。
これらの更新を放置すると、古い情報が表示されたままとなり、ユーザーの不信感につながる恐れがあります。最新の情報を正確に掲載し続けることは、サイトの信頼性とユーザー満足度の維持に直結します。
保守範囲には「月に○回まで無料修正可」など制限がある場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
また、更新頻度が高い業種(飲食店・美容院など)では、この更新対応の品質とスピードが顧客体験に大きく影響します。
障害時の復旧・バックアップ:万が一のトラブル時に迅速に復旧するため
万が一のサーバー障害や表示不具合が発生した際、迅速に復旧対応できるかどうかは保守体制に大きく依存します。
保守契約には、エラー発生時の原因調査・復旧対応、必要に応じた技術的サポートが含まれることがあり、企業にとって非常に重要な項目です。
また、日々の自動バックアップの取得・管理も多くの保守プランに組み込まれており、誤ってデータを削除してしまった場合にも、すぐに元に戻せる体制が整っていれば安心です。特にWordPressなどはテーマやプラグインの競合により突然不具合が起こることもあるため、復旧体制が整っているかは契約時に必ず確認しましょう。
バックアップの取得頻度や保管期間もチェックポイントです。
アクセス解析・改善レポート:サイトの課題を可視化し改善につなげるため
アクセス解析や改善レポートの作成は、単にサイトを維持するだけでなく、成果を上げるために欠かせない保守業務の一つです。
Googleアナリティクスやサーチコンソールなどのツールを用いて、訪問者数や直帰率、離脱率、人気ページなどを分析し、どこに課題があるのかを「見える化」します。
保守契約にこのレポート作成が含まれている場合、毎月もしくは四半期ごとに、改善点や提案を含めたレポートが提出されることが一般的です。
特にECサイトや集客目的のサイトでは、アクセス解析から得た情報をもとに、サイト構成や導線、コンテンツの見直しが売上に直結します。
単なる管理ではなく、継続的な改善を目指すための保守として、アクセス解析は大きな価値を持っています。
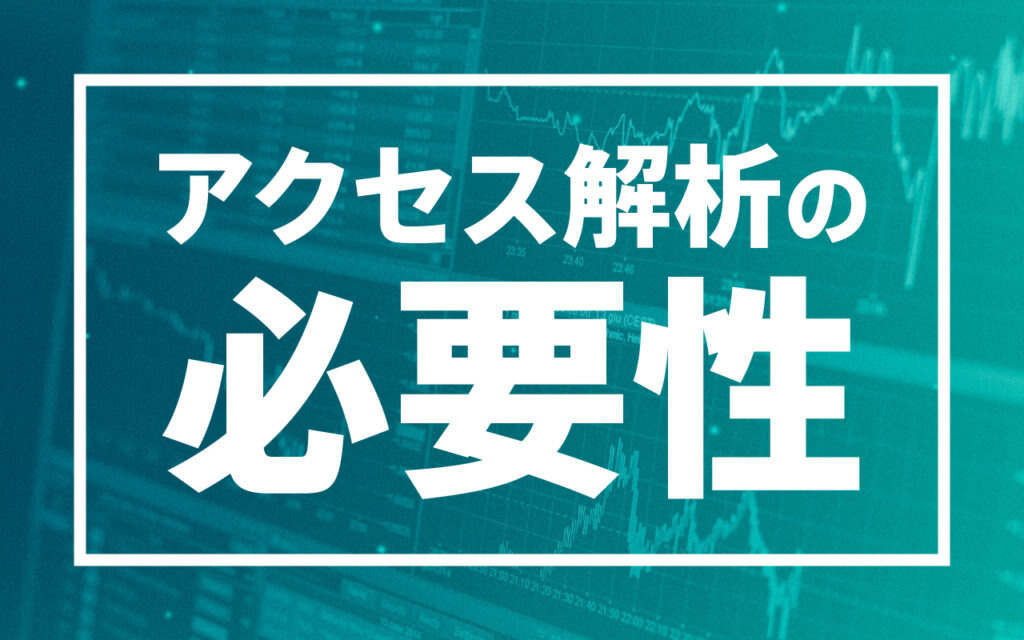
ホームページ保守費用が高くなるケースとその理由
ホームページ保守費用が高くなるケースとその理由は、以下の通りです。
- 頻繁な更新・カスタマイズがあるから
- 24時間365日対応などサポート体制が手厚いから
- セキュリティ対策に専門知識が必要だから
- 外部ツールとの連携や改修が必要だから
頻繁な更新・カスタマイズがあるから
保守費用が高額になる一因として、「サイト更新の頻度の高さ」が挙げられます。
たとえば、毎週キャンペーン情報を差し替える、ニュースやブログを頻繁に投稿する、掲載内容の修正依頼が多いといった場合、それに対応するための工数が大きくなります。
特にECサイトやイベント情報を扱うメディアでは、商品の入れ替えや掲載情報の更新が日常的に発生するため、作業ボリュームが膨らみがちです。こうした継続的な更新対応を外注先に任せる場合、人件費・確認工数・反映スピードの担保などを含めて月額費用が高く設定される傾向があります。
契約前に「月何回まで対応可能か」や「超過時の追加費用」などを明確にしておくことも重要です。
24時間365日対応などサポート体制が手厚いから
保守契約に「24時間365日のサポート対応」が含まれている場合、費用は通常よりも高額になります。
特にECサイトや医療機関、予約サイトなどでは、深夜や休日にもアクセスが集中しやすく、万が一の障害時には即座に対応できる体制が求められます。このような体制を整えるには、常時監視やシフト勤務体制を含む人的リソースが必要になり、保守会社側にも相応のコストがかかるため、料金に反映されます。
また、サーバーダウンや不正アクセス、注文不具合といったトラブル発生時に即対応できる環境は、売上やブランドイメージを守る上で非常に価値があります。
その分、費用が高くなるのはやむを得ない部分であり、サイトの重要性に応じて検討すべき項目です。
セキュリティ対策に専門知識が必要だから
保守費用が高くなる大きな要因のひとつが、専門的なセキュリティ対策の実施です。
サイトが不正アクセスや情報漏えいのリスクに晒されないよう、WAF(Web Application Firewall)の設定、二段階認証、IP制限、脆弱性診断など、専門的な知識が求められる作業が含まれます。
特に、会員情報を扱うサイトや、問い合わせフォームで個人情報を収集する企業サイトでは、セキュリティ対策の強化は必須です。
また、CMSやプラグインのアップデートによる不具合対策、サーバー側の設定調整なども一括して任せる場合、保守会社のエンジニアに高いスキルが求められるため、月額費用も上がる傾向にあります。
安全性を最優先するサイトでは、保守の「質」が料金に反映されます。
外部ツールとの連携や改修が必要だから
サイト内で予約システム、在庫管理システム、顧客管理(CRM)やマーケティングオートメーション(MA)ツールなどと連携している場合、保守の手間が大きくなり、費用が高くなる傾向があります。
外部APIとの連携には、仕様変更への追従や障害発生時の調査・復旧対応といった専門対応が発生するため、通常のWeb保守よりも高い技術力が求められます。また、ツールによっては更新や連携先の設定作業が頻繁に発生するケースもあり、これらを保守範囲に含めると費用が大幅に増加することがあります。
さらに、複数の外部サービスを使っている場合は、全体の動作テストや設定確認も必要になるため、保守工数が増える要因になります。システム連携を行っているサイトは、保守体制を強化する前提で見積もりを検討すべきです。
格安のホームページ保守費用サービスを利用する際の注意点
格安のホームページ保守費用サービスを利用する際の注意点は以下のとおりです。
- 契約範囲が狭く「更新作業」が含まれないことがある
- レスポンスが遅く緊急時に対応できない可能性がある
- セキュリティ更新が放置されるリスクがある
- 無料や格安プランには広告表示や制限がある
契約範囲が狭く「更新作業」が含まれないことがある
格安のホームページ保守サービスでは、契約範囲が非常に限定的であるケースが多く、更新作業が含まれていないことも珍しくありません。
たとえば、ドメインやサーバーの契約管理はおこなうものの、テキストや画像の変更といった実務的な更新は「別料金」となっていたり、「月1回まで無料」「軽微な作業のみ」といった制限が設けられていることがあります。
更新作業が別途スポット対応になると、頻度によってはトータルコストが割高になる可能性もあるため注意が必要です。契約前には「どこまでの作業が含まれているか」「どこから追加料金が発生するのか」を明確にしておきましょう。
保守費用の安さだけで判断せず、対応内容を必ず確認することがトラブル回避につながります。
レスポンスが遅く緊急時に対応できない可能性がある
費用を抑えた格安の保守サービスでは、人員体制が最小限であることが多く、問い合わせやトラブル発生時のレスポンスが遅くなる傾向があります。特にサーバーダウンや不正アクセス、フォームの不具合など、すぐに対処しなければ業務や信頼に影響が出るケースでは、対応の遅れが大きな損失につながります。
「メール対応のみ」「営業時間内のみ」「返信までに数日かかる」といった条件が設定されている場合もあり、保守というより“最低限の監視”という位置づけのことも。万が一の際に「すぐ連絡が取れない」「対応は翌営業日」といった状況ではリスクが高まります。
契約前には、対応スピード・受付時間・緊急連絡手段の有無などを必ず確認しておきましょう。
セキュリティ更新が放置されるリスクがある
ホームページのセキュリティ対策は、定期的なCMSやプラグインのアップデートが不可欠ですが、格安の保守サービスではこれらが対応外になっていたり、十分におこなわれていないケースがあります。
WordPressなどを使っている場合、脆弱性が発見されると早急に対応しなければ不正アクセスやデータ漏洩などの重大なトラブルに発展しかねません。サービスが安価であっても、セキュリティ更新が自動化されていない、チェック体制がないといった場合は、放置状態になりリスクが高まります。
特に個人情報や問い合わせフォームを設置しているサイトでは、セキュリティが甘いと信頼を失う原因にもなります。安さを優先するあまり、安全性が犠牲にならないよう十分注意が必要です。
無料や格安プランには広告表示や制限がある
特に無料や極端に安価な保守・運用サービスでは、サービス側の都合によって広告が自動表示されたり、機能に大きな制限があることがあります。
たとえば、共用サーバーによる表示速度の低下、独自ドメインが使えない、アクセス数に上限がある、ファイル容量が制限されているなど、運用に支障をきたす可能性も。広告表示があると、ビジネスサイトとしての信頼性を損なうことにもなりかねません。
また、サポート内容がテンプレート対応のみ、マニュアル提供のみといったケースも見られます。安さの裏にある制限や条件を正しく理解し、自社の目的に合致しているかをよく確認することが、後悔しない保守契約のポイントになります。
年間契約は割安になるが契約内容が不利になる
格安サービスの中には、年間契約を前提に割引を提示しているケースがあります。確かに長期契約は1ヶ月あたりの料金が抑えられるため魅力的に見えますが、内容をよく確認しないと後悔することもあります。
たとえば、月1回までしか更新できない、緊急対応は別料金、途中解約に高額な違約金が発生するなど、契約内容がユーザーに不利な条件になっていることも。格安だからこそ、対応の柔軟性や解約条件、対応範囲などを細かくチェックする必要があります。
年間契約を結ぶ前には、数ヶ月のトライアル期間やスポット契約を利用し、サービスの質や対応スピードを実際に確認してから判断するのがおすすめです。価格だけでなく、サービスの実態を見る目が求められます。
自社で対応する場合のホームページ保守費用と必要なスキル

自社で対応する場合のホームページ保守費用は、ドメイン・サーバー契約のみなら月1,000円前後から実施できます。更新頻度が低ければ自社運用の方がコストを抑えられることが多いです。
また、自社で対応する際に必要なスキルは以下の通りです。
- HTMLやWordPressなどの基本知識
- ミスやサーバーダウン時の復旧対応
HTMLやWordPressなどの基本知識
自社でホームページ保守をおこなうには、ある程度のWebの基礎知識が求められます。たとえば、WordPressを使用している場合、テーマやプラグインの更新、エラー時の対処、セキュリティ設定などに対応する必要があります。
HTMLやCSSの基礎的な理解があれば、テキストや画像の差し替えも自力で可能ですが、ミスをすればレイアウト崩れや表示不具合が起きるリスクもあります。
また、ドメインやサーバーの管理には専門用語や手続きも関わるため、初めて対応する人にはハードルが高く感じられるかもしれません。
保守を内製化することでコストは抑えられますが、知識や経験が不足していると、結局外注よりも時間と手間がかかってしまうケースも少なくありません。
ミスやサーバーダウン時の復旧対応
自社でホームページを管理している場合、更新作業や設定変更によって不具合が起きた際は、自力で原因を特定し、復旧する必要があります。
たとえば、WordPressのプラグインを誤って更新してしまいサイトが真っ白になる、FTP操作で必要なファイルを削除してしまうといったケースは、意外とよくあります。
こうしたトラブルが起きた場合、復旧には技術的な知識と冷静な対応が求められます。また、サーバー側のトラブルでサイトが表示されなくなった場合も、自らサポート窓口に連絡し、原因を調査する手間が発生します。
外注していればすぐに対応してもらえるような問題でも、自社管理では「すべて自己責任」であることを十分に理解しておく必要があります。
外注する場合のホームページ保守費用の選び方と比較ポイント
外注する場合のホームページ保守費用の選び方のポイントは、以下の通りです。
- 対応範囲とサービス内容を確認する
- 更新対応の頻度と制限回数を確認する
- 緊急時のサポート体制を確認する
- 月額・年間費用とその内訳を確認する
- 保守実績とこれまでの運用事例を確認する
- 依頼先が制作会社と保守専門会社のどちらかを確認する
- 契約期間や解約条件を確認する
対応範囲とサービス内容を確認する
保守費用を外注する際は、料金だけでなく「どこまで対応してくれるか」を確認することが最も重要です。たとえば、サーバーやドメインの管理だけでなく、更新作業やセキュリティ対策、障害時の復旧対応まで含まれているかは会社ごとに異なります。
中には、月額料金が安くても、更新作業が別料金だったり、障害対応が有料オプションというケースもあります。契約前には「対応可能な作業範囲」と「回数制限」「対応時間帯」など、具体的なサービス内容を明確にし、自社のニーズに合っているかどうかを見極める必要があります。
サービス一覧や契約書、プラン比較表などで、どの作業が含まれていて、何が別料金なのかを事前に確認しましょう。
更新対応の頻度と制限回数を確認する
多くの保守契約では、更新作業の対応回数に制限があります。「月◯回まで無料」「それ以降は1回あたり◯円」などの条件が設定されているケースが一般的です。
たとえば、頻繁にお知らせやキャンペーン情報を差し替える必要がある場合、回数制限があると追加費用がかさむことがあります。また、制限があっても「軽微な修正」の範囲内であればカウントされないような独自ルールを設けている業者もあるため、曖昧な点は事前に確認しておくことが重要です。
更新作業の頻度が多い業種や、社内でWeb作業に時間を割けない企業では、無制限プランや柔軟に対応してくれる保守会社を選ぶと、後々のコスト面や手間が軽減されます。
緊急時のサポート体制を確認する
サーバーダウンやサイトの表示エラーなど、ホームページのトラブルは突然発生します。そのため、保守を外注する場合は「緊急時の対応体制」がどのようになっているかを必ず確認しましょう。
たとえば、平日営業時間内のみの対応なのか、休日や深夜もサポートが受けられるのか、障害時は電話対応が可能かなど、サポートの時間帯と連絡手段は重要な比較ポイントです。ビジネスの性質によっては、24時間体制の保守が必要になることもあります。
また、障害時の優先対応や復旧までの目安時間(SLA)が明確に決められている業者であれば、安心して任せられるでしょう。表面的な費用だけでなく、トラブル発生時の対応力も必ず評価すべきポイントです。
月額・年間費用とその内訳を確認する
保守費用は「月額いくら」という金額だけでなく、その中にどの作業が含まれているかの「内訳」を確認することが重要です。
料金が安く見えても、更新作業や障害対応が別料金になっていると、実際の支払いは予想以上に膨らむこともあります。また、年間契約で割引がある場合でも、解約時の違約金や条件にも注意が必要です。
見積もりを依頼する際は、「基本プランに含まれる作業」「オプションで追加できる作業」「スポット対応の料金」などを細かく書面で確認し、複数社で比較検討しましょう。さらに、保守対象のページ数や更新頻度によってプランが変動する場合もあるため、自社サイトの運用状況に合った料金体系を選ぶことが大切です。
保守実績とこれまでの運用事例を確認する
保守会社を選ぶ際には、料金やサービス内容だけでなく「これまでどのようなサイトを保守してきたか」という実績も重要な判断材料となります。
業種やサイトの規模、使用しているCMSなどが自社と似ている事例があれば、安心して任せられる可能性が高まります。また、長期間同じ会社と契約を継続している実績がある場合、その対応力や信頼性が評価されている証拠ともいえます。
公式サイトに掲載されている実績紹介や導入事例のページ、クライアントの声などを参考にしながら、自社のニーズに合致しているかを確認しましょう。できれば、初回の問い合わせ時に「自社と似たタイプのサイトでの対応経験があるか」を直接聞いてみるのもおすすめです。
依頼先が制作会社と保守専門会社のどちらかを確認する
ホームページの保守は、制作会社にそのまま依頼するケースと、保守専門の会社に切り替えて運用するケースの2パターンがあります。
制作会社に保守も依頼する場合、サイトの構造や設計を熟知しているためスムーズな対応が期待できますが、保守業務をあまり重視していないケースでは対応が遅れることもあります。一方、保守専門会社はトラブル対応や日々の運用をメイン業務としているため、対応スピードや柔軟性に優れている傾向があります。
自社がどのようなサポートを重視するのかに応じて、どちらに依頼すべきかを検討しましょう。予算やサポート体制、業務の重要度によって最適なパートナーが異なります。
契約期間や解約条件を確認する
保守契約を結ぶ前に、必ず確認しておきたいのが「契約期間」と「解約条件」です。
多くの保守サービスは月額制ですが、年間契約が前提となっている場合や、最低契約期間が設定されていることもあります。また、途中解約時に違約金が発生したり、解約の1ヶ月前通知が必要などのルールがあることも珍しくありません。
これらの条件を確認せずに契約を結んでしまうと、思わぬタイミングで費用が発生するリスクがあります。
契約前には、契約書や利用規約をしっかり読み込み、疑問点は必ず事前に質問しましょう。柔軟な契約内容を提示してくれる保守会社を選ぶことで、将来的なトラブルも防ぎやすくなります。
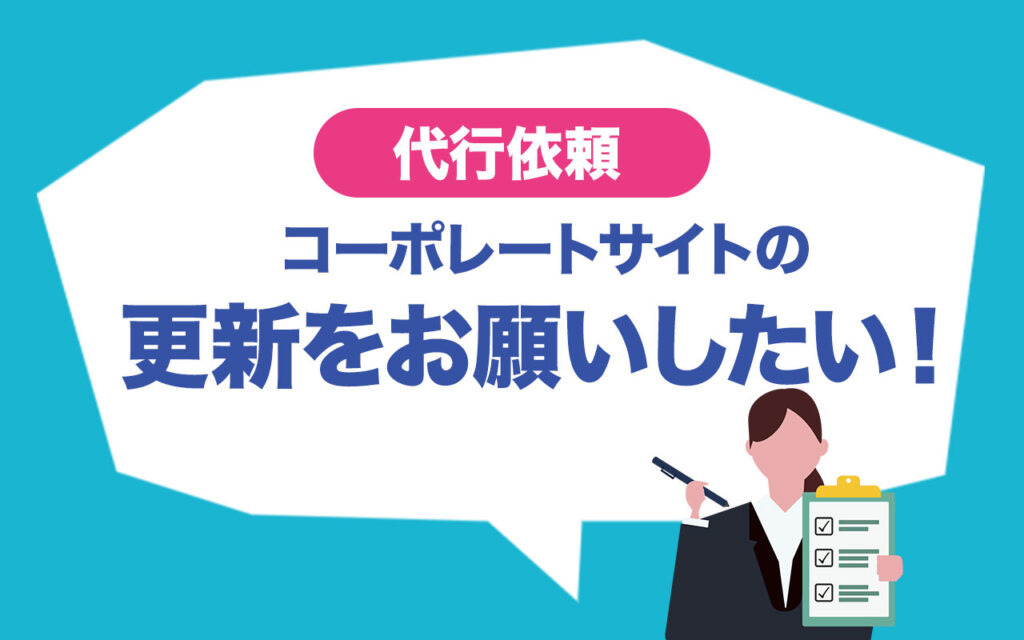
ホームページ保守運用まで一貫して依頼をご検討中の方はTHINkBALへご相談ください

ホームページの保守運用を外注するにあたり、「どこまで対応してくれるのか」「費用に見合うサポートが受けられるのか」と不安を感じている方も多いでしょう。
THINkBALでは、ホームページ制作後の保守・運用も一貫して対応しており、サーバーやドメイン管理、更新作業、セキュリティ対策、障害対応、改善レポートの提供までトータルでサポート可能です。
これまで多数のコーポレートサイト・ECサイト・採用サイトなどを手がけ、業種や規模を問わず幅広い保守実績を積み重ねてきました。「自社に必要な保守内容がわからない」「現在の費用が適正か判断できない」といったお悩みにも丁寧に対応いたします。
保守費用の見直しや、より安心できる外注先をお探しの方は、ぜひ一度THINkBALへご相談ください。
ホームページ保守費用を見直してコストを削減する方法
ホームページ保守費用を見直してコストを削減する方法は、以下の通りです。
- 契約内容を精査して不要なサービスを削る
- 定期更新を減らしてスポット対応に切り替える
- 複数社から見積もりを取り直す
- 一部業務を社内で実施して必要な部分だけ外注する
契約内容を精査して不要なサービスを削る
保守費用を見直す第一歩は、現在契約している保守内容を精査し、実際に使っていないサービスを洗い出すことです。
たとえば、ほとんど更新していないのに毎月更新対応費を支払っている、アクセス解析のレポートを活用していない、障害対応の24時間体制が実は不要、など見直す余地は意外とあります。
定型レポートやサポート内容が自社の実情に合っていないことも多く、その分のコストを削減できる可能性があります。
契約書や見積書を再確認し、「本当に必要なサービス」と「今は不要なサービス」に分けて整理しましょう。保守会社に相談すれば、無理のない範囲でプランの変更や一部オプションの削除に応じてもらえるケースもあります。
定期更新を減らしてスポット対応に切り替える
更新作業が月に1〜2回程度しか発生しないのであれば、定額制の保守契約ではなく、必要なときだけ依頼する「スポット対応型」の契約に切り替えることでコストを大幅に削減できる場合があります。
スポット対応では、更新ごとに作業単価が発生しますが、頻度が少ない場合は月額保守よりもトータルコストを抑えられる可能性が高いです。
ただし、対応スピードやサポート体制は保守契約より限定的になることがあるため、「即日対応が必要かどうか」「月に何回程度更新があるか」などを明確にした上で検討する必要があります。
また、スポット対応を行っている業者をあらかじめ確保しておくことで、必要なときにすぐ依頼できる体制を整えておくと安心です。
複数社から見積もりを取り直す
保守費用が高すぎると感じた場合は、現状の契約内容をもとに複数の保守会社へ見積もりを依頼し、内容と料金を比較してみましょう。同じような保守内容でも、業者によって月額費用や対応範囲、サポート体制には大きな差があります。
特に、過去に制作を依頼した会社にそのまま保守も任せている場合、相場より割高な料金が設定されていることも珍しくありません。比較の際は、「作業の対応範囲」「更新回数の上限」「緊急時の対応」など、各社が提供しているサービス内容を細かく把握し、自社のニーズに最も合ったプランを選びましょう。
見積もり比較を通じて、現在の契約内容が適正かどうかを客観的に判断できます。
一部業務を社内で実施して必要な部分だけ外注する
保守費用を抑えるためには、すべてを外注せず、自社で対応可能な業務を分担する方法も有効です。
たとえば、お知らせやスタッフ紹介のテキスト修正など、簡単な更新作業は社内でおこない、セキュリティ対策やサーバー保守といった専門性の高い作業だけを外注するといった方法です。
最近では、WordPressの管理画面を使えば非エンジニアでもある程度の更新が可能なため、マニュアルを整備して社内で対応できるようにすれば、外注費を抑えられます。
社内対応と外注の「役割分担」を明確にすることで、無駄な費用をかけずに安定した運用が実現できます。初期段階では一部だけ外注して様子を見るのもよいアプローチです。
まとめ:ホームページ保守費用の相場と内訳を理解して適正価格で運用しよう
ホームページの保守費用は、作業範囲・更新頻度・サポート体制などによって大きく変わります。
相場だけに注目するのではなく、「どの作業が必要で、どれが不要か」「自社で対応できる範囲はあるか」といった視点で精査することで、無駄なコストを抑えつつ、必要なサポートを確保することが可能です。
本記事を通じて、保守費用の内訳や選び方、外注と自社対応の違い、コスト削減のポイントについて理解を深めていただけたなら幸いです。最終的には、安心して任せられるパートナー選びが、長期的なWeb運用の成否を左右します。
THINkBALでは、ホームページ制作から保守・運用まで一貫してサポート可能です。貴社に最適な保守プランを提案し、安心・安全かつ成果につながるWeb運用をご支援します。まずはお気軽にご相談ください。
お客様の目的とビジネスの成果に合わせたホームページの保守・運用

毎月支払っている保守・運用費用が無駄になっていませんか?
- 毎月分析・解析レポートを作成してほしい
- いざというトラブルに備えておきたい
- 管理・保守運用を兼ねてSEO対策もお願いしたい
ホームページの保守・運用なら
THINkBALにお任せください
Works
事例紹介

Relation 関連記事

- Web制作
2025/11/30【2025年版】採用サイト制作会社おすすめ15選|失敗しない選び方と成果を出すパートナー探し完全ガイド
- Web制作
2024/6/23人材・転職サイトで製作会社を選ぶには?ポイントやおすすめ会社を紹介
- Web制作
2024/11/9不動産業界のサイト制作方法は?ポイントや費用、制作会社の選び方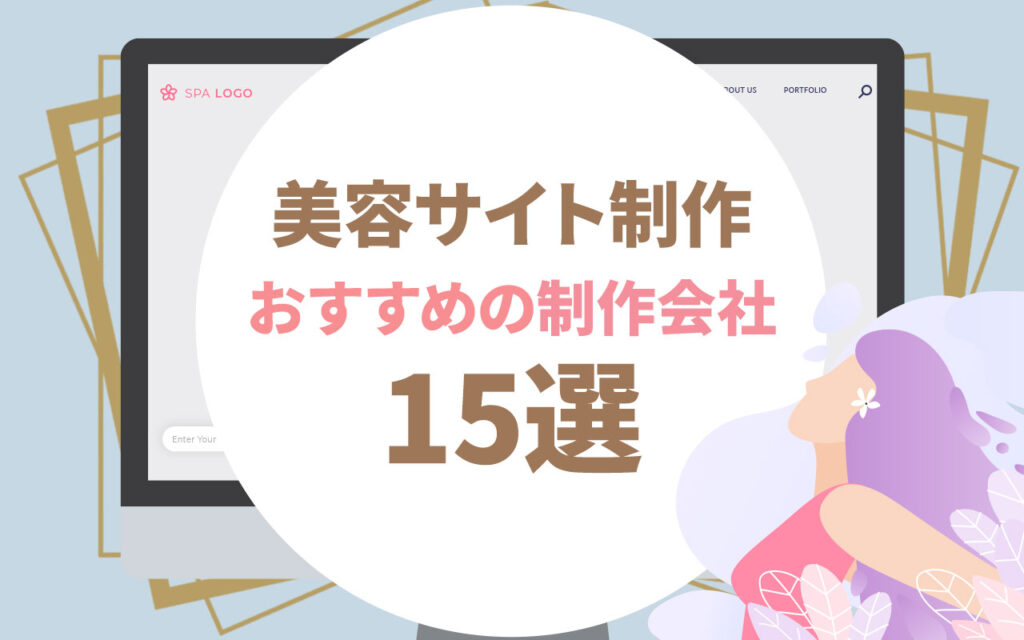
- Web制作
2024/6/17美容系サイトでおすすめの制作会社15選|参考になるサイトデザインも紹介!
- Web制作
2023/11/307種類に分類!Webサイトの制作はどんな会社に依頼するのがおすすめ?
- Web制作
2024/11/21おすすめのWebサイト制作の代行会社5社!選び方のポイントも紹介
What's New 新着情報

- Web制作
2026/1/5ヘッダーの作り方完全版!HTML・CSS・スマホアプリで作る手順を解説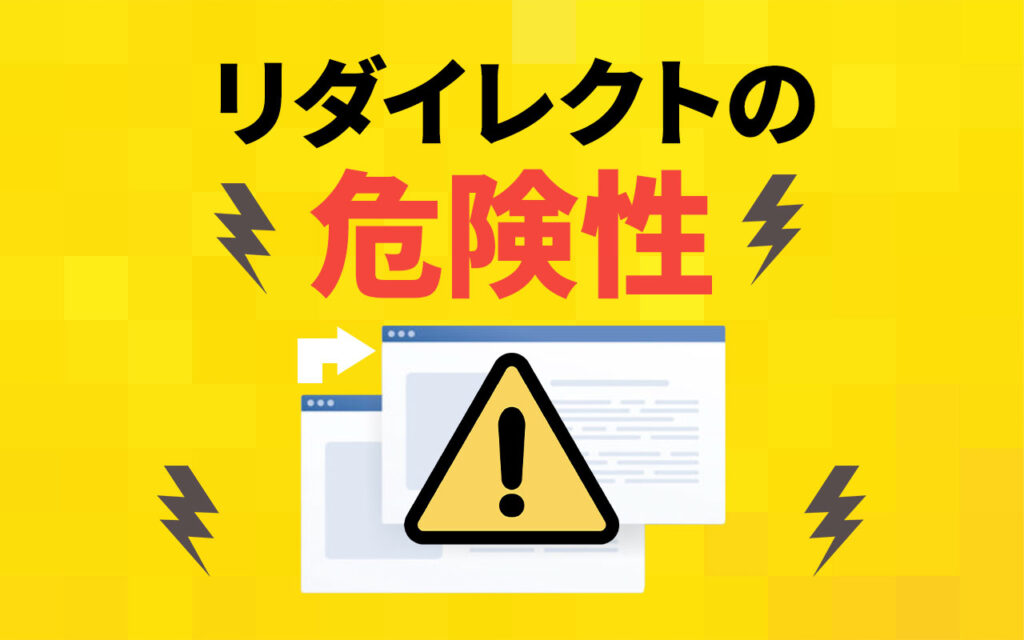
- Web制作
2026/1/5リダイレクトの危険性│ユーザーやSEOにおけるリスクや注意点について解説
- Web制作
2026/1/5グローバルメニューとは?優れたデザイン事例とクリックされる設置のコツ
- Web制作
2026/1/5初心者でも分かるStudioの使い方|プロが教える設定手順と事例
- Web制作
2026/1/5ホームページ公開までの流れを5ステップで解説!公開前後でやるべきチェックリストも紹介
- Web制作
2026/1/5ブランドサイト事例15選!デザイン参考例と制作の流れを徹底解説
Recommend オススメ記事
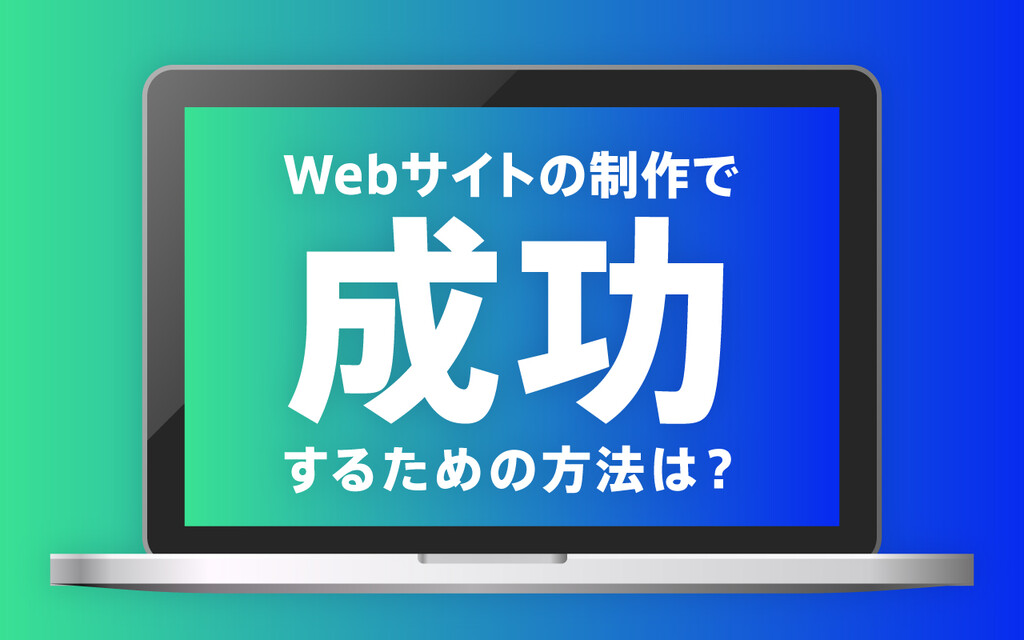
- Web制作
2025/9/19BtoBサイトでおすすめの制作会社15選|BtoBビジネスで成功するには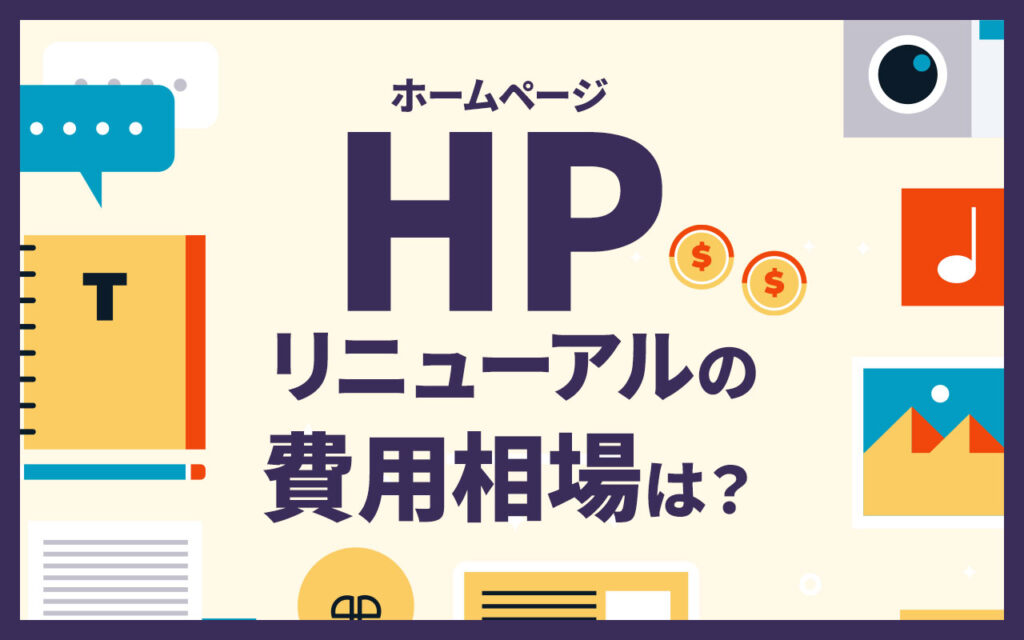
- Web制作
2025/10/2ホームページリニューアルの費用相場は?内訳と安く抑えるポイントを解説
- Web制作
2024/4/28採用サイトの集客方法5選!採用に必要なコンテンツは?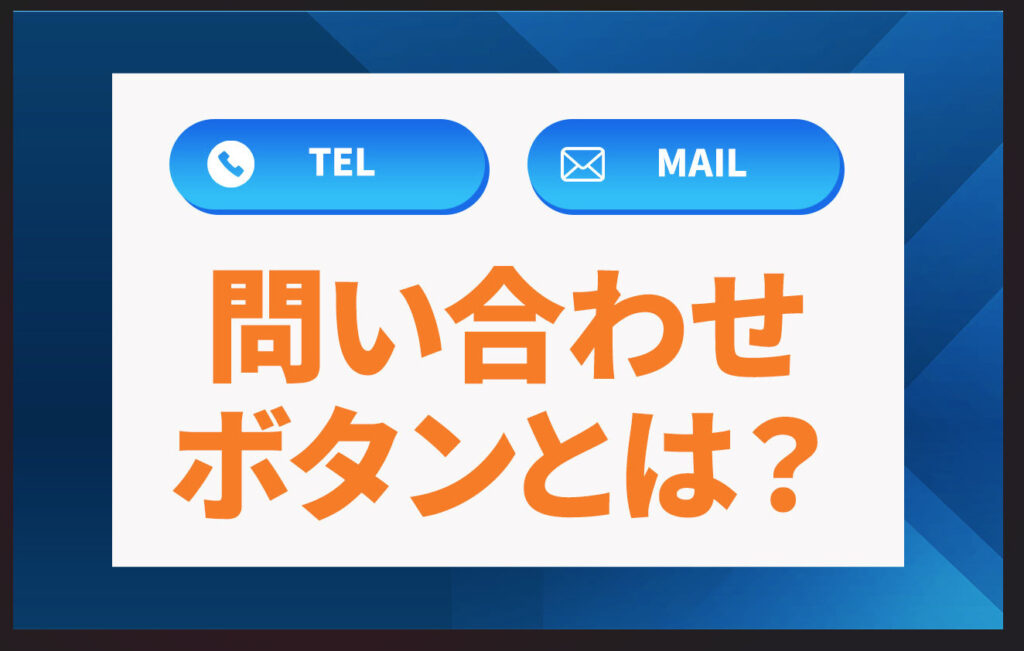
- UX/UIデザイン
2025/11/30問い合わせボタンとは?効果的なデザインと作り方・参考事例10選を徹底解説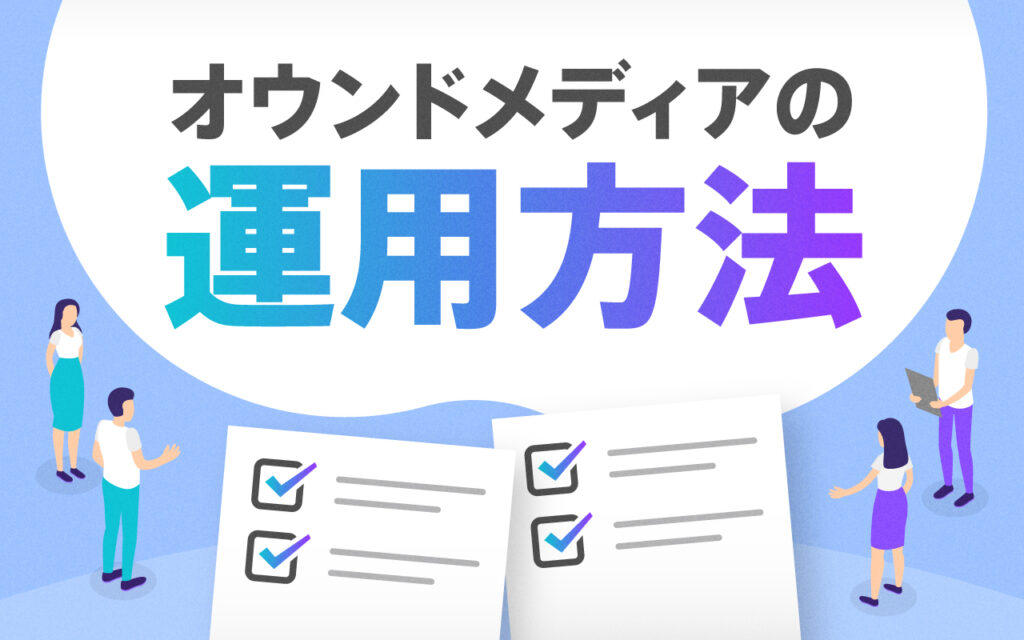
- Web制作
2024/9/19オウンドメディアの運用方法|成果の出るポイントを押さえて運用しよう
- Web制作
2026/1/5ブランドサイト事例15選!デザイン参考例と制作の流れを徹底解説
- Web制作
2025/9/30コーポレートサイトのSEO対策は必要?対策方法や注意点
- Web制作
2024/5/5採用サイトの改善方法とは?課題の見つけ方やリニューアルのポイントについても解説
- コンテンツマーケティング
2024/4/6コンテンツマーケティングの効果的な進め方とは?3つの成功事例も紹介