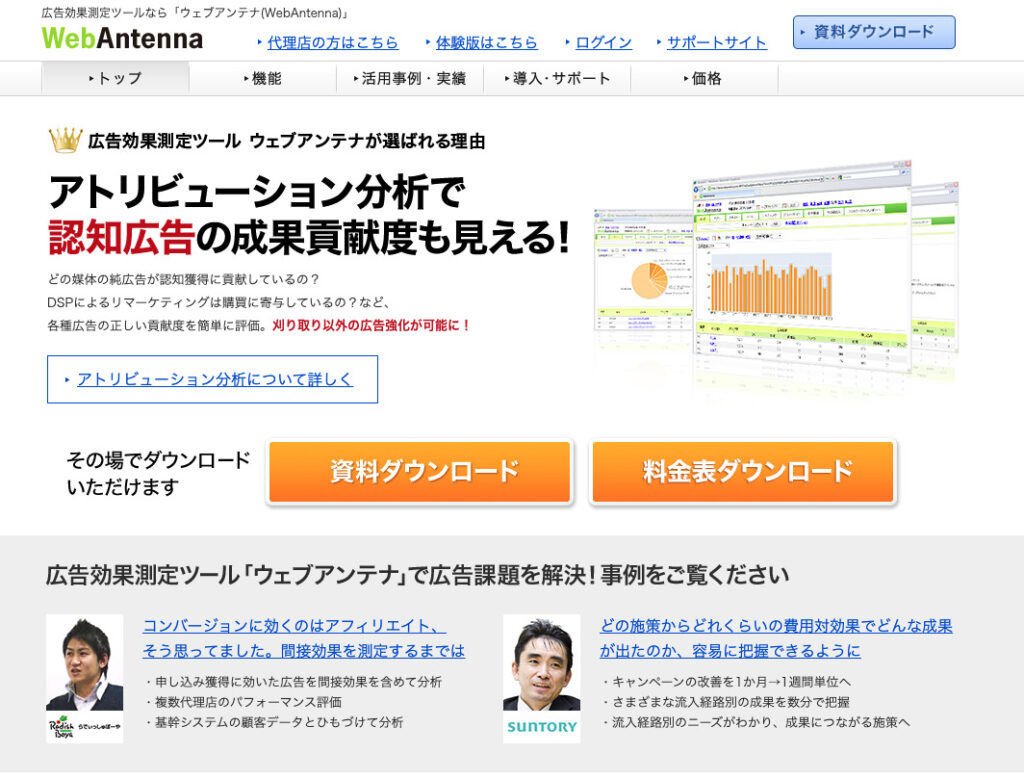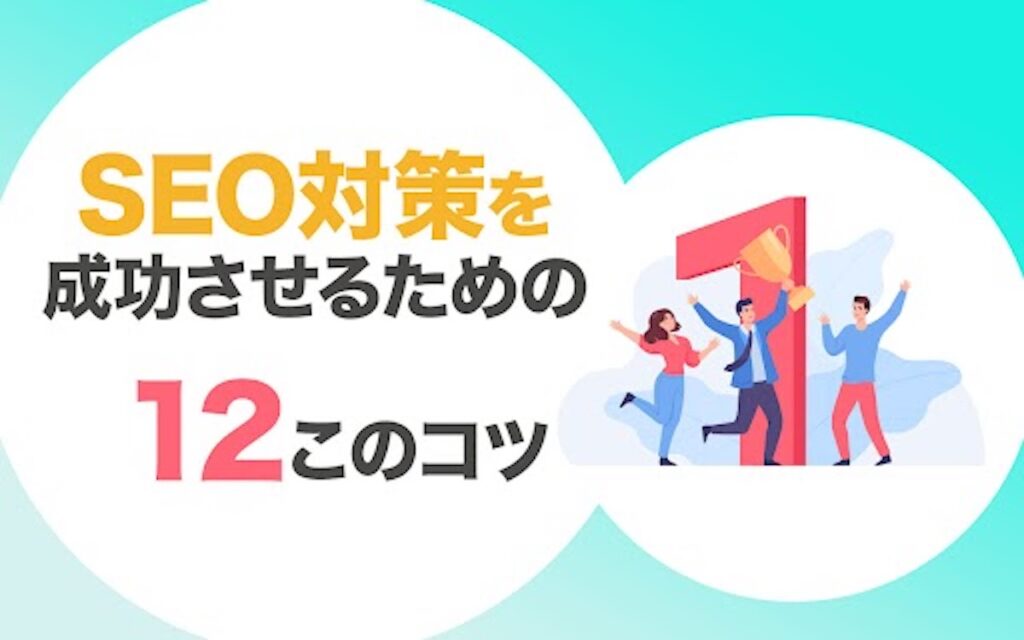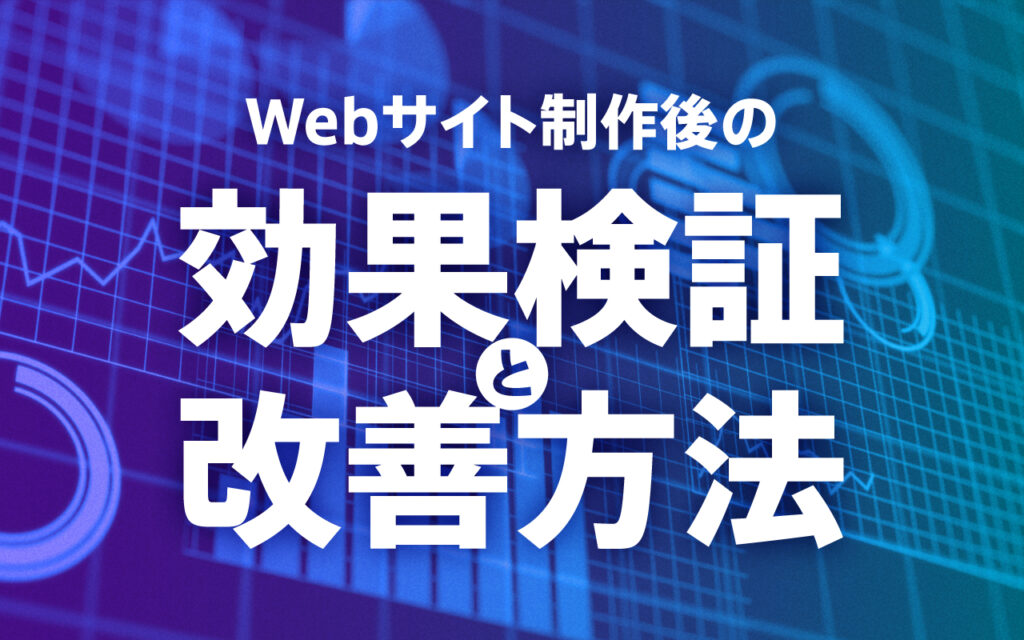
制作してからの効果検証・改善ができていないと辿り着く末路
Webマーケティングにおいて、Webサイトが公開されたということは、ようやくスタートラインに立ったことになります。公開後に継続した効果検証や改善ができておらず、ただインターネット上に公開されているだけのサイトになっていないでしょうか。
- Webサイトの効果検証は何故必要なのか知りたい人
- どのように改善すれば良いのかわからない人
- どのように測定すれば良いのか具体的に知りたい人
今回の記事では、効果検証や改善をしっかりとおこない、Webサイトの本来の目的を達成するための方法について解説していきます。制作後にWebサイトを放置してしまっている企業ご担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
データ分析、UX/UI設計に基づく戦略とデザインで伝えたい価値を伝わるカタチに。
ビジネス成果に貢献するWebサイト制作・構築を提供します。
Webサイト制作後に効果検証・改善ができていないとどうなる?
「Webサイトを制作すれば、自動的に見込み顧客が見に来てくれるはず!」と思っている方もいるかもしれませんが、そう簡単にはいきません。多くのWebサイトはインターネット上で公開されただけでは、ユーザーは集まりません。そればかりか1日のアクセス数は数件にとどまり、高額な制作費が無駄になってしまうことも考えられるでしょう。
そうならないためにも、Webサイト制作後には効果検証や改善が必要になります。それをしなかった場合に、どのようになるか考えてみましょう。
目標としていたアクセス数や成約数に達するのが難しい
Webサイトを制作する際に、想定する目標や数値を設定していたのではないでしょうか。まだ制作されていない方は、どのくらいのアクセス数があって、どのくらいの問い合わせを獲得して、どのくらいの売り上げにつながるのが理想か目標を設定するようにしましょう。
これらの数値はWebサイト制作後に計測しておく必要があり、目標に対しての進捗度合いや達成率を把握しなければなりません。それができていないと、Webサイトを制作したことがが良かったのか悪かったのかも分からず、今後のWebマーケティングにおける改善施策も見つけることができず、見込み客をずっと増やせないことにもつながってしまいます。
逆にしっかりと日々計測をして分析ができていれば、改善する方法や方針も見出すことができるので、改善施策も思いつくことができるでしょう。継続的に目標を達成している企業のWebサイトはそうした取り組みがしっかりできている企業なのです。
ニーズを把握できずユーザー離れにつながる

Webサイトの分析と検証ができていないと、ユーザーのニーズを把握できず、アクセス数を増やすこともできなくなります。不要なコンテンツが多く、求めている情報に辿り着かないようなサイトにユーザーは再び戻ってくることはありません。
たとえば、どのようなコンテンツがよく見られているのか、逆に見られていないコンテンツはどのページかといったデータがわかれば、Webサイトの改善をすることができます。必要な情報を追加し、不要な情報は更新、修正していくといった改善を繰り返していくことで、Webサイトがより良いものに洗練され、さらにファンを獲得することにつながります。
ユーザーが離れてしまわないためにも、Webサイトのデータからユーザーのニーズを把握するようにしましょう。
コンテンツや導線が適切か確認できない
必要なコンテンツだけあれば良いかといえば、そうでもありません。コンテンツが充実していることはもちろん重要ですが、そのページにアクセスするまでの導線についても考慮する必要があります。
Webサイトにアクセスするユーザーは、少なくとも1日数百~数千人程度になります。多ければ数万人以上になることもあるのです。ユーザー全員が、スムーズに各々が求めているコンテンツに辿り着けるわけではありません。なかなか見つからずに、途中で諦めてしまうユーザーが多いのも実状です。
Webサイトの分析ができなければ、そうした状況を把握することができず、ユーザーにはストレスばかり与えるサイトになってしまいかねません。
Webサイトの制作後におこないたい効果検証の種類

Webサイトの効果検証について、未実施によるデメリットは大きく、前項ではその重要性について解説してきました。効果検証の種類には大きく以下の2つがあります。
- アクセス解析
- 広告の効果測定
こちらの2つについて詳細に紹介していきます。
アクセス解析
サイト制作後におこないたい効果検証のひとつ目は、アクセス解析です。アクセス解析では、どのような経路でユーザーがアクセスしてきていて、どのコンテンツを閲覧して、離脱しているのかがわかります。これらのデータをもとにWebサイトの改善が可能になります。
たとえば、よく閲覧されているコンテンツはニーズが多いと考えられるため、より目立つ位置に配置することでユーザビリティが高まります。逆に、離脱しているページはニーズがない・見にくい・わかりにくいなどの原因が考えられますので、修正したり内容を変更したりする必要があります。
また、性別や年齢などのユーザー属性を分析できるのもアクセス解析の特徴です。どの属性のユーザーがアクセスしてきているのかを把握することで、必要なコンテンツを制作し提供することも可能になります。
サイト制作におけるアクセス解析ツールについて詳しく知りたい場合は、こちらの記事もご覧ください。
広告の効果測定
もうひとつの効果検証の種類としては、広告の効果測定があります。アクセス解析とは異なり、広告に特化しているため、広告効果を把握するのに重要になります。
Web広告では広告の表示回数やクリック数などのデータを管理画面上から取得できるものが多くなっています。しかし、そのデータだけでは実際に受注につながっているのかどうかわかりません。
そのため、より正確なデータを取得するためには、購入や問い合わせに至ったコンバージョン件数〜受注までの細かい部分を計測する必要があります。
どの媒体からコンバージョンが獲得できているのか、効果の高い広告メニューが何かを把握することで、広告効果の改善をすることが可能になります。無駄な広告費を削減し、より確度の高いユーザーを獲得できる確率が高くなるため、Web広告を配信している場合には必須の効果測定といえるでしょう。
Webサイトの効果測定における各数値の見方

Webサイトの効果測定ではわかりにくい用語が多いので、主要な数値について解説しておきます。いずれも重要な指標となりますので、特にコンテンツを作成する前に、それぞれの想定値を確認しておくと良いでしょう。
CPA|新規顧客の獲得単価
CPAとは、Cost Per Acquisition(コストパーアクイシジョン)もしくはCost Per Action(コストパーアクション)のことで、広告による顧客獲得単価を指します。一人の顧客を獲得するためにかかった費用のことであり、計算式ではコスト÷コンバージョン数で求めることができます。
資料請求やお問い合わせを獲得することが目的のBtoBサイト、商品の購入をしてもらうことが目的のECサイトでは特に重要になります。
CPAが低いほど少ない費用で顧客を獲得できているので、効率的なリード獲得ができているといえます。逆にCPAが高ければ自社のターゲットにリーチできていない可能性が考えられ、無駄な情報発信が多くなっていることが分かります。
またCVR(コンバージョン率)を改善することも考えるようにしてください。ユーザーに購入や問い合わせなどのアクションを起こしてもらいやすい工夫をすると良いでしょう。具体的にはコンバージョンに誘導するためのボタンを分かりやすくクリックしやすいものにするなどが考えられます。
CTR|クリック率
CTRとは、Click Through Rate(クリックスルーレート)のことで、コンテンツやサイト内の各ページがクリックされた割合を指します。日本語ではクリック率と呼ばれ、クリック数÷表示回数×100(%)で計算されます。
クリック率はターゲティングやコンテンツの品質によって大きく左右されます。ターゲットと情報の内容がマッチしているとクリック率は高くなりやすいので、それぞれ考えて設定することが大事になります。
たとえば、男性には男性用のキーワードやテーマ(かっこいい、高級感など)、女性には女性用のキーワードやテーマ(かわいい、綺麗など)を準備します。各コンテンツにターゲティングをそれぞれ適切に設定することで、クリック率は上昇することになります。
CVR|コンバージョン率・成約率
CVRとは、Conversion Rate(コンバージョンレート)のことで、クリックされた広告のうち顧客獲得に至った割合を指します。日本語ではコンバージョン率と呼ばれ、コンバージョン数÷クリック数×100(%)で計算されます。
CVRが高いほど、効率よくリードが獲得できていることを示しています。クリック単価が100円の場合、CVRが1%とするとCPAは10,000円になりますが、CVRが0.1%となるとCPAは100,000円となります。
CVRを左右する要素としては、大きくランディングページ(LP)とターゲットがあります。LPではユーザーにアクションしてもらうためのセールスライティングが必要になり、上手く誘導しなければCVRは高まりません。またLPに誘導するターゲットが異なっていては、いかにセールスが良くても興味を持たれないため、コンバージョンに至ることはないでしょう。
目標とするCPAを維持するためにはCPCがいくらで、CVRがどのくらいになるかをシミュレーションしておくとその後の改善もスムーズです。
効果検証後のWebサイトの改善方法

次に、Webサイトの効果検証後に具体的な改善方法を紹介していきます。効果検証ができても専門的な知識や経験がなければ施策を考えることはできないため、他社の事例などを参考にしながら対応を進めるようにしましょう。
サイトのページビューが少ない場合
まず、Webサイトの効果検証において基本的なページビュー数(PV数)が少ない場合に考えるべき施策には、SEO対策とコンテンツ作成があります。
SEOとはSearch Engine Optimizationのことで、検索結果の上位表示を目指す施策を指します。検索広告とは異なり、SEO対策することで上位表示を達成した場合には、広告費用を掛けることなく、多くのトラフィックが期待できます。また狙ったキーワードでのアクセス数が増えれば、コンバージョン数の大幅な増加が期待できます。
コンテンツを作成することで、多くのページが閲覧されるため、PV数を増やすことにつながります。ただ単にコンテンツがあれば良いというものでもなく、しっかりとユーザーのニーズを捉えて、充実した情報を提供する必要があるでしょう。
それぞれについて、もっと詳しく見ていきましょう。
SEO対策の強化
具体的なSEO対策には、内部施策と外部施策があります。
内部施策は、タイトルタグ・見出しタグなどのHTMLタグを正しく使うこと、適切な内部リンクをページ内に張り巡らせる施策などがあります。 しかし、内部施策をしたからといって必ず上位表示できるというものではなく、あくまで検索エンジンのアルゴリズムによってランキングが決定されます。
一方で、外部施策は他サイトから被リンクを獲得することを指します。被リンクの獲得はWebサイトの評価を上げることになり、上位表示されやすくなります。ただし、意図的に被リンクを操作することは禁止されているので、特に他サイトから被リンクを購入すると、逆にランキングを下げる要因にもなるので注意が必要です。
ユーザーニーズを満たすコンテンツを作成
ユーザーの興味を満たすようなコンテンツを制作していくと、Webサイト内の回遊率が高まるので、PV数の上昇に貢献することになります。また1ユーザーが1ページだけを閲覧させるのではなく、関連するページを表示させることで、2ページ3ページと読み進めてもらうような導線を作るのも良いでしょう。
1ユーザー当たりのPV数は平均PV数と呼ばれますが、コンテンツが充実しているかどうかを表す指標ともいえます。少ないアクセスであっても、なるべく平均PV数を高めてWebサイト内を回遊してもらうことができれば、全体のPV数を上昇させることが可能になるのです。
また、ユーザーのニーズを満たすコンテンツはSEO対策にもつながります。ユーザーが何を探しているのか、何を求めているのかを把握してコンテンツに落とし込むことで、検索エンジンにも評価されることになるのです。
サイトの離脱率が高い場合
前項では、サイトのPV数が少ない場合を解説してきましたが、次にサイトの離脱率が高い場合の改善施策について紹介していきます。離脱率が高いということは、ページ内に求めているコンテンツがないとユーザーに判断された、あるいはユーザーに強いストレスを与えてしまったことなどが原因として考えられます。
いずれにしても離脱率が高いことはWebサイトにとって望ましいことではなく、改善の余地があることを意味しています。
ちなみに広告のリンク先として1ページで構成されるランディングページ(LP)もありますが、その場合はスクロール率によって離脱率を判断します。なるべくスクロールして読んでもらうように改善をすることが重要です。
ファーストビューの改善
離脱率を下げるためには、ページ内に重要なコンテンツが含まれていることを最初にユーザーに伝える必要があります。ページ内で最初にユーザーの目に入る箇所をファーストビューと呼びますが、ファーストビューではユーザーを惹きつけるコンテンツが求められます。
具体的にはキャッチコピーやメインビジュアルになりますが、自分に関係している情報がページ内に含まれていることや先を読んでみたくなるようなテキスト・画像が含まれていると良いでしょう。
そのためには、Webサイトにどのようなユーザーがどういう意図をもってアクセスしてきているかを把握するようにしましょう。検索キーワードは何か、SNSではどの媒体かなどはファーストビューを考える上で重要なデータとなります。
ファーストビューのデザインについて詳しく知りたい場合は、こちらの記事もご覧ください。
表示速度の改善
離脱率を下げるのに大事なことはコンテンツだけではなく、ページの表示速度も重要になります。ユーザーはページにアクセスしてから、わずか数秒の間にコンテンツを読み進めるかどうかを判断します。少しでもストレスを感じてしまうと、離脱につながるので細心の注意を払う必要があります。
ページの表示速度を改善するためには、不要なファイルや大容量のファイルをブラウザに読み込ませないようにします。あるいは、ページ全体を表示させた後でファイルを読み込ませると良いでしょう。
サイトの離脱率の改善について紹介していますが、ページ表示速度の改善はユーザビリティを高めるため、SEO対策にもなります。自然検索結果の上位に表示されればアクセス数も増加しますので、是非とも取り組んでおきたい施策の一つと言えます。
表示速度の改善についてより詳しく知りたい人は、こちらの記事もご覧ください。
CVRが低い場合
PV数が増加し、離脱率が下がっても、肝心のコンバージョンが増加しなくては売り上げが増加することはありません。アクセスしたユーザーを効率よく顧客にすることが求められます。
CVRはコンバージョンの種類(資料請求、会員登録、購入など)や商材によっても異なりますが、平均的には1%~3%程度と言われています。つまり、100人がWebサイトに訪問した時のコンバージョン数は1件~3件程度ということになります。またクリック単価が100円とすると100人のユーザーを集めるのに10,000円が必要になり、CPAは3,333円~10,000円に収まります。
目標とするCPAに達していない場合には、CVRを上げるために、以下の施策を実行してみてください。
サイト内の導線を改善
まず、サイト内でユーザーが迷わないように、購入や問い合わせまでの導線を作り上げましょう。インターネットユーザーは、思いの外しっかりとWebサイトを見ているわけではないため、次のステップへのリンクやフォームまでのボタンを見逃してしまうことが多くなっています。
起こして欲しいアクションまでの道のりを、できるだけわかりやすく示してあげてください。
具体的な導線の改善方法には、リンクのテキストをユーザーが目を止めるように「無料」や「プレゼント」といった文言にしたり、フォームボタンのデザインを変えたり、追尾型にしたりするのがおすすめです。
動線設計についてより詳しく知りたい場合は、こちらの記事もご覧ください。
問い合わせフォームのデザインを改善
導線を改善してフォームまで誘導しても、フォーム内で離脱してしまうユーザーも一定数います。せっかく興味を持って問い合わせをしようとしてくれたユーザーを離脱させてしまうのは、大きな損失となるので、しっかりフォーム送信までしてもらうように改善しなくてはなりません。
問い合わせしようとした時にフォームの入力項目が多く、途中で止めてしまった経験はないでしょうか。多くの問い合わせフォームでは沢山の入力項目があり、ユーザーにストレスを与えてしまっています。その結果、フォームでの離脱を招いてしまっていると言えます。
入力項目は必要最低限にしてスムーズに送信完了できるように工夫します。また住所などは郵便番号からの自動入力機能を付けたり、送信完了までのステップをわかりやすくしておくことで、ユーザーのストレスを軽減することになります。
サイト内の導線にしても、フォームデザインの改善にしても、分析と検証を繰り返し改善をしていくようにしましょう。
効果測定&サイト改善に役立つツール4選
ここまで効果改善の重要性や具体的な施策などを解説してきましたが、最後に各社から提供されている効果測定のために役立つツールを紹介します。いずれも導入実績が豊富にあるので、サイト改善には役立ちますが、すべてを導入する必要はありません。自社に合った必要なものを活用するようにしてください。
Google Analytics
Google Analytics(グーグルアナリティクス)は、アクセス解析ツールの定番とも言えるもので、多くの企業に利用されています。一般的にGA(ジーエー)と称されることもあり、Webマーケティングに携わっている人であれば一度は聞いたことがあるはずです。
名前の通り、Googleが提供しているツールになるため、Google広告との相性も良く、連携することで様々なデータを活用することができます。費用は無料になるので、Googleアカウントを作成すれば誰でも利用することができます。
無料のツールになるので、Googleからのサポートはありません。分からないことがあれば自分で調べて解決するしかありませんので、全くの未経験者では導入までに時間が掛かってしまうかもしれません。どうしても自社では対応できないという場合には、Webサイトの制作会社やWeb広告の運用会社であれば対応してくれるかもしれませんので、依頼をしてみると良いでしょう。
基本的なPV数やUU数はもちろん把握することができ、Googleが所有している膨大なデータからWebサイトに訪問しているユーザーの性別や年齢などを推定し、レポートしてくれます。これらのデータはWebサイトの改善にも貢献し、また場合によっては商品企画や全体のマーケティングにも使えるでしょう。
AD EBis
AD EBis(アドエビス)は広告効果測定ツールのひとつで、東証グロース市場に上場する株式会社イルグルムが提供するサービスです。アクセス解析ツールだけでは分析しづらい広告効果も分かりやすくレポーティングしてくれます。
AD EBisでは、どの広告媒体からコンバージョンしているのか分析するのに役立ちます。それだけではなく、アトリビューションの分析も可能です。アトリビューションとは広告クリックのコンバージョン貢献度のことで、ラストクリックだけではなく、初回クリックなどを評価することで、全体の広告を最適化することができます。
AD EBisを利用するためにはWebサイトに計測タグを設置する必要があります。また広告のリンク先URLにはAD EBisから発行されるパラメータを付与します。これら二つの準備が整えば、コンバージョンのデータを取得し計測することができるようになります。
AD EBisの料金は初期費用は無料で、月額料金は定額料金+従量課金制になっています。プランによって変動しますので、詳しくは公式サイトよりお問い合わせください。
Web Antenna
Web Antenna(ウェブアンテナ)はAD EBisと同じ広告測定ツールで、株式会社ビービットが提供しています。基本的な機能として大きな違いはありませんが、オプションや細かい仕様の違いがあると思いますので、導入前に問い合わせをして目的に合った分析ができるかどうかを把握するようにしてください。
Web Antennaの料金は初期費用は無料というのはAD EBisと同じで、月額料金は2万円〜の従量課金となっています。低価格で導入しやすいので、中小企業にも活用しやすいサービスと言えるのではないでしょうか。
Google Analyticsのような無料ツールではサポートがないため、知識のある担当者が必要になりますが、Web AntennaやAD EBisといった有料のツールではサポートが充実しています。Webマーケティング未経験であっても安心して導入できるのが大きなメリットです。
公式サイトには活用事例が豊富に用意されているので、同じ業界の事例などは参考にしてみると良いかと思います。
コールトラッカー
Web AntennaやAD EBisでは計測できないものにユーザーからの電話を受信することによるコンバージョンがあります。広告クリックを起点にし、Web上での動きを計測しているため、Webサイトを見て電話してきたユーザーを分析評価することが難しいと言えます。
コールトラッカーという広告測定ツールでは、広告を経由して電話をしてきたユーザーを判別しコンバージョンとしてカウントできます。今まで計測できていなかった電話コンバージョンが測定できれば、正しく広告効果を分析することができ、Webマーケティング戦略の最適化をすることができます。
特にユーザーから電話を受けることの多い業界や商材には必要なツールと言えます。利用料金は0円で利用できるフリートライアルプランから月額6,500円から利用できるスターターパックなどがあるので、中小企業から大手企業まで利用しやすい価格帯となっています。
コールトラッカーではWeb広告だけではなく、チラシや看板などのオフライン広告にも活用できます。様々な広告を実施していて、どの広告効果が高いのか明確にしたい場合には導入をご検討ください。
サイト制作後の長期運用ならTHINkBALにお任せください

サイト制作後には効果検証や改善が必要になりますが、一度や二度の施策で効果が表れることはあまり多くありません。Webサイトの運用は中長期的な視点で考える必要があり、効率的にするには知識や経験の豊富なプロに依頼するのが最短です。
THNIkBALではWebサイトの長期運用をサポートをしている豊富な実績があります。制作した後に何をしたら良いか分からない、効果が改善しなくて困っている企業のご担当者様は是非ご相談ください。
まとめ
Webサイトの効果検証ができていないと当初の目的を達成することができず、制作費が無駄になってしまいかねません。そうならないためにも効果測定ツールを導入し、ボトルネックとなっている箇所を究明し、考えられる改善施策を実行するようにしましょう。
- サイト制作後の効果検証、改善の重要性
- 具体的なWebサイトの改善施策
- 自社に合った効果測定ツールを導入する
またWebサイトの運用は改善施策を実行して、すぐに効果が表れるものではありません。短期的に見るのではなく、中長期的な視点を持って戦略的に進めるようにしてください。

Relation 関連記事
What's New 新着情報

- マーケティング
2025/6/30【プロが解説】Webマーケティングとは?3つの種類と効果の出る施策を徹底解説!
- Web制作
2025/6/28リスティング広告の「ランディングページ」とは?必要なシーンや設置場所、作成のポイントを解説
- コンテンツマーケティング
2025/6/28コンテンツマーケティングが失敗しそう…|原因と解決策を徹底解説
- Web制作
2025/6/28LP(ランディングページ)制作会社11社を厳選|特徴別に詳しく紹介
- Web制作
2025/6/28ランディングページの制作費用の相場は?内訳や料金事例を徹底解説
- Web制作
2025/6/28コーポレートサイトでブランディングできる?5つの効果と実践方法を解説
Recommend オススメ記事
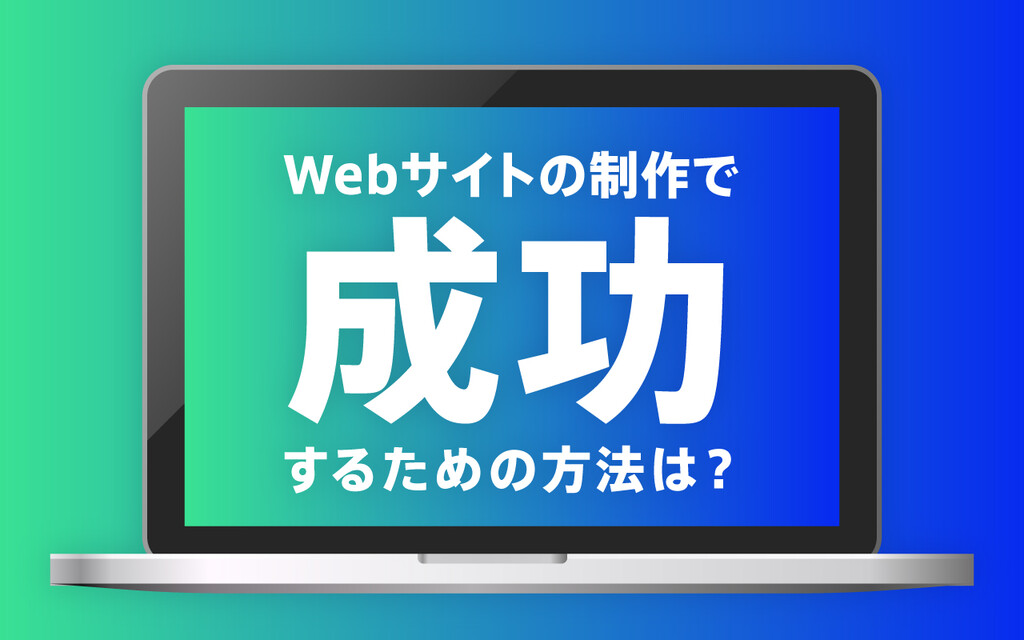
- Web制作
2024/7/1BtoBサイトでおすすめの制作会社14選|BtoBビジネスで成功するには
- Web制作
2024/4/13ホームページリニューアルの費用の相場は?流れ、メリットデメリット、ポイントを解説
- Web制作
2024/4/28採用サイトの集客方法5選!採用に必要なコンテンツは?
- UX/UIデザイン
2024/9/28サイトの問い合わせを増やす施策を8つ紹介!CTAボタンの設置方法も解説!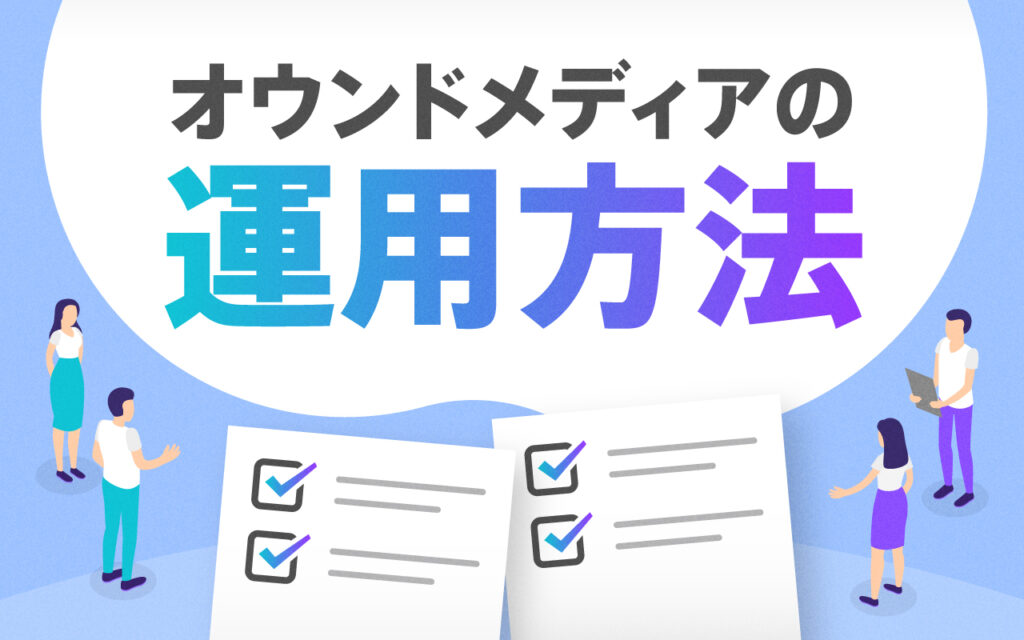
- Web制作
2024/9/19オウンドメディアの運用方法|成果の出るポイントを押さえて運用しよう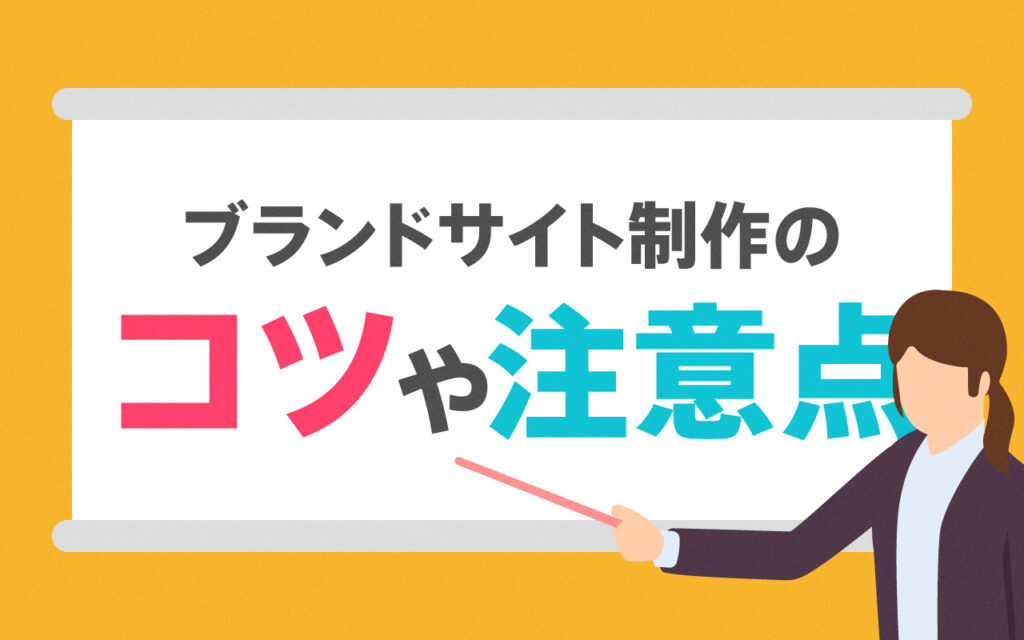
- Web制作
2024/4/28ブランドサイト参考事例10選!制作のコツや注意点についても解説
- Web制作
2024/5/5コーポレートサイトのSEO対策は必要?対策方法や注意点
- Web制作
2024/5/5採用サイトの改善方法とは?課題の見つけ方やリニューアルのポイントについても解説
- コンテンツマーケティング
2024/4/6コンテンツマーケティングの効果的な進め方とは?3つの成功事例も紹介